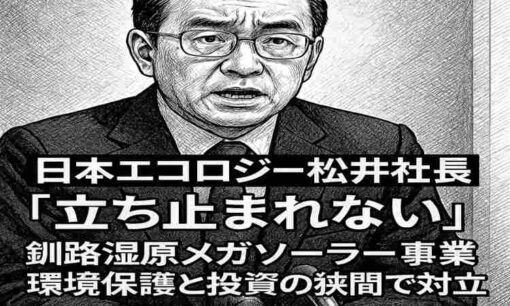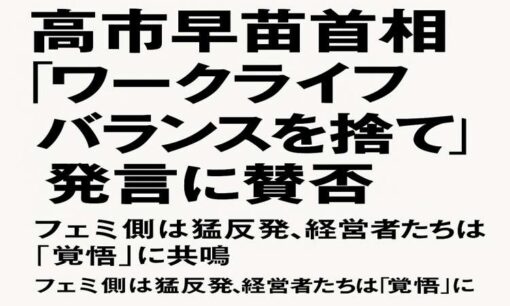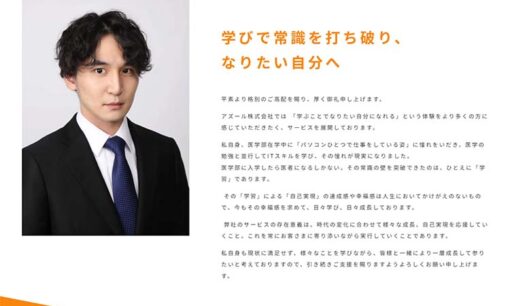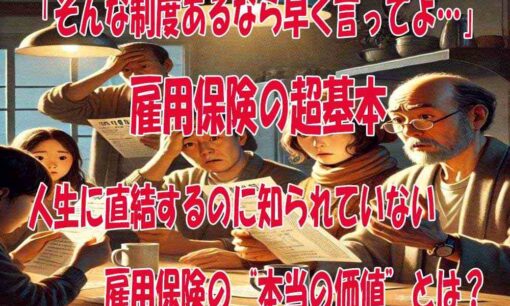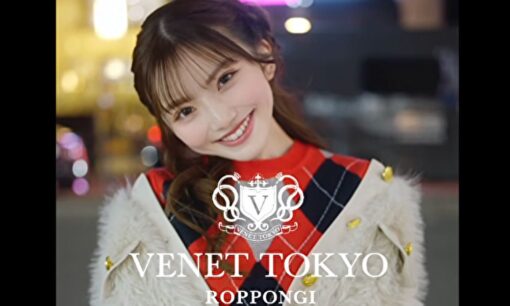自民党の新総裁に就任した高市早苗氏が掲げる「太陽光発電支援制度の見直し」発言が波紋を広げている。7日の閣議後記者会見で、武藤容治経済産業相は「政府としては地域との共生や技術の自立化を図った上で、再生可能エネルギーの導入を進めていくことも重要」と語り、慎重な姿勢を示した。
高市氏は総裁選のさなか、国内の太陽光パネル市場の大半を占める中国製品を念頭に「私たちの美しい国土を外国製パネルで埋め尽くすことには猛反対」と訴えた。さらに「これは歪んだ補助金の結果だ」と強調し、補助制度の根本的な見直しを明言。環境政策を政権の再構築テーマとして掲げた形だ。
経産省は一方で、「地域の合意形成や国際的枠組みとの整合性を欠くことはできない」と慎重論を崩さない。政策の方向性をめぐり、政権内にも微妙な温度差が生まれつつある。
補助金が生んだ“再エネ利権”の構図
かつて「国を挙げた脱炭素の希望」とされた再エネ政策だが、裏側では補助金ビジネスが膨張し、今や「再エネ利権」と呼ばれる構造が根を張っている。
固定価格買取制度(FIT)によって、電力会社が再エネ電力を買い取り、その費用を電気料金に上乗せして国民が負担する仕組みが導入されたのは2012年。制度の趣旨は再エネ導入の促進だったが、実際には一部の事業者や投資ファンドが巨額の利益を得る結果となった。
「環境支援」を掲げるNPOや政治家の親族が関わる財団が補助金を得ていた例もあり、制度はいつしか透明性を失った。あるエネルギー関係者は語る。
「理念先行で仕組みを作った結果、補助金を巡る利権が政治と経済の境界を曖昧にした。再エネが“環境”ではなく“票と金の動線”になってしまったのです」
高市氏が「ゆがんだ補助金」と呼んだのは、こうした制度疲労を意味している。国が掲げたクリーンエネルギー政策の裏で、金の流れが歪み、信頼が損なわれた現実がある。
“見えない増税”再エネ賦課金 家計を圧迫する静かな負担
太陽光発電のもう一つの歪みが「再エネ賦課金」だ。
家庭の電気料金には、1キロワット時あたり3.49円(2024年度時点)の再エネ賦課金が上乗せされている。一般家庭で年間およそ1万円。環境のために支払う負担金として導入されたが、その金額は年々上昇を続けている。
SNSでは「再エネ賦課金という庶民へのボディブローをやめてほしい」「これを止めたら自民党を見直す」といった投稿が相次ぐ。電気料金の高止まりに拍車がかかる中で、「エコの名を借りた隠れ増税」と受け止める国民も少なくない。
高市氏の発言がここまで注目を集めたのは、単なる環境論争ではなく、この“家計への直撃”という現実的な痛みが背景にあるからだ。理想のエネルギー政策と生活者の実感との乖離が、いまや政治的テーマになりつつある。
再エネが進むほど強まる中国依存 クリーンの裏に潜むリスク
太陽光発電のもう一つの課題は、圧倒的な中国依存構造である。
日本で設置されている太陽光パネルの約8割は中国製。原料となるシリコンの多くが新疆ウイグル自治区産とされ、強制労働問題が国際的に取り沙汰されている。米国では輸入規制が敷かれているが、日本では依然として対策が遅れている。
経済安全保障の専門家は警鐘を鳴らす。
「太陽光パネルのサプライチェーンは中国がほぼ独占しており、再エネを進めるほど依存度が高まる構造になっている。エネルギー政策が他国の産業支援になっているのが現状だ」
環境政策の裏で進行するこの“静かな支配”を指摘し、「外国製パネルで国土を埋め尽くすことには反対」と語った高市氏の言葉は、愛国的スローガンではなく安全保障上の警告として受け止められている。
SNSで噴出する民意 「利権」「負担」「中国」への怒り
ネット掲示板「ハムスター速報」では、高市氏の発言をめぐり激しい議論が続いている。
「まずはアホみたいに敷き詰めた太陽光パネルがどうなってるか調べろ」「利権と中国の息がかかってる」「何が再生可能エネルギーだ、自然破壊そのものだ」といった投稿が並ぶ。
再エネ賦課金への不満、補助金ビジネスへの嫌悪、そして中国依存への不安――。
三つの要素が結びつき、かつて環境政策の象徴だった太陽光発電が、今や国民の不信の象徴になっている。
「山を禿山にしてまで設置する意味があるのか」「環境のためと言いながら環境を壊している」との声も多い。かつて“エコ”と呼ばれたものが、今では“エゴ”と揶揄される。政策への信頼は、静かに失われつつある。
政府が問われる「誰のための再エネか」
武藤経産相が述べた「地域との共生」「技術の自立化」は、美辞麗句ではなく、現実的な警告でもある。メガソーラーによる山林伐採、景観破壊、土砂崩れなど、全国で問題が続発している。環境を守るはずの政策が、地域の自然をむしばんでいる現実を、国は直視せざるを得ない。
再エネ導入をやめるかどうかではなく、誰のために、何のために推進するのか。
高市政権の「太陽光見直し」は、単なる政策論争を超えて、日本のエネルギー主権を問う一歩になりつつある。利権、負担、依存――その三重の歪みを正せるかが、これからの政治の試金石となるだろう。