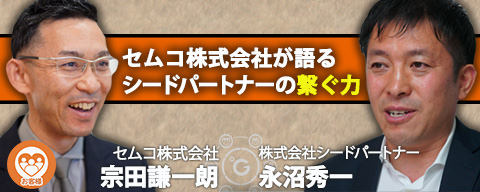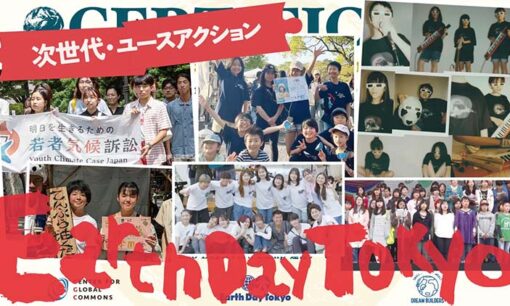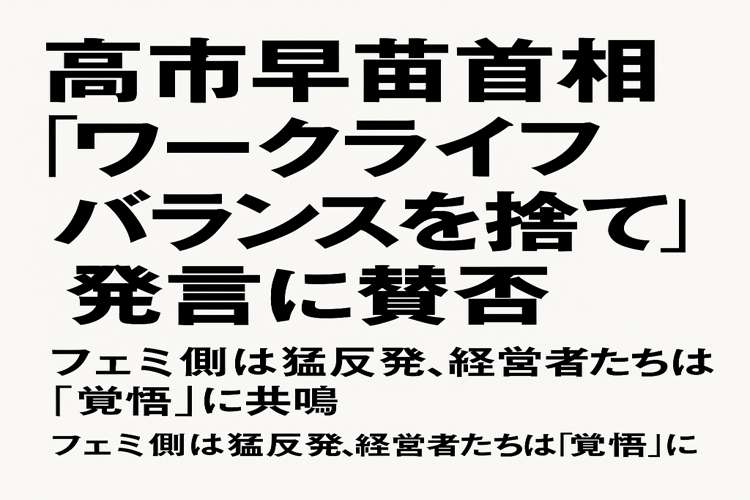
日本初の女性宰相が誕生した10月4日、自民党総裁選で高市早苗氏が小泉進次郎氏との決選投票を制し、自民党初の女性総裁に選ばれた。だが、その喜びの陰で、就任スピーチの一言が国内外の議論を呼び起こしている。
「だって今、人数少ないですし、全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて参ります」
この発言をめぐり、称賛と批判が入り乱れ、SNS上は大荒れとなった。
賛否には、いまの日本が抱える「働き方」と「価値観」の分断が見え隠れする。
フェミニスト界隈からの拒絶反応
「恐ろしい時代に入った」――。一般社団法人Colabo代表の仁藤夢乃氏は、X(旧Twitter)でこう綴った。「筋金入りのレイシストが日本初の女性総理大臣になってしまった。女性や子ども、あらゆる人々の人権が守られる社会からますます遠ざかると思う」
また、在外日本人の坂井京子氏は「ワークライフバランスなんて捨てて」という発言に失望をにじませた。
「ニュージーランドのアーダーン元首相は任期中に育休を取り、世界に希望を与えた。私は、そういう希望を感じさせる“女性初”を見たかった」と投稿している。
さらにジャーナリストの朝岡晶子氏も「女性初の就任がこんなに嬉しくないなんて…。日本社会の右傾化を止めなければ」と記した。
“女性初の首相誕生”という歴史的な出来事に素直な祝福が集まらない。そこに、ジェンダーをめぐる日本社会の根深い断層が浮かび上がる。
「またTBSの偏向報道か」報道の切り取りに疑問の声
一方で、報道機関の伝え方に対しても不満が噴出した。
TBSが高市氏の発言を報じる際、街頭で子育て中の母親に「子育てしながら働くのはしんどい」と語らせたシーンを放送。これに対し、SNS上では「文脈を無視した偏向報道だ」と批判が殺到した。
「彼女は国民にではなく、自民党議員に“馬車馬のように働こう”と呼びかけた。それを“国民に向けたメッセージ”のように編集するのは印象操作だ」
「またTBSか」とのコメントが並び、メディア不信の火種となっている。
発言の対象をすり替える報道姿勢に対し、「政治家の覚悟が“国民の負担”として映される構図こそ、時代遅れだ」との指摘も出ている。
経営者たちは歓迎「働ける自由を取り戻せ」
高市首相の発言は、経営者層にはむしろ歓迎された。参政党の梅村みずほ議員は「本人が望むなら“とことん働ける自由”を日本に取り戻すべき」と投稿。
実業家の三崎優太氏(元青汁王子)は「高市さんの言葉には強い覚悟を感じた。経営者も休日を返上して死ぬ気で働こう。日本企業の成長こそ、日本を救う特効薬だ」と呼びかけた。
投資家の上岡正明氏も「勤労勤勉は成果の基礎。就任早々としては悪くない言葉」と支持を表明した。
さらに、格闘技イベント「BreakingDown」のCOO・溝口勇児氏も反応した。「高市さんの目、表情、言葉の節々に“覚悟”を感じる。この火を国民が消すのか、それとも共に燃やすのか。国のトップが“ワークライフバランスなんて無視して働く”と宣言している今、政治も経済も現場も、全員が同じ覚悟で挑むべきだと思う」
この投稿は拡散され、多くのビジネスパーソンが「共に燃えよう」と賛同した。「働くことが誇りに変わる社会を取り戻したい」との思いが、経営層の間で広がりつつある。
「働く自由」をめぐる再考 “休む権利”と“働く誇り”のあいだで
サステナビリティの文脈でも、ワークライフバランスの重要性が声高に語られて久しい。
だが、現実の日本経済を見れば、中国や韓国に生産性で抜かれ、企業の足腰は確実に弱っている。上場企業の業績は表面上よいように見えても、その下には疲弊した中小企業の存在がある。しわ寄せは常に現場に向かい、そこにいる労働者たちが静かに倒れていく。
かつて日本を支えた勤勉さや誠実さは、いつの間にか“古臭い価値観”として片づけられた。権利を主張する声ばかりが大きくなり、結果として、真面目に働く人間が損をする社会になってしまってはいないか。
ワークライフバランスという理念は尊いが、それを過度に尊重しすぎたことで、働く自由まで制限してしまった側面もある。実際、ある年代には「もっと働きたい」「成長したい」という意欲を持つ人が多い。にもかかわらず、労働時間規制や企業の過剰なコンプライアンス運用、そして“働かせないことが美徳”とされる風潮が、その意欲を押しとどめている。
いま必要なのは、“働かされる社会”からの脱却ではなく、“働けない社会”からの脱出だ。勤労意欲がある人にはその分の報酬と評価を与え、ライフステージに応じて柔軟に働き方を選べる環境を整える。
それが、本来あるべきワークライフバランスの姿ではないか。
真剣に働くことが再び誇りとされる社会へ。日本が再び成長のエネルギーを取り戻すには、単なる制度改革ではなく、「働くことの価値」そのものをもう一度見つめ直す時期に来ている。