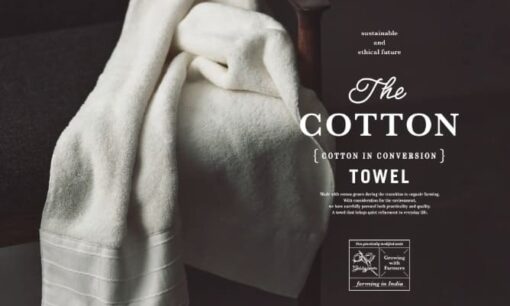デジタル庁は2025年9月26日、大手コンサルティングファームのアクセンチュア株式会社に対し、新規の入札や契約から4カ月間除外する指名停止処分を下した。日本のデジタル化を推進する要であるデジタル庁と、世界的なITコンサルティング企業であるアクセンチュア。両者の間に何があったのか。
デジタル庁とアクセンチュアとの関係性
まず、今回の問題の核心を理解するために、デジタル庁とアクセンチュアの過去の取引を振り返る必要がある。両者はこれまで、日本の行政サービスのデジタル化という共通のミッションを担うパートナーとして、数々の大型プロジェクトをともに進めてきた。特に、今回の指名停止の原因となった「情報提供等記録開示システム」の開発・運用業務は、その象徴的な案件である。
このシステムは、もともと2014年12月に内閣官房社会保障改革担当室によって開発が始まり、2021年9月にデジタル庁へと移管された。以来、システムの開発・運用はデジタル庁が主導し、その重要なパートをアクセンチュアが担ってきた。
2024年度(令和6年度)に契約された「情報提供等記録開示システムに関する設計・開発及び運用・保守業務一式」は、約47億円という巨額の契約であり、「情報提供等記録開示システムバックエンド機能の再構築及び運用保守業務一式」は約169億円という契約金額で締結されている。
これらの契約は、一般競争入札ではなく、特定の事業者と直接契約を結ぶ随意契約という形式が取られていた。これは、システムの複雑性や継続性、そして高度な専門性が求められる案件において、特定の事業者が有利になるケースがあるためだ。デジタル庁の公開情報でも「2014年から継続して追加開発をしてきたシステムであるため、モノシリックな状態になっており、一部を改修するために全体に影響するため費用が高くかかってしまうところ」と説明している。
つまり、長年にわたってシステム開発に関わってきたアクセンチュアは、この複雑なシステムを最も深く理解しており、実質的に他の事業者が参入することが困難な状況であった。デジタル庁としても、円滑なシステム運用のためには、アクセンチュアに頼らざるを得ない側面があったと見られる。
なぜ「指名停止」処分に?
今回の指名停止処分の直接的な原因は、契約に違反して業務を無断で再委託したことにある。
デジタル庁の発表資料によると、アクセンチュアは「情報提供等記録開示システム」に関する業務の履行において、契約書で定められた再委託の申請を怠り、複数の下請け企業(A社他数社)に無断で業務を再委託していた。
契約社会において、再委託は珍しいことではない。特に、大規模なITプロジェクトでは、特定の分野に強みを持つ専門企業に業務の一部を任せることは一般的だ。しかし、今回のケースでは、契約書に「デジタル庁の承認を得て再委託を行うこと」が明記されていたにもかかわらず、アクセンチュアはこれを無視した。
デジタル庁は、この行為を「不正又は不誠実な行為」と認定し、指名停止に踏み切った。この判断の背景には、単なる契約違反以上の重大なリスクが潜んでいる。
参照:指名停止情報 (デジタル庁)
再委託が抱える「国家機密」の闇
なぜ官公庁の案件で再委託が無断で行われることが、それほどまでに問題視されるのか。その理由は、情報セキュリティと国家機密に直結するからだ。
デジタル庁が担う業務は、国民の個人情報や国の重要な機密情報を取り扱うものが多い。「情報提供等記録開示システム」も、その名の通り、機密性の高い情報を取り扱うシステムである。もし、発注元であるデジタル庁が知らないところで、第三者企業に機密情報が渡り、それが万が一、外部に漏洩するようなことがあれば、国家的な問題に発展することも考えられる。
再委託に関する契約条項は、このようなリスクを未然に防ぐための重要な安全装置である。発注者であるデジタル庁は、再委託先の企業の信頼性やセキュリティ体制を厳格に審査し、問題がないと判断した場合にのみ許可を与える。
もちろん、再委託の背景には様々な理由が考えられる。「より効率的に業務を進めるため」「特定の技術を持つ企業に頼る必要があった」など、アクセンチュア側の都合もあっただろう。しかし、いかなる理由であれ、機密保持が最優先される官公庁の契約において、無断での再委託は決して許される行為ではない。
企業にとっての「指名停止」はどれほど重い処分か
今回の指名停止処分は、アクセンチュアにとってどれほどの痛手なのだろうか?
まず、直接的な影響として、デジタル庁が今後4カ月間(令和7年9月26日~令和8年1月25日)に行う新規契約に参加できない。これは、日本の行政IT分野において、巨大なビジネスチャンスを逃すことを意味する。
しかし、より深刻なのは、社会的な信用失墜という側面である。指名停止という処分は、その企業が「ルールを守らない」「不正な行為をした」と公に認められたことを意味する。特に、コンプライアンス(法令遵守)が厳しく問われる現代において、この事実は企業イメージに大きな傷をつける。アクセンチュアはグローバルな巨大企業であり、この信用失墜は国内外の他事業にも波及する懸念がある。
また、今回のデジタル庁の決定は、他の省庁や地方公共団体に対しても、同様の事態が発生していないか契約内容を再確認させるきっかけとなるだろう。
「随意契約」の課題と、今後のデジタル庁の調達方針
今回の問題は、随意契約という調達方式が抱える課題も浮き彫りにした。
特定の企業に長期間にわたって仕事を任せる随意契約は、効率的な反面、競争原理が働きにくく、結果的に費用が高騰したり、特定の事業者が市場を独占したりするリスクがある。デジタル庁の公表でも、過去の会合で「調達に係る問題の大きなものの一つとして変更契約を挙げており、変更金額の幅が4割を超えないことや2回以上の変更は行わないことを原則とするルールを策定し、原則から外れるものは真に必要性があるか細かくチェックを行っている」と述べている。
今回のような問題が起きたことで、デジタル庁は今後、調達プロセスの透明性をさらに高め、より多くの事業者が参入できるような仕組みを構築していく必要がある。
デジタル化の推進と、公正な行政のあり方
今回の指名停止処分は、日本の行政におけるデジタル化の推進が、単なる技術的な課題だけでなく、契約遵守やコンプライアンスというガバナンスの問題と深く結びついていることを改めて示した。
アクセンチュアは、世界的な知見と技術力を持つプロフェッショナル集団である。しかし、いかに優れた企業であっても、契約というルールを守らなければ、行政のパートナーとして仕事をすることはできない。
今回の件を機に、デジタル庁は調達のあり方を再検討し、より公平で透明性の高いプロセスを確立していくことが求められる。そして、民間企業もまた、行政との取引においては、利益追求だけでなく、公共の利益を守るという高い倫理観を持つことが不可欠だ。日本のデジタル社会の未来は、行政と民間が互いに信頼し、ルールを守りながら健全な関係を築いていくことにかかっている。
参照:デジタル庁入札等監視委員会(第6回)(デジタル庁)