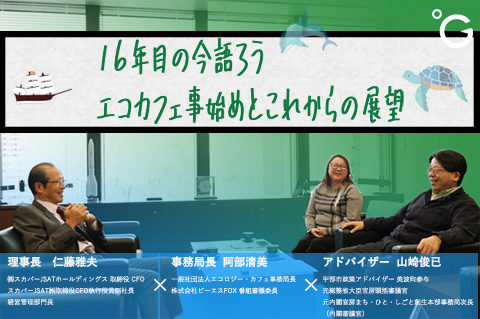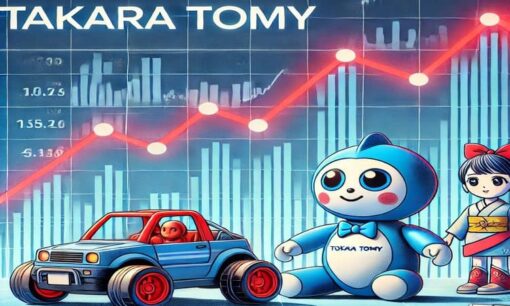島根県の小学校で、児童が授業の一環として収穫した米20キロを担任教諭が自宅に持ち帰り、消費していたことが明らかになった。県教育委員会は9月11日、この20代男性教諭を停職3か月の懲戒処分とし、本人は同日付で辞職した。
教育の信頼を揺るがす行為は、どのようにして起きたのか。
児童と地域が汗を流した稲作体験
昨年秋、松江教育事務所管内の小学校。5年生の児童たちは地域住民と共に田んぼに入り、黄金色の稲を刈り取った。笑顔と汗が入り混じる体験学習の一日。収穫された30キロの玄米は、地域の代表から学校へ寄贈され、児童にとって大切な学びの成果であり、地域と学校を結ぶ象徴でもあった。
その一部、約2キロは家庭科の授業でおにぎりにして味わった。しかし残りの米は児童に配布されることなく、家庭科室に置かれたまま年度末を迎えてしまう。
担任が抱え込んだ20キロの米
担任だった男性教諭は、配布を後回しにしたまま、やがて校内の精米機を使って残りの玄米を精米。そのうち約20キロを自宅に持ち帰り、日常の食卓で消費した。
「配らなければと思いながら年度末を過ぎた。報告すると怒られると思い、ごまかそうとした」
後に県教委の聞き取りで、教諭はそう語っている。
精米機と米ぬかが告げた“異変”
新学期が始まった4月。教諭は別の学校へ異動していた。そんな中、家庭科室に片付けられていない精米機や米ぬか、捨てられた米袋を同僚教員が発見。「残っているはずの米が見当たらない」と不審を抱いた。
さらに保護者から「親子活動で学校に残っている米を使いたい」と問い合わせが入り、事態は表面化。教諭は事実を認め、持ち帰った米の一部約2.4キロを返却し、児童や保護者に謝罪した。
厳しい処分と謝罪
県教育委員会は「児童や保護者の信頼を裏切り、教育行政への信頼を失墜させた」として停職3か月の処分を決定。教諭は「責任を取らなければならない」として辞職願を提出した。
学校企画課の和田正利管理監は「誠に遺憾。心よりお詫び申し上げる」と会見で陳謝。警察への告訴は行わないが、服務規律の徹底を全校に通知し、再発防止を図る方針を示した。
信頼回復の鍵は「現場の負担軽減」
今回の問題は、一教諭の過ちにとどまらず、教育現場の構造的課題を浮き彫りにした。かつては保護者会や地域の協力で分担していた収穫米の仕分けや配布作業も、共働き家庭の増加や地域活動の縮小で、教師が一手に担うケースが増えている。
叱責を恐れて相談できず、結果的に「隠す」という誤った選択をした背景には、失敗を許容しにくい職場環境と、若手教員に集中する業務負担がある。
県教委は服務規律を求めるだけでなく、教員が孤立せずに相談できる仕組みや、業務を分担できる体制の整備を進める必要がある。児童と地域の思いを守り、信頼を取り戻すためには、教育現場そのものの働き方を見直すことが欠かせないだろう。