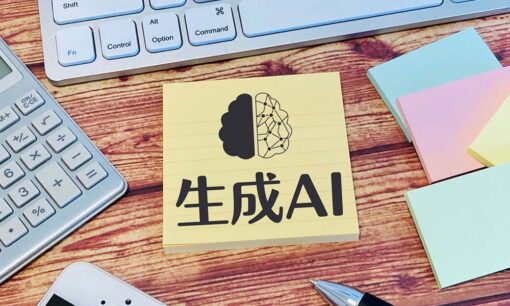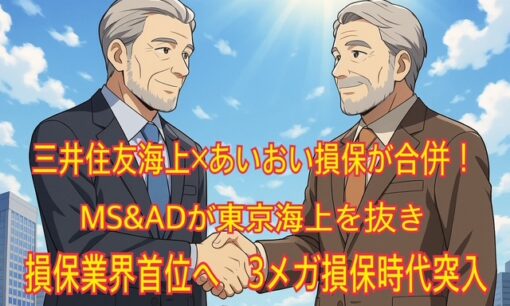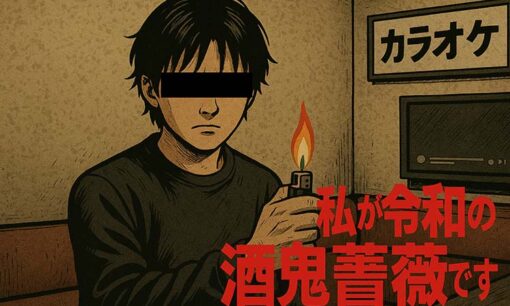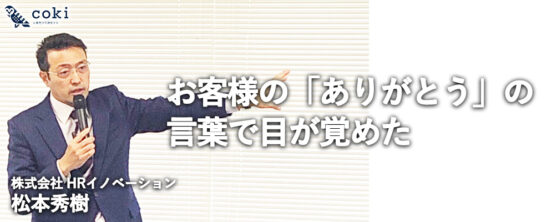寿司や弁当を購入すると当たり前のように添えられてきた「魚型の醤油容器」。日本発のこの小さな容器が、オーストラリアで姿を消そうとしている。南オーストラリア州が9月1日から施行した新たな規制により、魚型容器を含む小型プラスチック製調味料入れが禁止されたのだ。世界に広がった便利アイテムが、なぜ規制の対象となったのか。背景には深刻化するプラスチックごみ問題と、環境保護をめぐる国際的な流れがある。
魚型醤油容器、豪州で禁止に
BBCの報道によると、南オーストラリア州政府は2025年9月1日から、ふたや栓が付いた30ミリリットル以下の小型プラスチック製醤油容器の販売・配布を全面的に禁止した。対象には寿司や弁当に添えられる魚型容器が含まれており、これは世界で初めて同容器の使用を制限する措置とされる。
今回の措置は同州が推進する「使い捨てプラスチック禁止政策」の一環であり、既にレジ袋やストロー、綿棒などの禁止を進めてきた流れをさらに広げたものだ。副首相兼環境相のスーザン・クローズ氏は「魚型容器は数秒しか使われないが、廃棄されれば数十年から数百年にわたり環境に残る」と指摘している。
なぜ規制の対象に?
魚型醤油容器は再利用可能なポリエチレン製だが、その小ささゆえに機械によるリサイクルが困難で、多くが焼却や埋め立てに回される。さらに浜辺や道路に落ちやすく、排水口から海へ流れ込みやすい特性がある。
アデレード大学の海洋生態学者ニナ・ウトン氏は英メディアに対し、「魚型容器は海洋生物が餌と誤認して飲み込む危険があり、厚いプラスチック製のため分解には極めて長い時間がかかる」と警鐘を鳴らした。環境への負荷の大きさが、今回の禁止措置の根拠となった。
日本発祥のアイテムが世界で愛用
この容器のルーツは日本にある。1954年、大阪市住吉区の食品資材メーカー「旭創業」の創業者・渡辺輝夫氏が開発した。当時、調味料容器はガラスや陶器が主流だったが、「使い捨てなのに高価で危険」という問題意識から、安価で扱いやすいポリエチレン素材を用いた小型容器を考案。商品は「ランチャーム」の商標で販売され、日本全国に普及していった。
その後、寿司の持ち帰り需要が高まると「寿司といえば魚」との発想から魚型の容器が生まれ、赤いキャップと透明なボディの姿で定着した。魚の王様とされる鯛を模した形状は「めでたさ」や「親しみやすさ」も込められており、寿司文化の象徴的存在として日本国内のみならず世界へと広がっていった。
世界的に広がるプラスチック規制の流れ
今回の禁止措置は南オーストラリア州に限られるものだが、背景には世界的なプラスチック削減の流れがある。オーストラリア政府は、対策を取らなければ2040年までに海洋に流入するプラスチックごみが年間2,900万トンに達し、現在の3倍に膨れ上がると警告している。
また、世界のプラスチック廃棄物管理指数において、オーストラリアは25カ国中7位に位置するなど、比較的高い評価を受けている。今回の措置はその取り組みをさらに強化し、海洋汚染対策の先進例として注目される。
消費者に問われる“選択”
魚型醤油容器は、寿司や弁当文化を支えてきた一方で、環境負荷の象徴的存在ともなった。利便性を守るのか、それとも環境保護を優先するのか。この選択は行政や事業者だけでなく、日々容器を使う消費者にも突き付けられている。
小さな容器の禁止は、一見するとささいな規制に思えるかもしれない。しかし、その背景には海洋汚染や気候変動といった地球規模の課題が横たわっている。魚型容器が姿を消す出来事は、私たちに未来の海をどう守るかを考えさせるきっかけとなるだろう。