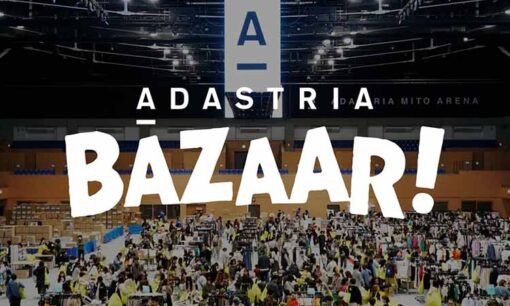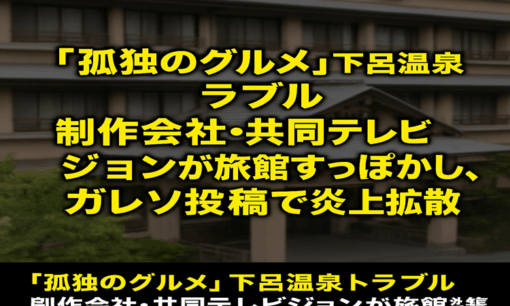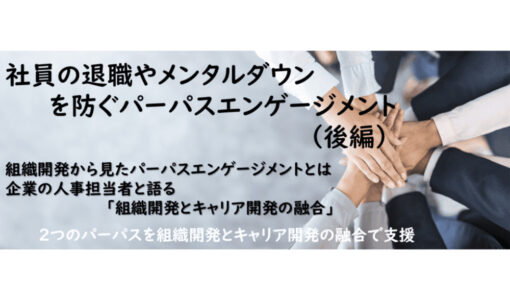望まぬ妊娠を防ぐ「緊急避妊薬(アフターピル)」の入手が、より身近になる見通しだ。厚生労働省は処方箋なしで薬局販売する際に年齢制限を設けず、親の同意も不要とする方針を固めた。性交後の限られた時間内に服用することで妊娠を防ぐ薬だが、これまでアクセスの難しさが課題とされてきた。制度変更の背景や仕組み、社会的な意義を追った。
厚労省が示した新方針
厚生労働省は2025年8月27日、自民党の部会で緊急避妊薬の薬局販売に関する方針を示し了承を得た。これによれば、処方箋を不要とする「市販薬」としての販売を進める一方で、年齢制限を設けず、親の同意も不要とする。さらに薬剤師の対面販売と「面前服用」を条件とすることが盛り込まれた。
市販化にあたり、薬機法改正で新設された「特定要指導医薬品」に位置づけられる予定である。この区分は安全性は認められているが、使用上の注意を理解してもらう必要がある医薬品を対象とするもので、オンライン販売は認められず薬局での対面販売が必須となる。
試験販売の経緯と成果
緊急避妊薬をめぐっては、2023年11月から全国約340の薬局で「16歳以上の女性」を対象に試験販売が始まっていた。性交後72時間以内に服用することで高い確率で妊娠を回避できるとされ、試験では薬剤師が利用者に説明を行い、面前での服用を求める仕組みがとられていた。
厚労省によると、試験販売を通じて大きな健康被害は確認されず、適正使用が担保されていたことから、市販化に向けた議論が加速した。市民団体からは「アクセスが改善される一方で、薬局での服用がプライバシーの負担になり得る」との指摘もあったが、日本産婦人科医会などは「望まぬ妊娠を避けるためには必要」との立場を示していた。
緊急避妊薬(アフターピル)とは
緊急避妊薬、いわゆる「アフターピル」は、避妊の失敗や性被害を受けた場合に性交後72時間以内に服用することで妊娠を防ぐ効果が期待できる薬である。代表的なのは「ノルレボ錠(一般名:レボノルゲストレル錠)」で、厚労省が承認する唯一の専用薬として用いられている。
妊娠阻止率は服用のタイミングによって異なり、24時間以内で95%、48時間以内で85%、72時間以内では58%程度とされる(日本産科婦人科学会の指針より)。ただし100%の効果を保証するものではなく、あくまで緊急時の対応である。副作用として一時的な吐き気や頭痛、倦怠感がみられることがあるが、多くは軽度で一過性とされる。
入手の現状と価格
現在、日本で緊急避妊薬を入手するには医師の診察と処方箋が必要である。自由診療であるため費用は医療機関によって異なるが、6,000円から2万円程度と幅がある。試験販売では薬局での価格は7,000〜9,000円前後とされてきた。今後市販化されれば、アクセスは大きく改善すると期待される一方で、価格の適正化や負担軽減も課題となる。
年齢制限を設けない理由
今回、厚労省が年齢制限や親の同意を不要とした背景には、若年層や性被害者の状況がある。性に関する悩みを保護者に相談できない若者や、性暴力を受けた場合に迅速に対応する必要があるためだ。
厚労省の有識者会議では「年齢制限を設けると必要な人が適切に薬を得られない」との意見が相次ぎ、試験販売での16歳以上という条件も見直されることとなった。
社会的背景と国際比較
日本では避妊に関する議論が長く続いてきた。世界保健機関(WHO)は緊急避妊薬を「安全で有効な方法」と位置づけており、欧米諸国では既に市販化されている国が多い。米国では17歳以上から処方箋不要となり、その後さらに年齢制限を撤廃した経緯がある。
一方、日本では医師の関与が必要とされる期間が長く続き、アクセスの困難さが課題となっていた。市販化は望まぬ妊娠を防ぐための社会的な一歩とされる一方で、性感染症対策や性教育の充実とあわせて議論すべきとの声もある。
利用者への注意点
緊急避妊薬はあくまで「緊急時に限る対応」であり、日常的な避妊手段としては適さない。服用後に避妊効果が持続するわけではないため、避妊の失敗を繰り返さないよう低用量ピルやコンドームなど確実な方法を併用することが望ましい。
また性感染症の予防効果はなく、コンドーム破損などの場合には性感染症の検査も必要となる。薬剤師や医師の説明を正しく理解し、適切に使用することが重要である。
今後の展望
緊急避妊薬の市販化は、女性の健康と権利に関わる重要な政策転換である。安全性や適正使用を確保するためのルールを維持しながら、社会的に必要とする人が確実にアクセスできる仕組みを整えることが求められる。
厚労省は今後、専門部会での審議を経て最終決定を行う。市販化が実現すれば、日本におけるリプロダクティブ・ヘルスのアクセス改善に向けた大きな一歩となるだろう。