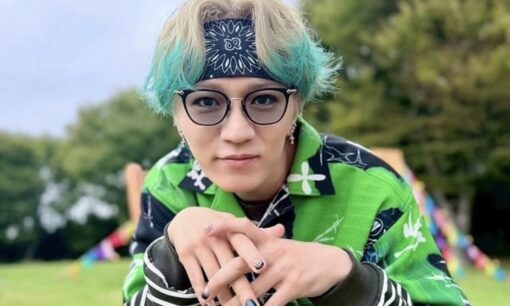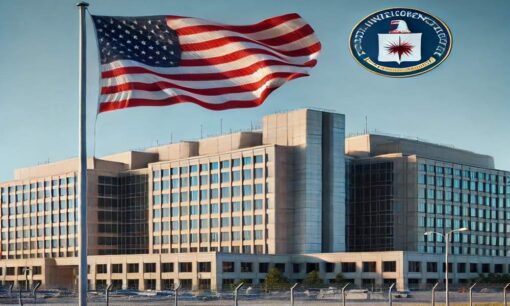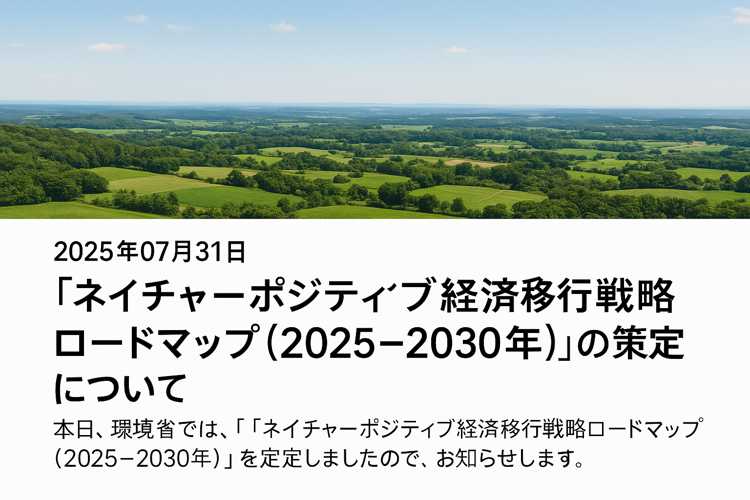
環境省は7月31日、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」を公表した。2050年に向けて「自然と共生する社会」の実現を目指す中期戦略として、2024年3月に策定された「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を具体化する位置づけとなる。
本ロードマップでは、企業、金融機関、投資家、消費者、自治体など、多様なステークホルダーが連携し、自然資本を基盤とした経済構造へと移行するための道筋が示された。
2030年に向けたネイチャーポジティブ経済の「絵姿」
ネイチャーポジティブ(Nature Positive)とは、生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せることを目指す概念であり、日本政府は2030年までにその達成を掲げる「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定している。今回のロードマップは、その中でも「ネイチャーポジティブ経済の実現」を担う柱としての役割を担う。
環境省が描く2030年の理想像では、企業が自然資本を起点とした経営に移行し、ESGやTNFDを通じた情報開示が進み、その取組が投資家や地域社会から高く評価されることで、企業価値と地域価値がともに向上する好循環の創出が期待されている。たとえば、自然共生サイトを活用した地域の活性化や、生物多様性に配慮した調達・資金循環の促進がその柱となる。
自然と経済の好循環を支える三つの視点
今回のロードマップでは、国が主導する施策と、ステークホルダーに求められるアクションが三つの視点に分けて整理されている。第一の視点は、地域の自然資本を活用した経済と自然の両立である。企業が森林や湿地、里地里山といった地域資源とのつながりを認識し、事業活動と生態系保全が調和するランドスケープアプローチの導入が奨励されている。栃木県那須野が原をモデルとした事例創出や、自然共生サイトの活用による観光振興などが想定されている。
第二の視点では、自然資本に関するデータ整備や情報開示を通じて、ネイチャーファイナンスの拡大と高付加価値経済への転換を促す。既に三菱UFJ銀行や三井住友信託銀行、MS&ADなどが自然資本を評価対象とした金融商品を展開しており、今後は投融資における「NP配慮指針」の策定とともに、金融業界によるルール形成への参加も期待される。また、TNFDやISSBといった国際的枠組みとの連携も視野に、自然関連のデータプラットフォーム整備や、生物多様性価値の定量評価手法の開発が進められる見込みだ。
第三の視点では、日本企業の国際的競争力を高めるために、自然領域におけるルールメイキングへの参画と主導が不可欠であるとした。とりわけアジアモンスーン地域における自然資本の特性を踏まえた技術・制度の国際標準化を推進し、地球観測衛星や環境DNA、水リスク評価といった分野において、産官学連携による「攻めの戦略」と「守りの戦略」の双方を構築する。政府はこの分野において「見えない市場への投資」が不足していると指摘し、大学発ベンチャーや企業による技術の海外展開と標準化を後押しする構えだ。
ステークホルダーに求められるアクション
消費者に向けた施策としては、自然配慮型商品への選好行動を促す仕掛けも盛り込まれた。小売店でのポップ掲示などによる価値訴求により、認証商品の売上が増加するなどの効果も報告されており、今後はこれらの事例を全国へ横展開する方針だ。商品・サービスの裏にある企業の自然配慮の取組を、消費者が適切に理解し、購買行動に反映できるような環境整備が求められる。
さらに、持続可能な調達を実現するための取り組みも重要な要素として位置づけられている。たとえば、ASEAN諸国との連携を見据えた自然関連リスク評価、認証製品の選定、デュー・ディリジェンスの標準化などが、日本企業のサプライチェーン全体に求められている。環境省は、グリーン購入法へのNP配慮基準の反映も検討しており、公共調達を通じた波及効果にも期待が集まる。
政策実施スケジュール
政府は2025年度から2030年度にかけて、段階的に施策を実装していく。支援証明書制度や自然共生サイトの普及、企業のNP経営支援、プラットフォームによるマッチングの強化、国際会議での日本の技術打ち込みなど、多層的な戦略が進行する予定である。環境省は「自然を守ることがコストではなく、経済的成長の源泉となる社会を目指す」と強調しており、2030年を一つの転換点として、日本発のネイチャーポジティブ経済モデルの確立を視野に入れる。