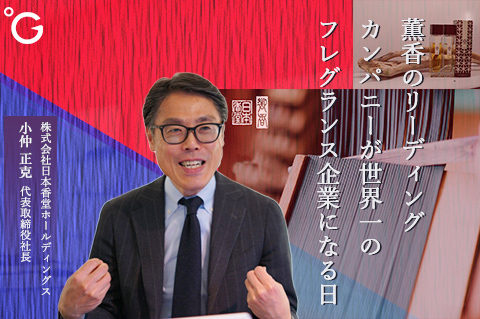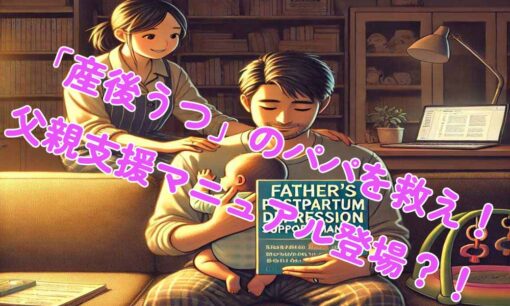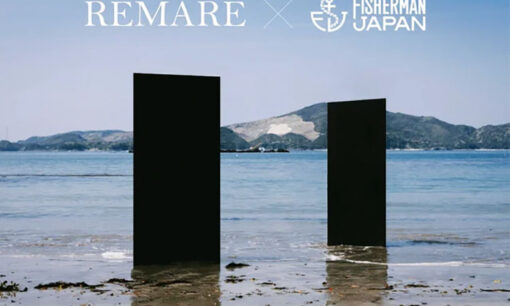東京博善株式会社は、2026年3月31日をもって東京都23区との協定に基づく「区民葬儀」制度からの離脱を表明した。長年にわたって低所得者の葬送を支えてきた制度からの突然の撤退は、都民生活への影響が大きく、制度設計の根幹を揺るがすものとして波紋を広げている。
火葬という公共性の極めて高いインフラが、営利目的により左右されてよいのか。今、問われているのは、制度からの「離脱」ではなく、公共と民間の境界そのものだ。
火葬料金引き下げの裏で進む制度の崩壊
東京博善は、8月1日に火葬料金の一部引き下げも発表している。大人1体あたりの火葬料は90,000円から87,000円、小人は51,000円から50,000円に下げられる。これは一見すると利用者に寄り添う姿勢に見えるが、「実態は異なる」と指摘する声が多い。
この引き下げは、あくまで「協定外料金」としての改定であり、区民葬としての協定料金体系そのものからの離脱を意味している。すなわち、行政と葬儀業者、火葬場運営企業、霊柩業者が連携し、一定の価格で葬儀を提供してきた公益制度の土台が、今、音を立てて崩れつつある。
佐藤信顕氏が警鐘「行政も都民も舐められた」
この問題に対し、「葬儀葬式ch」を運営する日本一の葬祭系YouTuber、佐藤信顕氏は厳しく批判している。氏は「利益に走らぬようにとの厚労省通達に違反している。行政も都民も舐められた結果だ」と指摘。さらに、「行政の発表よりも先に、民間企業が勝手に制度の方向性を公表することは常識では考えられない」と、行政の統制力のなさを痛烈に批判した。
また、「東京博善は年商130億円に対して営業利益50億円という、利益率約40%のバケモノ企業。資産も潤沢で、流動資産140億、固定資産250億円もあり、金銭的な理由での離脱はあり得ない」として、今回の判断が“営利目的”以外に説明できないと断じた。
決算資料が示す“離脱の論理” 高収益化と脱・公共のシナリオ
佐藤氏の主張を裏付けるかのように、東京博善の親会社・広済堂ホールディングスの直近、2025年3月期決算資料を見ると、同社の営業利益は前年比+55.9%増の83億円を計上。そのうち、「葬祭公益」(火葬事業)および「葬祭収益」(式場・葬儀)セグメントが大半を占めている。
とりわけ、東京博善の中核をなす「葬祭公益」セグメントでは売上高59億8,600万円、営業利益12億4,900万円を計上しており、利益率は実に20%を超える。これは「公共インフラ」としては異例の高収益体質である。また、火葬件数は年間72,000件にのぼり、2028年には78,000件を目指す拡大戦略が明記されている。
一方、もう一つの柱である「葬祭収益」セグメントも見逃せない。こちらは自社式場での葬儀施行や関連サービスを提供するもので、2025年3月期の売上高は104億4,200万円、営業利益は42億8,800万円に達している。利益率は実に41%を超え、民間ビジネスとして極めて優良な収益源となっていることがわかる。式場稼働率の改善や価格改定、TVCMによる集客強化が奏功し、特に「東京博善のお葬式」ブランドを軸に、都内および近郊への認知拡大が進んでいる。
こうした安定収益を背景に、東京博善は今後、既存施設内に新たな式場(桐ヶ谷・四ツ木)を増設予定であることも決算資料で明記されている。制度に依存せず、独自ブランドによる収益最大化を図る構造が、すでに出来上がっているのである。
ESG報告書でも、東京博善は23区内の火葬需要の約70%を担う“基幹インフラ”であり、「火葬の社会的責任」を強調しながらも、行政とは一線を画した独立性と事業判断を貫く姿勢がにじんでいる。すなわち、「区民価格」という公共の論理から解放されることが、もはや戦略的選択肢として制度内に組み込まれているのだ。
東京博善を巡る企業買収の攻防と“公共の死角”
東京博善は1887(明治20)年創業。長らく寺院や僧侶が株を保有していた時代もあり、公益性の象徴ともいえる存在であった。そんな歴史ある企業の構造は、1980年代に大きく変わる。田中角栄元首相と親交があり、「政商」「大物フィクサー」とも呼ばれた櫻井義晃氏(故人)が株式を取得し、自ら創業した印刷会社「廣済堂」(旧・東証1部上場)に子会社化させた。
しかし2000年代以降、廣済堂本体が印刷業の不振で業績悪化に陥る一方、東京博善は火葬場新設が困難という“独占インフラ”として安定的に利益を上げ続けてきた。
2022年以降、その東京博善を巡って激しいM&Aの攻防戦が勃発する。最初に動いたのは廣済堂経営陣で、外資系ファンドと組んだMBO(経営陣による買収)を発表。TOB(株式公開買付け)価格は1株610円とされたが、これに対し、創業家や古参幹部が反発。さらに、村上世彰氏と関係の深い投資ファンドが市場で株を買い進め、TOB対抗価格750円を掲げて買収合戦が激化した。
ところがこの買収合戦は両陣営ともTOB不成立に終わる。株価は一時1000円を突破し、その後、2023年に入ると麻生太郎元財務相の一族が率いる麻生グループが大量に株式を取得。最終的に19%超を保有し、投資額は43億円に達した。一部では、村上ファンドが保有していた約13%分の株式を、950円の高値で麻生側に売却し、7〜8億円の利益を得たとも言われている。
さらに、中国系投資家グループの参戦も報じられた。ラオックス買収で知られる中国出身の羅怡文(ルオ・イーウェン)氏に連なる勢力が20億円以上を投じて廣済堂株を取得したとされ、「東京博善の利権」が日中の投資勢力を引き寄せる存在となっていることが明らかとなった。
この買収劇の背景には、「火葬場は新設できない=競合不在」「高齢化で市場拡大」「公共補助制度に依存しない現金商売」という極めて高い利益率と安定性がある。にもかかわらず、現状ではこの“公共的インフラ”が完全に資本市場の論理の中で売買され、誰が所有し運営するかがブラックボックス化している。
事実、東京博善の協定離脱も、こうした企業支配構造の変化と無関係ではない。政治的影響力を持つ麻生グループ、海外資本、短期的リターンを追求するアクティビストなど、さまざまな思惑が交差する中で、日本人の生活基盤が投機対象として「死角」へと追いやられているのではないだろうか。
火葬インフラの民営独占と構造的問題
東京23区にある9か所の火葬場のうち、実に7か所は民間企業によって運営されており、そのうち6か所を東京博善が一手に担っている。このような構造は、全国的にも稀であり、事実上の寡占状態にある。ちなみに、火葬場は全国で約1500カ所あるが、95%は各地の地方公共団体等が運営する非営利事業となっている。
火葬場の開設には「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく厳しい規制が課されており、特に都市部では新設がほぼ不可能に近い。つまり、一度既得権を得た企業が、長期にわたって独占的に市場を支配できる構造が温存されているのだ。
こうした背景のもと、東京博善は「競争相手のいない」立場を最大限に活かし、今回の離脱を決断した。公益的な役割を担っていた区民葬から離れる一方で、今後は火葬料金を“自由価格”で設定することが可能となり、実質的に価格支配権を握ることになる。これは、都市インフラの一部を民間が私的に収益化する構図そのものである。
厚労省通達と「公共性」の崩壊
厚生労働省はこれまで、火葬場や葬儀制度について、「地域住民の生活に不可欠な公共性を有する施設」として、その非営利性や公平性を強く求めてきた。実際、2007年に通知された「墓地、火葬場の設置及び管理に関する指導指針」では、「営利を目的とすることなく、地域住民に広く開かれた施設運営」が原則とされている。
しかし今回の東京博善の行動は、この原則と真っ向から矛盾する。価格協定を一方的に破棄し、区民への説明責任も果たさないまま撤退を決定した姿勢は、厚労省通達を事実上無視するものと言える。これを許せば、他の火葬場や葬儀事業者にも同様の行動を誘発しかねず、制度全体の崩壊へとつながりかねない。
23区は「助成制度」で対応へ、しかし…
今回の混乱を受け、特別区長会は8月1日に、2026年度から、火葬場を利用する区民に対し新たな助成制度を設けると発表した。これにより、一部の経済的負担軽減は図られるが、制度の詳細は予算編成次第であり、利用者への周知や運用の信頼性には懸念が残る。
佐藤氏は「これを許しちゃうのが政治ですかね、行政ですかね」と吐き捨てるように語る。もはや一民間企業の判断に行政が振り回されている現状は、火葬行政における統治能力の欠如そのものである。
公共性をどう取り戻すか「火葬の再公共化」は可能か
今回の事態が突きつけたのは、火葬インフラの“公共としての再設計”の必要性である。災害対応の観点からも、公営火葬場の整備や自治体主導の価格統制の導入など、包括的な対応が急務だ。
一方で、東京博善が既得権と利益構造を手放す可能性は極めて低い。であるならば、都や23区が新たな公営火葬施設を整備するか、あるいは強制力をもった価格指導を制度化するしか、公共性を回復する道は残されていない。
「公共の火」が民の手で弱火にされる日を、見過ごしてはならない。