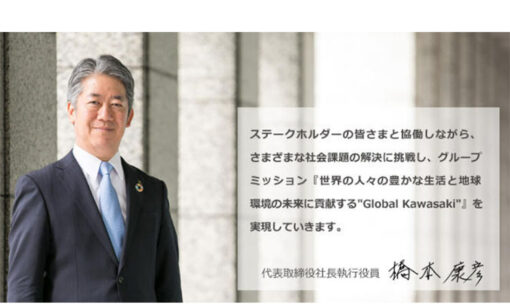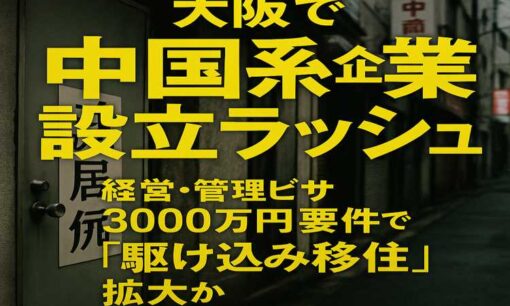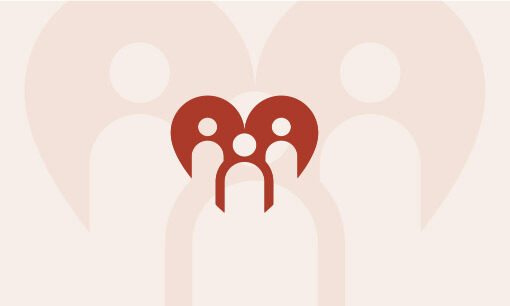北京の裁判所がスパイ活動と認定、罪を認めた日本人社員に懲役3年6か月の判決

中国・北京市の第2中級人民法院は2025年7月16日、アステラス製薬に所属する60代の日本人男性社員に対し、スパイ活動を行ったとして反スパイ法違反で懲役3年6か月の実刑判決を言い渡した。この判決により、長らく不透明だった事件の一端が明るみに出たが、その詳細はいまだ霧の中にある。
20日、日本テレビなどの報道によると、被告である日本人社員は裁判で罪を認めたという。判決文では、「日本の情報機関の依頼を受け、中国国内の情報を収集し、報酬を受け取っていた」とされ、それが「スパイ活動」に該当すると判断されたとされる。
ただし、具体的にどのような情報を提供したのかは判決でも明かされておらず、「国家の安全に関わる問題」として非公開のまま処理された。実質的に何が「国家秘密」に該当するかの基準が不明確な中国の反スパイ法の下では、詳細な事実が国際社会の目に晒されることはない。
これに対し、日本政府は金杉憲治・駐中国大使が判決直後に領事面会を行い、「人道的対応」を引き続き求めていく方針を示した。一方、本人は「弁護士と相談する」と述べつつも、現時点では上訴しない意向を示しているという。今後、判決が確定すれば、未決勾留分が刑期から差し引かれ、約1年半の服役期間を経ての釈放が見込まれる。
罪を認めれば減刑 “認罪認罰”がもたらした判決の軽さとその裏側
注目すべきは、過去に反スパイ法違反で有罪判決を受けた日本人の多くが10年前後の長期刑を科されてきた中で、今回の3年6か月という量刑が“異例の軽さ”である点だ。
背景には、中国特有の司法制度である「認罪認罰制度」がある。これは、被告が罪を認めることで審理が迅速化され、刑罰が軽減される仕組みだ。今回も被告が罪を認めたことが、刑期短縮につながったと見られている。
ただし、この「罪の自白」が自発的なものか、あるいは早期の釈放や軽減を目指した弁護戦略によるものかは、外部から判断するのは困難だ。日中関係筋は「心から罪を認めたのか、あるいは司法制度に順応するための戦術的判断かは見極めがつかない」と話す。
さらに見逃せないのは、中国当局が判決の根拠として「日本の情報機関の関与」を明示した点である。中国は過去にも、反スパイ法違反で拘束した日本人について、「公安調査庁などとの関わり」を問題視してきた経緯がある。こうした言及は、中国当局が日本政府の情報収集活動に警戒感を強めていることを示唆している。
北京での“スパイ認定”に広がる動揺、日本人ビジネス関係者にとっての「予測不能な地雷」
拘束されたアステラス製薬社員は、長年にわたり中国ビジネスの第一線に立ってきた人物だった。北京や香港での駐在経験が豊富で、中国市場に関する知見を深めていたほか、日系企業による業界団体「中国日本商会」の副会長やライフサイエンスグループのリーダーも務めていた。
まさに帰国直前のタイミングで拘束されたという経緯も、現地の日本人社会に強い衝撃を与えている。ある駐在員は「追い出すならまだしも、帰国させずに拘束するのは恐怖以外の何物でもない」と語る。
中国の反スパイ法は2014年の制定以来、その適用対象が広がり続けている。2023年には改正が行われ、ネットワークインフラや経済情報にまで“国家機密”の適用範囲が拡張された。外資企業や研究者、駐在員にとっては、「何が地雷になるのか分からない」状況が続いている。
外交筋によれば、「裁判はすべて非公開で行われ、どのような証拠に基づいて有罪とされたのかも把握できない。後出しで『これは国家秘密だった』とされることが最大の問題」だという。
伊藤忠、北大教授の事例と比較 外交交渉が実を結ばなかった理由とは
過去にも同様の拘束事例は複数存在する。2018年には、伊藤忠商事の中堅社員が中国・広州で家族旅行中に国家安全局に拘束され、懲役3年の実刑判決を受けた。2020年に刑期を満了して帰国しているが、日本の本社社員であったこと、拘束から報道まで1年かかったことなどから、当時も企業関係者に大きな警戒感が走った。
さらに2019年9月には、北海道大学法学研究科の岩谷將教授が中国社会科学院の招待を受けて訪中した際、「国家秘密に関わる資料を入手した」として拘束されたが、日本の世論と政府の迅速な外交対応が功を奏し、わずか1か月ほどで釈放された。
今回のアステラス社員に関しては、拘束からすでに2年半が経過している。外交カードとしての利用ではなく、中国側が国家安全問題として内部的に処理した可能性が高く、「外交ルートの限界」を象徴する事例となった。
中国の“対外開放”と裏腹の拘束連発 ビジネスと安全保障の矛盾
中国は現在、経済成長の鈍化と外資離れに直面しており、政府首脳は対外開放を強調する場面が目立つ。2023年3月に開催された「中国発展ハイレベルフォーラム」では、習近平国家主席が「制度的開放を着実に拡大していく」と演説し、各国の投資家に呼びかけた。
しかしその一方で、外国企業に勤務する社員や研究者が、反スパイ法など国家安全関連法で次々と拘束されている実態は、中国市場の不確実性を如実に示している。
たとえば、アメリカの信用調査会社「ミンツ・グループ」の北京事務所が中国当局によって家宅捜索され、中国籍の社員5人が拘束された事例も記憶に新しい。これらの動きは「外国企業への恣意的介入」と見られており、すでに欧米系企業を中心に中国ビジネスからの“撤退ドミノ”が始まりつつある。
日本企業は“沈黙外交”から脱却できるか 現地社員保護の再設計が急務
今回のアステラス事件は、単なる一企業の不幸ではなく、日本の産業界全体に突き付けられた“安全保障上の警告”と捉えるべきだろう。現地での情報活動はもちろん、通常の企業活動ですらいつ国家安全に抵触するか分からない状況下では、「従来型のビジネスリスクマネジメント」はもはや通用しない。
これまでの日本企業の対応は、水面下の交渉や外務省ルートによる“静かな対応”が主流だった。しかし、中国が反スパイ法を外交カードとしてではなく、国内統治の一環として運用し始めている今、「静かに解決」はむしろ事態を長期化させるリスクすらある。
日本の経済界が団結して、邦人保護と法制度の透明性について中国に対して発信する時機が訪れている。「ビジネスと安全保障の分離」は幻想にすぎない。中国との経済関係を維持するのであれば、その前提となる“信頼の再構築”が不可欠である。