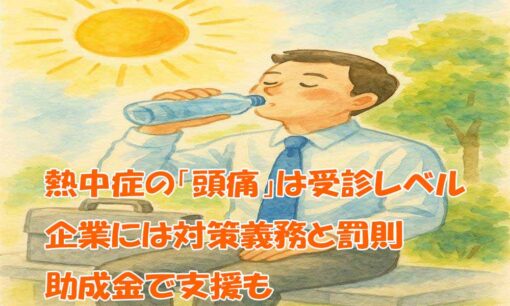戦後まもない伊豆・修善寺で、家族を支えるために立ち上げた小さな金属加工業。有限会社伊藤金属総業は、祖父の挑戦から始まり、父へ、そして今、三代目・伊藤徹郎氏の手で「蝶番製造」という独自の道を切り拓いている。
地味ながら生活に欠かせない蝶番に情熱を注ぎ、家族と地元の縁を力に変えながら歩んできた軌跡。そして、時代の波に挑みながら、次の世代へと受け継がれていくものづくりのバトン。伊豆の山あいに息づく、ひたむきな「幸場」の物語を追う。
祖父が興した「蝶番製造」
伊豆箱根鉄道修善寺駅を降りてなだらかな坂道を登っていくと、ほどなく山の中腹の開けた土地に有限会社伊藤金属総業の社屋が見えてくる。
「会社の裏山には北条早雲が伊豆支配の拠点として使った城跡もあるんですよ」と話してくれたのは同社代表の伊藤徹郎氏。祖父の起こした同社の代表に就任して今年(2025年)で5年になる。

伊藤金属総業の創業は終戦直後の1945年。
「私の祖父恒三郎は戦前、東京の金物屋で働いていたんですが、激しくなってきた戦争から疎開するために伊豆に一家で移り住んだんです。なぜ伊豆だったかというと祖母の父、私からみたら曽祖父に当たる人が伊豆の出身だったから。伊豆から東京に働きに出る人が当時は多かったようですね」
戦争が終わっても一家が東京に戻ることはなかった。焼野原となった東京には仕事もなく、住んでいた家ももう失われていたからだ。恒三郎は妻と子供たちを抱え、伊豆の地で食べていく方法を考えねばならなかった。
「そこに東京で働いていた時に縁があった方が連絡してきたんです。戦争が終わって事業拡大をしたい、うちで販売する部品を作ってくれないかと。それで金属加工業を始めたのが創業のきっかけですね」
当時は頼まれるままに様々な部品を製造していた同社だったが、次第に蝶番が主な製品になっていく。
「昔は必死だったから、仕事になればなんでも挑戦して作っていたよ、とは祖父のあとを継いだ父も言っていました。トランクなどの留め具として使われるパチン錠や、打ち抜き鎖、ホールケーキの底を固定する爪なんかも注文が来たら作っていたそうです。それがだんだんと『この部品ならあそこに頼む』と住み分けされるようになってきて、弊社は蝶番の注文が多くなってきた。今では99%が蝶番ですね」
金属・木製・プラスチック製品など凡そありとあらゆる製品の可動部に蝶番は使われている。私たちが日常生活を送っているすぐ近くにも様々な蝶番があり、生活を支えている。家のドアだけでなく家具や電化製品にも使われているし、それは屋外でも同じだ。伊藤代表も、町を歩いているときにふと見かけた信号機の裏に自社で作った蝶番を見つけたこともあるという。地味ながら重要な部品、それが蝶番だ。
伊藤代表は言う。
「弊社の事業内容は、一般的にはプレス加工業の区分になるでしょう。伊豆地方を含む静岡県を見渡せばプレス加工業者はたくさんありますが、それは自動車や電機などの大手製造業が県内に工場を有していて、その下請けで部品を製造するプレス加工業者が多いからです。しかし私たちが作っているのはプレス加工『部品』ではなくて蝶番という『製品』です。プレス加工はあくまで蝶番を作るための手段にすぎない」
「だから蝶番だけを作るとは言っていないし、頼まれればなんでも作る気概はありますけど、今は堂々と『蝶番製造業』と名乗っていいのかなと思っています」と伊藤代表は微笑んだ。
「図面通りに作ればいいものではない」
「蝶番も工業製品ですから、図面と金型さえあれば同じカタチのものを作ることはできます。しかしだからといって誰にでも作れるものではありません」。伊藤代表はそう自信を示す。
「どうしてもお客様は少しでも安く作る業者に頼もうとします。図面さえ与えてくれれば、どこのプレス加工業者でも図面通りの製品は作れるでしょう。けれど実際に使ってみると思うように動いてくれないことも多々ある。他所の製品のそういう不具合が解消できずに、結局私のところに相談が来ることもあるのですが『私たちのやり方で作っていれば問題なかったのに』と思うこともありますね。
例えば蝶番には軸が入っていますが、これが抜けることはあってはいけません。私たちは長く蝶番を作っていますから抜けない方法を知っているのですが、それを分かっていない業者が別の方法で軸を抜けないようにするとやはり動作に不具合が出る。私たちが長年培ってきたノウハウがそこにはあるわけです」

しかし、と伊藤代表は続ける。
「それが蝶番を自社の製品に使っている製造業者に伝わりにくいのが大きな悩みです。全く蝶番を知らない業者が図面を描いて『これならどこのプレス加工業者でもできるな』と思って下請けに発注しても、蝶番の作り方を知らないので、結果組み立ててから上手く作動しない、なんてことも聞きます。だから私たちが今やるべきことは、ノウハウを持っている私たちの存在をもっとたくさんの人に伝えて、『蝶番を作っている工場がある』ことを知ってもらうことが必要だと思っています」
自動車は小さなネジ1本まで数えると1台で3万点もの部品から成り立っているという(トヨタ自動車HPより)。自動車に限らずあらゆる製品は、その数は違えど大小様々な部品から構成されており、一つ一つに工夫が込められている。それを知らない門外漢が「こんなものか」と高をくくって作ると最後に大きなしっぺ返しを受ける。伊藤代表の言葉からはそんな教訓が感じられた。
修善寺の「縁」で営んできた
「なぜ今も修善寺でやっているのですか?」と尋ねると、伊藤代表は笑った。
「確かに商談などで東京に出ていかなければならない場面では不利かなと思うことはありますが、どこでやっても結局生み出す製品は同じ品質ですから。……ただ私としては修善寺だから続けられた、という思いもあります」
実は創業者恒三郎氏は当初、もう少し山間に入った疎開先で土地を間借りして作業場を開いていたのだが、創業から14年ほど経ったころ、もっと広く使いやすい土地を提供してくれる人が現れたので現在の場所に移ってきたのだという。
「そういった人の縁があってここで仕事をしてこられた。それに弊社で働いてくれる人も近所の方々がほとんどです。私たちのことを知っている人から紹介されて入社してきてくれます。だから今まで人手不足、人が見つからないで困るとか無く続けられているんです」

また家族が多く働いてくれているのも大きな特徴だと伊藤代表は話す。
恒三郎氏には伊藤代表の父である長男達夫氏を含めて四男一女の子供がいたが、次男は金型業、三男はダイキャスト工場で、四男はメッキ表面処理でそれぞれ修業してから修善寺に戻り、家業を手伝ってくれたのだという。
「恒三郎が意図的に兄弟を各業種で修業させたかどうかは分かりませんが、それぞれ種類が違う仕事を覚えて戻ってきたのは、やはり『金属総業』の名にふさわしく、何でもやろうという想いがあったのだと思います。
現在も二人の叔父が70歳を過ぎても働いてくれていますし、工場長は従兄弟で他には私の妹夫婦も。社員の中にも私の中学校の先輩が地元で働きたいと来てくれましたし、その方の娘さんもここで働いてくれています。従業員の半分くらいがそういう身内の繋がりですね」
近年では珍しいアットホームな社員構成だが、だからこそ気をつけなければならないこともあると伊藤代表は話す。
「家族だからとナァナァになってはならないし、甘えが出てはいけないと思っています。他の従業員からは経営者一族『伊藤家』として見られているわけですから、私たちが率先してちゃんとしていかなければいけない。だからより気を引き締めていくように心がけています。以前は『家業』としての感覚が強かったのですが、これだけ従業員が多くなると『企業』として考えていかなければと常々感じています」。
経営者になって見えてきた「家業」の姿
祖父・父と受け継がれ、そして親族も多く働く伊藤金属総業を、徹郎氏が継ぐことは自然の成り行きだった。
「家を継ぐのは自分にとって抵抗は有りませんでしたね。工業高校の機械科へ入学しましたが父からは「自分のやりたいことをやっていいんだぞ」と言われていましたので、PCが一般に普及し始めた時期でも有り興味の有った情報処理を学ぶために東京の専門学校へ進学しました。
卒業後は地元に戻りたかったのですが就職先が見つからず悩んでいた時に、創業からお世話になっている取引先から勉強にきませんか?と声をかけられ、いずれ家業を継ぐのだからそれもありかなとその取引先で6年間修業して。その間に妻と知り合いましたが、出会った時から家業を継ぐことは既定路線でしたから、妻もそのつもりで嫁いできて来てくれた」
「入社してから父に言われたことはまず『お前も作ることを覚えろ』。父も会社を継いだ時にお客様から『とにかく真面目にやっていれば仕事はいくらでもあるから』と言われてやっていたそうなので、まずは経営者というより、ものづくりのイロハから叩き込まれました」
だから営業に関しては教えてもらうことも少なかったのだが、徹郎氏が代表に就任したころには情勢が大きく変化していた。
「代表になった2020年は新型コロナの最中でした。世界が大きく移り変わる中で会社の状況を見つめ直していくうちに、これまでなら何とかやってきた経営が、実はいつ崩れてもおかしくないことに気づかされた。経営者になってみると風景が全く変わって見えるものですね。それで自分から動いて変えていかなければと思い立ったのです」
下請けとして注文に応えるだけでなく、こちらからも発信していかなければならない。自分に今、何ができるのかを考え続ける毎日だった。
「経営者として数字を管理しなければならないし、昔のままのやりかただと今にそぐわない点もあるから改善もしなければならない。製造していくための設備投資ももちろん必要になりますが、新型プレス機を導入したからといって作業が2倍速くなるわけでもないので、それも計画的に進めていかないと継続的な経営は難しい」

「大事なのはお客様のニーズにマッチしているかどうかです。弊社が設備に力を入れて100万個生産できるようになったとしても、お客様が10個だけしかいらないと言われたらどんなに単価が安かろうとマッチしない。世の中が求めている蝶番へのニーズに対して、私たちの都合でこれまでのやり方を大幅に変えてしまうと、せっかく培ってきた良さが失われる可能性もあるのです。
ロボットを導入する、もっとオートメーション化するなど目先の利益を求める方法はいくらでもあります。しかしそれでお客様の求める製品を生み出せなくなっては元も子もない」
だから工程や考え方からまず変えていくことで生産性を見直し、お客様のニーズに合わせる方法を模索しているんです、と伊藤代表は話す。
やりたいのは「アイデアを実現するお手伝い」
そんな伊藤代表が取り組んでいるのが蝶番のグッズ化だ。
「最初は私が携帯ストラップに小さな蝶番をぶら下げていたのを見つけた知人が、ぜひそれをグッズ化しようと閃いたのがきっかけでした。今では妻が積極的にグッズのアイデアを出してくれています。本人は妄想よ、と言って笑っていますが」
蝶番をデザインに用いたグッズはその後クリアファイルやシール、Tシャツにまで展開している。これらは修善寺のお土産店や各地の展示会で販売され好評を博している。中でもトートバッグは地元伊豆総合高校で授業をした時、高校生の意見から生まれた一品だ。

「先ほどお話しましたが、とにかく我々の存在を知ってもらうこと。その方法の一つとしてグッズ展開をしています。私たちは蝶番を部品に使って製品を作るユーザーさんと直接取引できなくてもいいんです。ただユーザーさんと私たちとの間に立つ商社さんやメーカーさんが、私たちの持つノウハウを伝えられるようにしなければならない。
そうしないと彼らの先にいるユーザーさんに私たちの名前が届かないからです。だから存在を知ってもらう努力を私たちからしていかなければならない」
グッズのアイデアを「妄想」するのは伊藤代表の奥様だが、それをカタチにしていくのは代表の仕事だ。
「だからやっぱり下請けなんです(笑)。けれど結局、私は人がこういうことをやりたい、こういうモノを作りたいというアイデアをカタチにしていくことが好きなんです。弊社製品も決して独創性がある製品ではないかもしれない。けれどお客様の『こういう蝶番が欲しい』という想いを実現するお手伝いができる。それが私たちの本当の強みなのかもしれません」。
受け継がれるものづくりのバトン
三代続く伊藤金属総業だが、次世代の息吹がすぐそこに芽生えている。
「会社をもっと大きくしていきたい」とその想いを語るのは現在同社専務を務める伊藤代表の子息大稀氏。
代表は息子である大稀氏についてこう語る。
「高校野球部の卒部式で、他の子たちが親に感謝を伝えている中で、息子だけが『家を継ぎます』と宣言してくれた。驚きましたね」
その後東京の大学へ進学した大稀氏は親に何も言わず、父が過去に修業した取引先に入社希望を出していた。
「取引先から連絡が来て『お宅の息子さんが来ていますよ』と。これにも驚きました(笑)。彼も幼いころから工場に顔を出していましたし、そこでは親類や近所の人が働いているわけです。その雰囲気が好きだったのでしょう。親が何も言わなくても自ら同じ道を歩み出してくれている」
瞬発力と発想力、そして人を動かす力に長ける、と自身の息子を評し「新しい時代の経営者になってほしい」と話す伊藤代表。
人手不足、技術継承の困難に頭を悩ませる経営者が多い中、伊豆の山あいに「家業」として事業を営みながら、人の縁で好循環を生み出している古き良き企業の姿がそこにはあった。