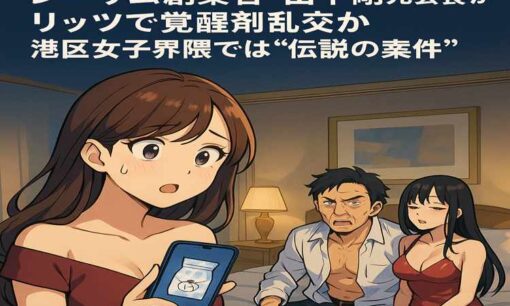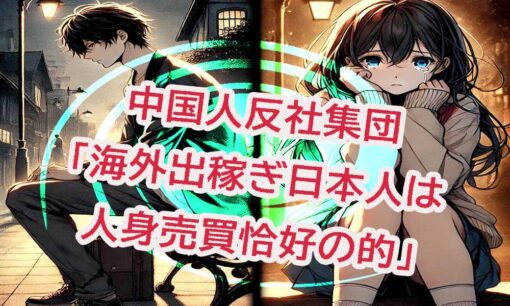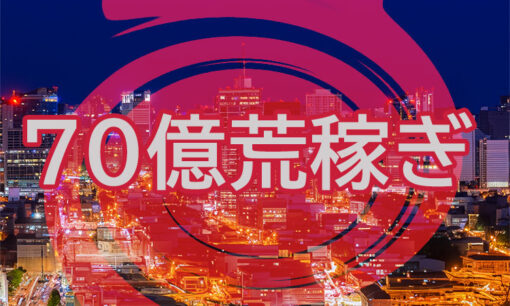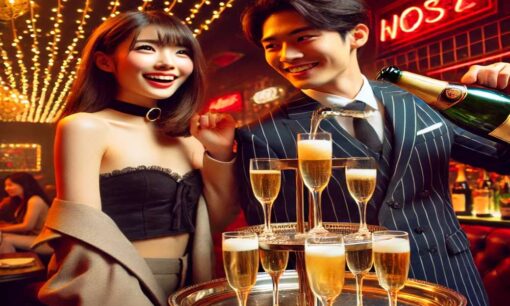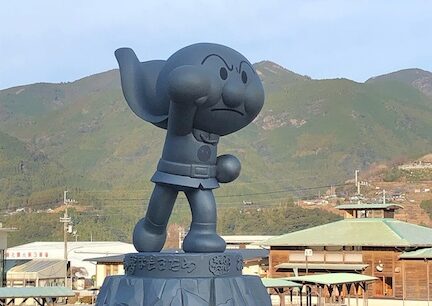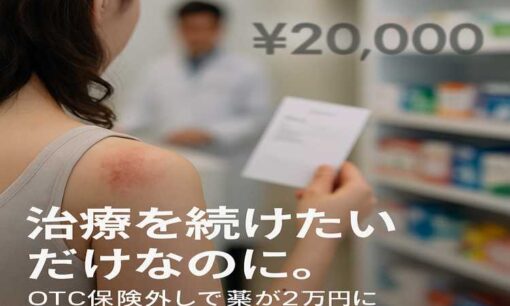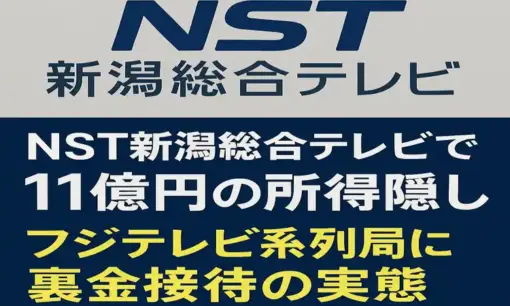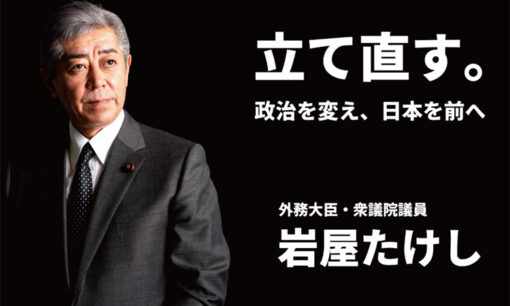SNSで突如として拡散された「ヤギとセックス」というセンセーショナルな言葉。きっかけはドバイ発の“案件女子”をめぐる投稿だったが、次第に話題の中心は「そのヤギとはどんな動物か」へと移っていった。「あれは日本人が想像する“ハイジの白ヤギ”なんかじゃない。見た目がヤバい」「気持ち悪いけど、なぜか気になる」
こうした声とともに注目されたのが、中東原産のダマスカスヤギである。
はたしてこの奇妙なヤギは、どこから来て、なぜあのような姿をしているのか。背後にあるドバイ文化とあわせて、その正体に迫った。
ドバイ女子のゴージャスな投稿が呼び込んだ、異国の動物への視線
ドバイの高層ホテルのプールサイド。煌びやかな衣装をまとい、シャンパンを片手に微笑む女性たちの姿がSNSで拡散される。日本国内でも“港区女子”という存在が語られてきたが、その上位互換とされるのが、いま注目されている“ドバイ女子”だ。
彼女たちは、ドバイに住む富裕層の男性やビジネスマンとの交流を軸に、まるで映画のような暮らしを見せつける。だが、その裏にある人間関係や資金の流れ、さらにはドバイ特有の文化的ギャップは、容易には語られない。
そんな最中、ある投稿をきっかけに、一匹のヤギが脚光を浴びることになった。見た目はまるで合成写真のように奇妙で、鼻筋が異様に盛り上がり、表情も人間じみて見える。その名は「ダマスカスヤギ」。この瞬間、動物好きからSNSユーザーまで、多くの日本人がこの“謎のヤギ”を検索しはじめた。
「どうしてこんな顔に?」──数百年を超える品種改良の果てに生まれた生物美
ダマスカスヤギは、中東地域で古くから飼育されてきた家畜であり、起源はシリアのダマスカス地方にあるとされている。最初にその姿を見たとき、驚きと違和感を覚えるのも無理はない。鼻は中央で膨れ、下顎が突き出るような形状、そして長く垂れた耳。どこか人間の顔を歪ませたような印象すらある。
だが、これは突然変異ではない。長い時間をかけた人為的な選抜交配によって生み出された、れっきとした品種なのだ。目的は単純明快。過酷な乾燥地でも生きられる強さ、高い乳量、肉としての品質。中東の人々にとって、このヤギは“機能美”の象徴であり、選ばれた姿なのである。
顔立ちについても、「奇妙」とするのはあくまで日本人の感覚だ。現地ではその容姿こそが“良血統”の証とされる場合もあり、なんと「ダマスカスヤギの美しさを競うコンテスト」まで存在する。
家畜の歴史が語る、人間と動物の関係性の深さ
中東の農村では、ヤギは単なる畜産物ではない。生活の基盤そのものである。乳を飲み、肉を食べ、皮を衣服や容器に加工する。ヤギは人間とともに家族のように生きる存在だった。中でもダマスカスヤギは、非常に効率的な乳生産を可能にするため、各地で改良が重ねられてきた。
とくに19世紀後半以降、レバノンやキプロスでも改良が進み、品種は徐々に固定化されていった。現在では主に「Shami goat(シャーミーゴート)」という名でも知られており、東地中海沿岸の農業圏では重宝されている。
この品種が“異様”に見えるのは、むしろ私たちが動物を「かわいい」か「気持ち悪い」で判断しがちなことの裏返しではないだろうか。農業・気候・宗教・美意識、すべてが異なる文化圏においては、動物の“見た目”すら評価軸が変わってくる。
日本人がダマスカスヤギに心を奪われる日が来るかもしれない
SNSでは、「グロテスクなのに、見れば見るほど気になる」「こんなヤギがいるなんて知らなかった」といった声が広がっている。もしかすると、これが“かわいい”という感覚の逆説的な発見なのかもしれない。
そして今、日本でもじわじわとエキゾチックアニマルへの関心が高まっている。ダマスカスヤギがすぐに一般家庭で飼えるようになるわけではないが、「知ることで世界が広がる」動物のひとつであることは間違いない。単なるバズで終わらせるには、あまりに奥深い歴史と文化を背負っている。
ドバイ女子の華やかな世界の裏で、ひっそりと浮かび上がったダマスカスヤギという存在。その奇妙な姿の奥には、人と動物の営みの歴史と、多様な価値観の交差点が広がっていた。次にこの名前を目にしたとき、あなたはその「顔」を、もう一度じっくりと見つめてみたくなるかもしれない。