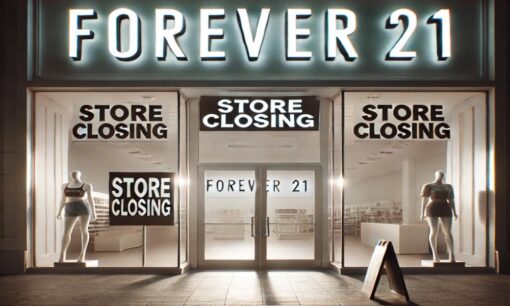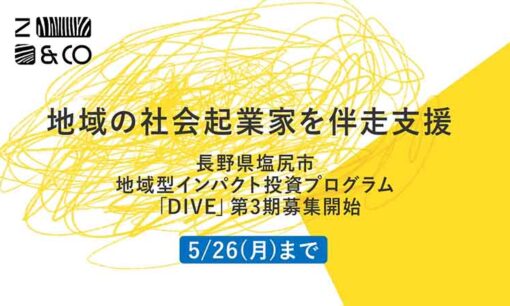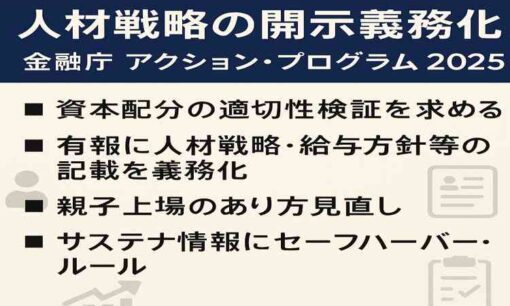おたふく風邪(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症である。主に子どもがかかる病気として知られるが、合併症による後遺症が残る例もあるため、予防の重要性が近年あらためて注目されている。
宮崎市内では現在、おたふく風邪ワクチンの全国的な供給不足を受け、年長児(6歳)を対象とする接種の制限が始まっている。供給減の背景には、国内2社の製造業者のうち1社が出荷を停止している事情がある。出荷再開の見込みは早くても2025年9月とされ、それまでの間、接種対象の選定が各医療機関に委ねられる状況が続く。
おたふく風邪とはどんな病気か
おたふく風邪は、耳の下から顎にかけての腫れ(耳下腺の腫脹)が特徴的なウイルス感染症で、発熱や頭痛、倦怠感などを伴うこともある。感染力が強く、飛沫感染や接触感染によって広がるため、保育園や小学校などで集団発生することも珍しくない。
一般的には軽症で済むことが多いが、無症状または軽い風邪症状だけで経過することもあるため、感染に気づきにくい点も特徴だ。
しかし、もっとも注意すべきは「合併症」の存在である。特に小児や思春期以降の感染者に見られる「ムンプス難聴」は、一度発症すると治療が難しく、永久的な聴力障害を残す場合がある。国立感染症研究所によれば、1万人に1〜2人の割合で発症するとされている。
予防接種の時期と対象年齢
おたふく風邪ワクチンは現在、任意接種(公費対象外)であり、自己負担が必要である。それでも、多くの小児科では、集団生活が始まる前の1歳児と、小学校入学を控える6歳児への2回接種を推奨している。
| 接種回数 | 推奨年齢 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 1回目 | 生後12か月~15か月 | 1歳を迎えたらできるだけ早めの接種が望ましい |
| 2回目 | 5歳~7歳未満 | 抗体の持続を狙って1回目から5年ほどあけて接種 |
現在は、ワクチン不足により6歳児への接種を一時的に見送る医療機関もあり、実際に宮崎市の「さとう小児科」では、1歳児への接種を優先する対応を取っている。
ワクチン接種で期待できる効果
おたふく風邪ワクチンは、1回の接種で約90%、2回接種で95%以上の予防効果が期待されている。感染を完全に防ぐことはできない場合もあるが、重症化や合併症のリスクを大きく下げることができる。
特に、難聴や脳炎、髄膜炎、睾丸炎などの重い合併症を予防するうえで、接種の意義は大きい。これらの合併症は、稀ではあるものの、後遺症が残るケースがあることから、医師の間でも接種の必要性は広く共有されている。
宮崎市の佐藤潤一郎医師は、「大人になってから聴力障害が判明し、その原因をたどると子どもの頃にかかったおたふく風邪だったという例がある」と述べ、接種の重要性を訴える。
他にもある、乳幼児のワクチン不足
2025年春時点で、全国的に供給が滞っている予防接種用ワクチンは、おたふく風邪ワクチンに限られない。以下に、特に乳幼児期に接種が推奨されているが、供給不足が懸念されている主なワクチンを示す。
| ワクチン名 | 対象年齢・接種時期 | 状況・補足情報 |
|---|---|---|
| おたふくかぜ | 1歳・6歳(任意) | 国内2社のうち1社が出荷停止、供給半減。9月再開見込み |
| MR(麻しん・風しん混合) | 1歳・就学前(定期) | 武田薬品製品の出荷停止。他社が増産中だが、依然として供給逼迫が続く |
| 日本脳炎 | 3歳・4歳・9歳(定期) | 2021年に生じた製造停止の影響で接種漏れが残存し、地域によっては不足の懸念あり |
各自治体では、対象年齢の延長措置や代替日程の案内などで対応を図っているが、接種を希望する家庭は早めに医療機関へ相談し、スケジュールを確認することが望ましい。
今後の見通しと注意点
ワクチンを製造している企業の一部では、品質管理や製造設備の点検のため、一時的な出荷停止を余儀なくされている。国や自治体はメーカーへの増産要請を行っているものの、十分な供給体制の確保には時間を要する見通しだ。
特に感染症による合併症は、時間をおいて判明することもあるため、日頃から予防接種記録の管理を徹底し、接種漏れを防ぐことが求められる。