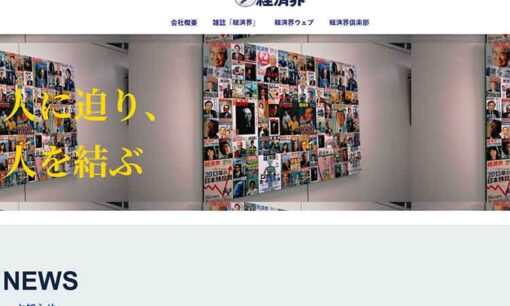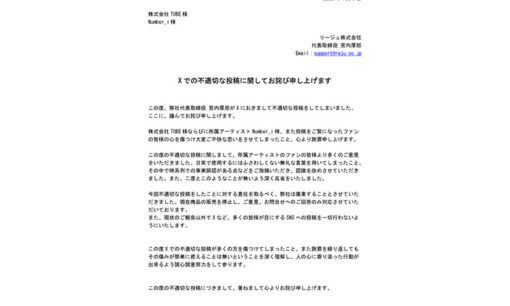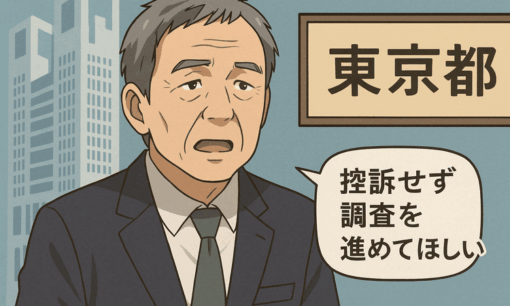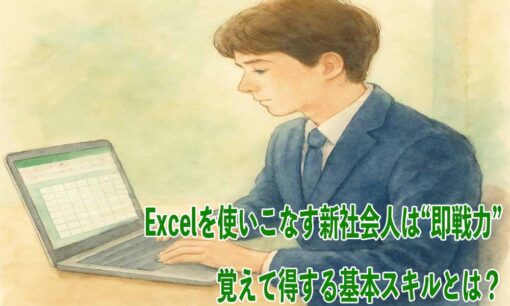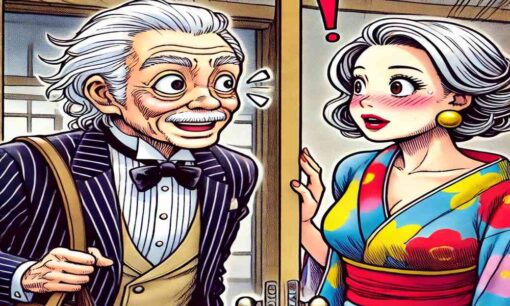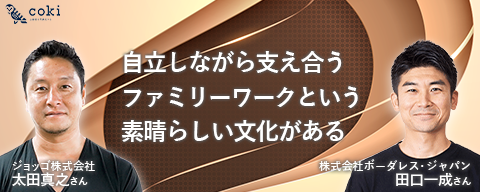大阪市西成区で、中国人経営者による民泊が急増している。阪南大学の松村嘉久教授(観光地理学)が調べたところ、国家戦略特区制度に基づいて市から認定された特区民泊5,587件(2024年末時点)のうち、41%に当たる2,305件を中国系事業者が運営していた。半数は2022年以降に認定されており、コロナ禍後に一気に拡大したという。
SNSが煽る「簡単移住」
資本金500万円の出資と事業所確保で取得できる在留資格「経営・管理ビザ」の敷居の低さが、移住拡大の原動力だ。中国版インスタグラム「小紅書(RED)」には〈日本語ができなくても問題ない〉〈民泊が一番簡単〉といった投稿が並び、行政書士や物件仲介業者の連絡先が添えられている。
天下茶屋の長屋を改装した民泊を営む張華さん(32、仮名)は「SNSで知った行政書士に依頼し、3か月でビザが下りた」と話す。日本語は話せないが、中国語対応の仲介業者が物件探しから購入手続きまで代行してくれたという。
“裏方”が支える移住ビジネス
大阪市内の行政書士法人には「民泊でビザを取りたい」という相談が週に複数寄せられる。不動産仲介会社は築50年以上の木造住宅をリフォームし、家具付きで販売。担当者は「投資よりも生活拠点として買う人が増えた」と明かす。
SNS経由で集客し、法人設立から物件取得、家具設置までをワンストップで請け負う仕組みが出来上がっており、中国語圏の顧客が中心だ。
住民との摩擦と制度の空洞化
西成区に40年住む女性に話を聞くと、「コロナ後、近所は中国人の民泊ばかり。深夜の出入りやゴミ出し違反が増え、転居を考えている」と語る。SNS上には〈行政は問題を放置している〉との不満も目立つ。
経済ジャーナリストの浦上早苗氏はSNSで「永住権の取得も相対的に容易で、中国では“日本の永住権を取ったら帰国してもいい”との声もある。制度が目的通り運用されているか検証が必要だ」と指摘する。
共生へ向けた手がかり──京都モデルと自治会の工夫
排除か受け入れか――議論が進むなか、共生を模索する動きもある。京都市は民泊営業を始める前に近隣住民への説明を義務づける条例を施行し、事業者と住民が顔を合わせる場を制度化した。
大阪市港区では自治会が外国人住民と合同で清掃活動や防災訓練を実施。「顔を合わせればトラブルは減る」と町会長は話す。西成区でも同様の仕組みを求める声が上がり、市担当者は「既存の住民説明会ルールの拡充を検討中」としている。
松村教授は「経営・管理ビザは事業を行う外国人のための資格。民泊との接続が移住の抜け道になれば制度の空洞化は避けられない。自治体と入管の連携による実態調査と、地域での対話の仕組みづくりが急務だ」と読売新聞の報道で警鐘を鳴らす。
ビザ統計が示す拡大トレンド
入管庁統計を基にした行政書士の分析によれば、経営・管理ビザ保有者は2024年6月末で39,616人。そのうち中国人は52%の20,551人を占める。外国人雇用サポート 同じ時点の在留中国人数は84万4,187人と過去最多を更新した。
制度の穴は塞げるか
宿泊需要が高まる大阪・関西万博を控え、民泊市場はさらに膨張が見込まれる。500万円で取れるビザは「開かれた門」か、それとも「制度の穴」か――。地域と制度の両輪で、持続可能な共生モデルを描けるかが問われている。