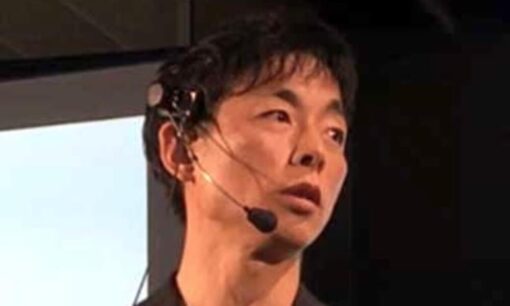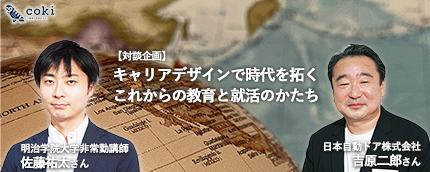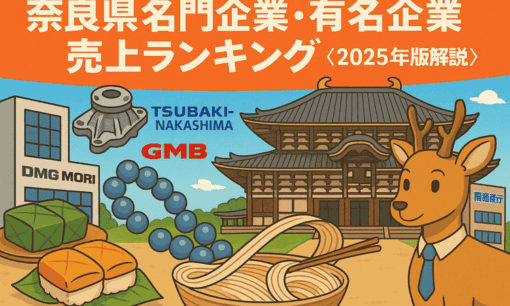温暖化に備えるインフラ整備の実務指針に
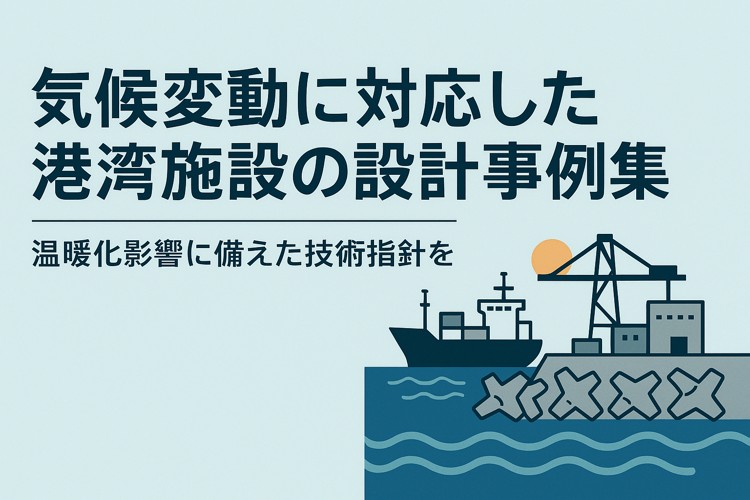
国土交通省港湾局は、4月に「気候変動に対応した港湾の施設の設計事例集」を公表した。これは部分改訂された「港湾の施設の技術上の基準及び同解説(以下、港湾基準)」に対応するもので、気候変動により変化する外力や設計条件を踏まえ、今後の港湾施設設計における指針を体系的に示したものである。
同事例集は、「港湾における気候変動適応策の実装に向けた技術検討委員会」の審議成果を基に構成されている。代表的な施設として、防波堤、岸壁、護岸を取り上げ、それぞれの設計条件の設定例と照査方法を事例形式で解説している。
RCP2.6を想定しつつ、予測の「上振れ」にも備える設計
本事例集においては、気候変動による将来の外力を見積もる際、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書で用いられた「RCP2.6シナリオ」を基本とする。このシナリオは、パリ協定における2℃未満の平均気温上昇目標が達成される前提で構成されたものであり、低炭素化が進んだ将来像を描いている。
しかし国交省は、温暖化予測には必然的に不確実性が伴うとの立場をとり、将来予測が平均値を上回る「上振れリスク」への備えも設計段階で講じるべきだとしている。そのため、外力の設定にあたっては平均的な将来値だけでなく、上限寄りの予測幅を考慮した設計が求められる。
たとえば潮位においては、20世紀末(1995年)から21世紀末(2090年)にかけて、上位シナリオで最大55cmの平均海面上昇が想定される。波高についても地域差があるものの、四国太平洋側では30年確率波高で1.10倍の将来変化比が提示されている。
「事前適応策」と「順応的適応策」の選定を明示
設計対象施設が長期間にわたり使用されることを考慮し、国交省は、気候変動への対応として大きく二つの適応策を示している。ひとつは、設計段階から将来の気候変動を見越して構造を強化する「事前適応策」。もうひとつは、設計時点では現行条件を前提にしつつ、将来の気候変化に応じて段階的な改修を行う「順応的適応策」である。
たとえば新設の消波ブロック被覆堤の設計事例では、天端高を当初から引き上げることで、将来的な施工の手戻りを避ける事前適応策が採用されている。一方、岸壁などでは、船舶の利用に支障が出る恐れから、順応的な段階対応を前提とするケースが想定される。事例集ではこうした判断フローも図示されており、実務者が各施設に適した方針を選定できるよう配慮されている。
設計照査に用いる外力の定義と算出手順も整理
事例集では、性能照査に用いる外力(作用)について、現在の気候状態に基づく「現在の作用」と、将来の変化を見越した「将来の作用」を明確に区別して整理している。たとえば、設計波高においては、将来の波浪条件に対して一定の変化率(変化比)をかけて波高を再定義する。さらに潮位偏差などについても、1980年から2040年までの年変化率をもとに、2090年に向けた予測値が線形に算出される手法が示されている。
特に注目すべきは、これらの将来作用を決定する際の「基準年」の考え方である。設計年時点の最新観測データの分析結果に応じて基準年が変動し、複数の手法(観測値に基づく新設定、従来値の再採用など)が選択可能とされている。事例集ではこの基準年設定のフローも丁寧に解説されており、今後の港湾設計における指針として有用である。
今後の設計・改修計画への実装に期待
国交省港湾局は、「本事例集は令和6年改訂の港湾基準に基づいて取りまとめたものであり、今後も技術開発や予測モデルの進展に応じて見直していく」としている。港湾施設は数十年にわたって使用されるインフラであり、設計段階での柔軟な想定が将来の維持管理や改修コストの最適化につながる。
気候変動が社会の持続可能性に大きな影響を与えることが明らかになるなかで、港湾施設も例外ではない。本事例集が各地の設計現場に広く活用され、より実効性の高いインフラ整備につながっていくことが期待される。