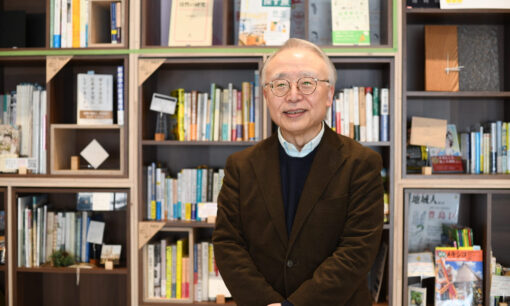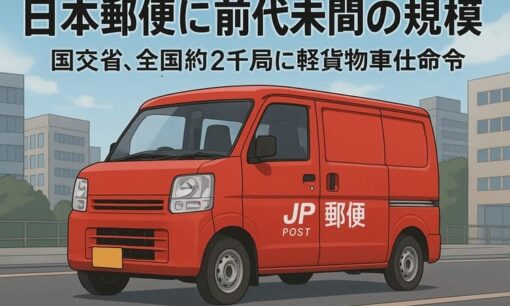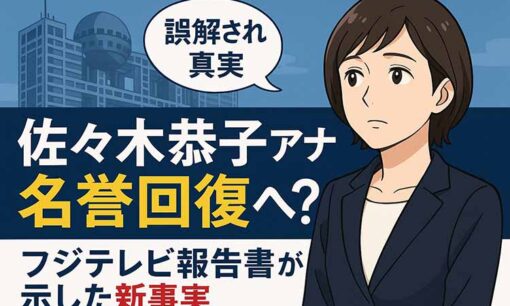足立区で進む「コーヒーかすアップサイクル」の実装が、新たな局面を迎える。ユーエスフーズとソーイが、区主催のSDGsイベント「ぐるぐる博」で、捨てられていたコーヒーかすを飲料や菓子へ再生する実証を行う。循環型モデルを地域の来場者に可視化する機会となる。
コーヒーかすを食品へ再利用する発酵アップサイクル技術
使用後のコーヒーかすは、通常であれば廃棄される。環境省によると、日本国内では年間数万トン規模が排出されると言われ、飲料産業が抱える構造的課題のひとつとされている。
今回のプロジェクトでは、足立区内のコーヒー店から回収したコーヒーかすを、ソーイの特許技術「UP0TECH®」によってペースト化し、食品として再活用する。300年続く発酵技術を背景に持つ同社の加工技術は、地域で排出される素材に新たな価値を与える点で独自性がある。
足立区SDGsイベント「ぐるぐる博」で循環型コーヒーを披露
足立区が主催する「ぐるぐる博 in 来た!アヤセ 2025」は、地域の住民や事業者が得意分野を持ち寄るSDGsイベントだ。今回の出店では、加工したコーヒーペーストを使ったドリンクや焼き菓子が販売され、来場者は“元は不要物だった素材が食品になる”プロセスを体験できる。
イベントは11月29日に北綾瀬のしょうぶ沼公園で開催される予定で、地域の挑戦を共有する場として定着している。
地域内で完結するローカルサーキュラーエコノミーの実装
区内の複数の自家焙煎店がコーヒーかす提供に協力しており、回収から加工、商品開発、販売に至る一連の流れが足立区内で完結している点は注目に値する。
「地域で生まれた素材を地域で価値化する」という構造は、サーキュラーエコノミーの理念を端的に示す。イベント出店は、こうした循環が“机上の構想ではなく、すでに現実として動いている”ことを示す実証の場となる。
コーヒー産業が抱える環境負荷と技術企業の役割
コーヒーの大量消費が続く一方、生産国は気候変動や労働環境など多くの課題を抱える。消費地である都市には、廃棄物処理や環境負荷の問題も残る。
こうした構造の中で、使用後の素材を再び食品として循環させる技術は、産業の持続性に現実的な選択肢を提示する。会場ではソーイ代表の石垣氏が同社の取り組みを説明する予定で、課題と向き合いながら価値を生む技術者の姿勢が鮮明に表れる。
ユーエスフーズが描く“循環型コーヒー”の未来と可能性
ユーエスフーズは「コーヒーがつなぐ素敵な出会いを、次の世代に」という理念を掲げて活動してきた。教育プログラム「珈育(コーイク)」や、社会課題と向き合う「えがおプロジェクト」を通じて、コーヒーの背景にある世界的な課題を伝え続けてきた企業でもある。
今回の出店は、同社が描く“循環型コーヒー”の未来像を実地で示すものとなる。地域企業と共に挑戦する取り組みは、今後の地域循環モデルとして他地域にも波及する可能性を持つ。