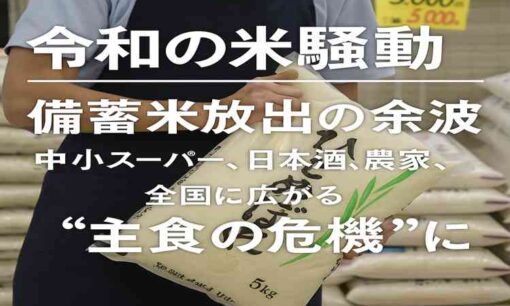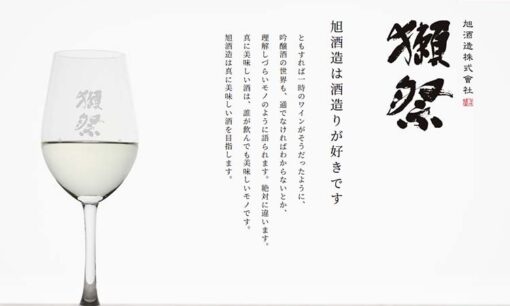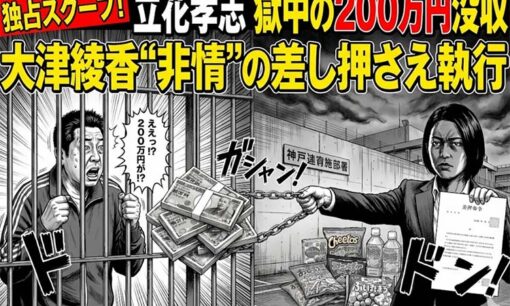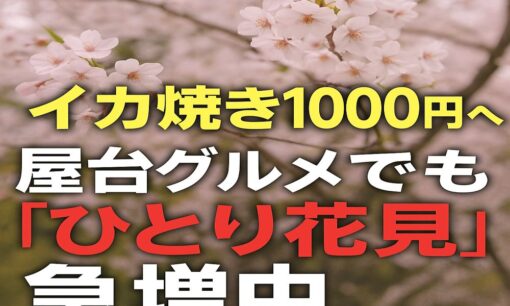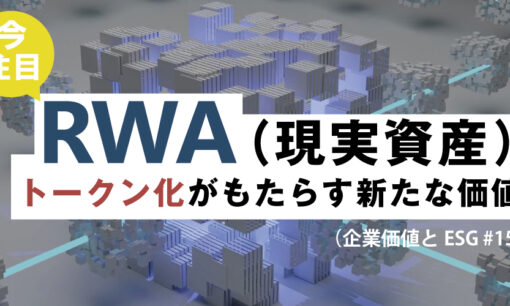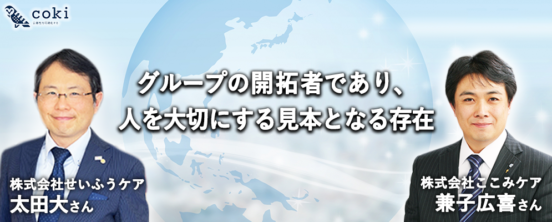アルミ缶入り日本酒の先駆として知られる新潟の菊水酒造が、SDGsの潮流を追い風に、容器革新を軸とした新戦略を打ち出している。
食品新聞の取材によると、1972年発売の元祖生原酒缶「菊水 ふなぐち」は累計3億本を超えるロングセラーであり、同社はここに安住せず、ボトル缶の新充てんライン稼働や外部蔵の充てん受託など、酒蔵の枠を超えた挑戦を進めている。環境配慮と日常酒の新たな価値創造を両輪に、日本酒市場が縮小する時代にどのような道を拓こうとしているのか、その動きを追った。
小容量需要の高まりが示した“半世紀前の先見性”
1972年、「菊水 ふなぐち」が市場に姿を現した。当時の日本酒市場は一升瓶が当然の時代であり、旅行やレジャーの普及を背景に「持ち運びやすい酒」へのニーズが芽生えつつあったものの、業界の主流は大容量瓶に根強く依存していた。
菊水酒造の先代社長である故・髙澤英介氏は、社会の動きを敏感に読み取り「いずれ小容量の時代が来る」と予見していた。酒蔵を訪れた客に振る舞っていた搾りたての生原酒が好評を博したことが開発を後押しし、遮光性が高く品質劣化を抑えるアルミ缶へと行き着いた。
製造工程の見直しや技術的課題の克服を経て生まれた「ふなぐち」は、発売当初こそ市場に浸透するまでに時間を要したが、いまや“コンビニ最強酒”として評価を確立し、レギュラー品に熟成タイプ、季節酒、スパークリングなど多彩な派生商品を持つブランドに育った。
同社のアルミ缶清酒の供給能力は日産最大10万本。半世紀におよぶ経験値は、国内トップクラスの知見として揺るぎない。
充てん受託で広がる“缶の文化” 酒蔵横断の新ビジネス
近年、同社のアルミ缶充てん技術が他蔵の注目を集めている。ボトリングラインを自前で持たない中小蔵にとって、設備投資をせずにアルミ缶商品を市場投入できるメリットは大きい。
髙澤大介社長によると、問い合わせは昨年ごろから増加し、今年2月より本格対応を開始。現在は4蔵を受託し、将来的には10蔵程度まで広げる見通しだという。
日本酒市場が右肩下がりのなか、各蔵が生き残りを模索する時代にあって、菊水酒造の取り組みは「瓶中心」の固定観念を揺さぶるものだ。他蔵との連携を深めながら、業界全体で缶のプレゼンスを押し上げる構想は、地方の酒蔵が共存の道を模索する一例として注視すべき動きと言える。
ボトル缶ラインが稼働 変化する生活スタイルに応える挑戦
8月下旬、同社製品棟で新たなボトル缶の充てんラインが稼働した。
外部委託していた「菊水の辛口 500ml」の内製化に踏み切ったのは、生活スタイルの変化を見据えた経営判断である。
髙澤社長は「デイリーの日本酒をもっとカジュアルに楽しんで欲しい」と語る。飲酒量の減少、家飲みの多様化、1日1杯程度の嗜み型飲酒の拡大など、消費行動は確実に変化している。こうした中で、リキャップ可能な500mlボトル缶は、新たな“日常酒”の形として有力視されている。
新ラインは300mlなど多様な容量に対応でき、家庭内のさまざまな飲酒シーンへの提案力を高める。環境面だけでなく、消費者のライフスタイルに寄り添う柔軟性こそが、同社の競争力の源泉となる。
アルミ缶が切り拓くSDGs時代の酒文化
SDGsの観点でも、アルミ缶はきわめて強い利点を持つ。アルミニウムは“CAN to CAN”の循環が可能で、瓶のように高温処理や大きなエネルギーを必要とせず再資源化できる。
また、瓶に比べて軽量で省スペースのため、家庭や店舗での保管負担が少なく、物流時のCO₂排出削減にも貢献する。
髙澤社長は「日常酒の容器が環境に優しいことも重要になる」と強調する。環境配慮が生活者の購買行動を左右する時代に、小容量・軽量・リサイクル効率の三拍子が揃うアルミ缶は、日本酒の未来を支える基盤となり得る。
瓶中心の歴史が長い日本酒業界において、“容器の転換”は容易ではない。しかし菊水酒造は、味やブランド価値だけにとどまらず、日本酒文化そのものの持続可能性を問い直す姿勢を示している。
先駆者だからこそ描ける次の50年
半世紀前に小容量の可能性を見出した同社は、いま再び酒類市場の転換点に立っている。
生活者の価値観が変わり、環境負荷が問われる時代において、アルミ缶は日本酒にとって「過去の延長線」ではなく「未来の入り口」となりつつある。
髙澤社長が語る「新たな価値を提供して市場を創っていきたい」という言葉は、単なるメーカーの戦略を超え、地域産業の持続性への確かな手応えを伴っている。アルミ缶清酒の文化を広げるため他蔵との共創を進める姿勢も、SDGs時代の産業像を体現している。
50年前に缶入り清酒の市場を切り拓いた企業が、SDGsを旗印に再び大きな役割を担おうとしている。日本酒が未来へと続くための道筋は、いまアルミ缶の軽やかな手触りとともに形を帯びてきた。