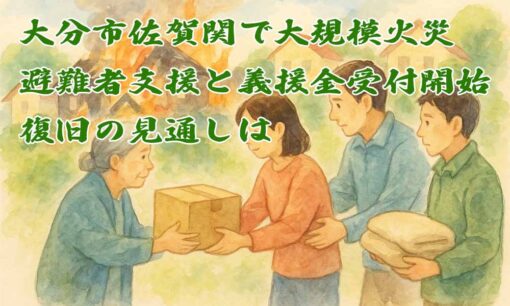人手不足の“最後の切り札”が、早くも波紋を広げている。ヤマト運輸がベトナム人ドライバー100人を採用へ――というニュースに、SNSでは「もう日本じゃ人が集まらないのか」「外国人に任せて大丈夫か」とざわついた。現場は期待と不安、そして本音が入り混じる。物流の現場に今、何が起きているのか。
「外国人100人採用」の裏で
締結式は都内の本社ビルで粛々と行われたが、現場の空気はまったく別物だ。
「うちはもう、40代でも若手扱いだからね」「来年の繁忙期は乗り切れんぞ」と、トラック運転手たちの休憩所では本音が飛び交う。
ベトナム人採用のニュースが社内メールで回った瞬間、「また現場に丸投げか」とつぶやく声もあった。
ヤマト側は「多様な人材を受け入れる体制を整える」と説明するが、教育係に任命された社員は「英語もベトナム語もわからないまま教えろって?」と苦笑いする。
外国人採用が“希望の光”か、それとも“新たな負担”か。いま現場では、複雑な感情が入り混じっている。
SNSが騒然「日本人より安いのでは」
発表の翌日、X(旧Twitter)はこの話題で持ちきりになった。
「結局、外国人の方が安く使えるんでしょ」「安全面どうするの?」「運転中に言葉が通じなかったら事故になる」――コメント欄は荒れに荒れた。
中には「日本人の給料を削って海外から雇うって、どんな国だよ」と辛辣な意見もある。
ヤマト運輸が特定技能制度を活用することは、法的には何ら問題がない。だが、国民の感情は別だ。
「物流の象徴」だったヤマトが外国人に舵を切る――その事実が、多くの人にショックを与えている。
「もう“ヤマトベトナム運輸”になるのでは」と揶揄する投稿も数千件にのぼり、火の手はなかなか収まらない。
現場が抱える“きれいごとではない”現実
ヤマトは「教育から生活支援まで徹底する」と発表している。だが、地方の支店にまでその体制が行き届くかは疑問だ。
「英語マニュアルが届いても、誰も読めない」「通訳を雇う予算なんてない」と、ある支店長はため息を漏らす。
新人教育の負担は増え、運行管理者たちは頭を抱えている。
一方で、現場にはすでに数名のベトナム人倉庫スタッフが勤務している。
彼らは真面目で温厚だが、時折の文化ギャップがトラブルを呼ぶ。
「“はい”と言っても理解してないことがある」「事故が起きてからじゃ遅い」との声も上がる。
現場の社員は「紙の上の理念」と「道路上の現実」の違いに、冷ややかな視線を向けている。
「働きたい人」と「働かせたい企業」のズレ
制度の建前と、現場の現実。
ヤマトが掲げる「共生社会」や「国際連携」の言葉は美しい。だが、現場では「そんな言葉、聞いたこともない」と苦笑されるのが実情だ。
「人が足りないから外国人を雇う」――それ自体は合理的だが、待遇や教育を改善しなければ、同じことの繰り返しになる。
SNSでも、「結局、使い捨てにされるのは外国人も日本人も一緒」といった冷めた意見が目立つ。
現場からは「上は“共生”を語るけど、俺たちは“共存”どころか共倒れ寸前」と皮肉まじりの声も。
“働きたい人”と“働かせたい企業”のズレ――この構図こそが、今の日本社会を象徴している。
終わりに――それでも走らなきゃ
夜明け前の高速道路。街灯の下で、黒いヤマトのトラックが音もなく動き出す。
そのハンドルを握るのは、もしかしたらベトナムから来た青年かもしれない。
彼らは希望を胸に、異国の道路を走る。だが、その裏で指導員は頭を抱え、SNSでは炎上が続いている。
それでも、荷物は待ってくれない。
日本社会はこの現実をどう受け止めるのか。
美談でも批判でもなく、“止められない現実”がいま、静かに走り出している。