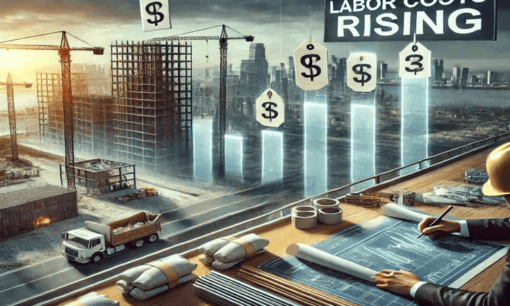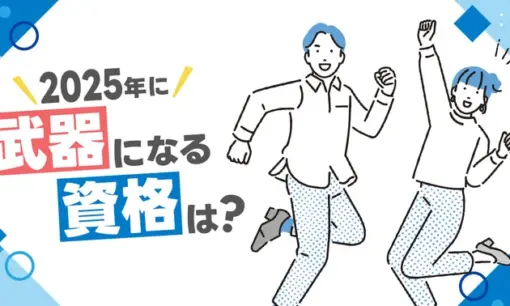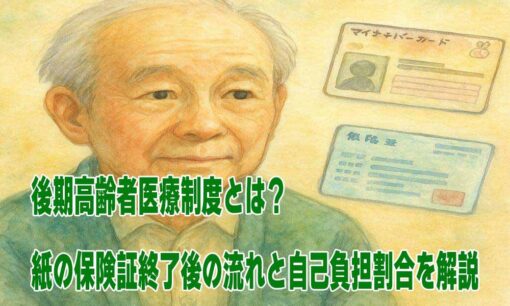大阪府茨木市の「アマゾン茨木フルフィルメントセンター」で発生した火災は、発生から丸1日が経過した12日午前時点でも消火活動が続いている。関係者によると、防火扉が作動し延焼の危険は抑えられているが、鎮火の見通しは立っていないという。
火災は11日午前10時20分ごろに発生。4階建て倉庫の3階部分から出火したとみられる。当時約370人の従業員が勤務していたが、全員が避難し、けが人は確認されていない。現場はJR総持寺駅から西に約1キロ、物流施設が建ち並ぶ一角にある。
センターは延べ床面積約6万4000平方メートルを誇る国内有数の拠点で、2019年の本格稼働以降、ロボットを活用した自動仕分けやAIによる在庫管理など、最新技術を導入してきた。
それだけに「火の手が上がった」というニュースは、物流業界に衝撃を与えている。
リチウム電池など「混在倉庫」のリスク
専門家によれば、アマゾン倉庫のように日用品から家電まで多種多様な商品を扱う施設では、可燃物や発火性のある製品が混在する。特にリチウムイオン電池は過充電や衝撃により発火する危険があり、取り扱いには高度な安全管理が求められる。
「燃えるモノ」は消防法上、危険物や指定可燃物に分類される。大量に保管する場合には届出と適切な区画管理が義務付けられているが、商品が常に入れ替わる物流センターでは実態把握が難しいという。
かつてアスクルの物流倉庫火災でも鎮火まで約1週間を要し、日立物流の倉庫火災でも同様に長期化した経緯がある。いずれも「延焼しやすい包装資材」「危険物保管の区分不備」などが指摘されており、今回の火災も構造的課題を浮き彫りにしそうだ。
自動化システムの限界も
アマゾンは自動消火設備やAIによる異常検知システム、分散型煙検知など高度な安全機構を導入している。今回も防火シャッターが作動し延焼を防いでいる点は一定の成果といえる。
しかし一方で、現場の消防関係者は「可燃物の密度が高く、燃焼が内部で続いている」と話す。自動倉庫においては、通路や空間が狭く消火活動が物理的に困難になる場合もあり、最新技術の導入だけでは防ぎきれない課題がある。
火災原因の特定はこれからだが、リチウム電池を含む商品の扱いや電源設備のトラブルなど、複合的な要因の可能性も指摘されている。
物流インフラの脆弱性を問う
今回の火災は、単なる一企業の事故にとどまらない。オンライン注文が急増する中、アマゾンの倉庫は全国の配送網の中核を担う。物流が一時的に滞るだけでも消費者や取引先への影響は甚大だ。
アスクル火災の際には、倉庫1カ所の停止で数百億円規模の損失が発生した。アマゾンのようなグローバル企業であっても、国内の物流基盤が火災リスクに脆弱であることは改めて認識すべきだろう。
防火設備が作動しても鎮火に時間を要する現状は、従来の消防・防災体制の限界を示すものだ。
原因究明と再発防止策の策定が急がれる。