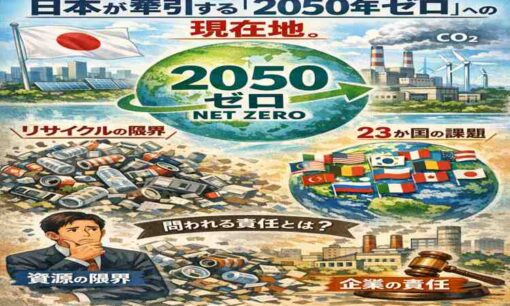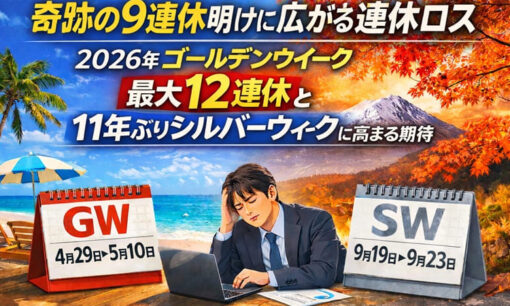2025年10月3日、日本の通貨製造を担う独立行政法人である造幣局から、驚くべき発表があった。広島支局の職員が、市中から回収された500円硬貨174枚(8万7千円分)を不正に持ち出していたというのである。この事件は、単なる職員の不正行為にとどまらず、通貨制度を支える機関の信頼を揺るがす重大な事態として、社会に大きな衝撃を与えた。
発覚のきっかけは「内部通報」
事件の始まりは、2025年6月末に造幣局に寄せられた一本の内部通報だった。通報の内容は「貨幣が不正に持ち出された可能性がある」というもの。これを受け、造幣局は直ちに内部調査を開始した。
調査の結果、監視カメラの映像に、職員が貨幣を外部に持ち出すような姿が写っていることが確認された。さらに、関係者への事情聴取を進めたところ、回収貨幣174枚が不足していることが判明。不正行為を行ったのは、再任用職員として勤務していた60代の男性であった。
男性職員は、調査に対し「買い物に使った。魔が差した」と不正の一部を認めたが、その後、死亡したことが明らかになっている。事件の全容が本人から語られることは、もうない。
そもそも造幣局とは?
多くの人にとって、造幣局は身近な存在ではないだろう。しかし、私たちの日常生活に欠かせないお金、つまり貨幣を製造しているのが造幣局である。
造幣局は、財務省所管の独立行政法人として、日本の通貨制度を支える重要な役割を担っている。新しい貨幣を製造するだけでなく、市中で古くなった貨幣を回収し、それを溶かして新しい貨幣に生まれ変わらせるという、循環システムも担っているのだ。
今回の事件で不正に持ち出されたのは、まさにこの「回収貨幣」であった。本来、溶解されて新しい硬貨に生まれ変わるはずだった硬貨が、男性職員の手によって外部に持ち出されたのだ。
巧妙な手口か、杜撰な管理か
男性職員が担当していたのは、市中から回収された古い貨幣を、溶解設備に入れるためのコンテナに移し替える作業だった。報道発表資料によると、彼はこの作業中に500円玉を抜き取り、6月26日から28日までの3日間にわたって、計174枚を持ち出したとみられている。
問題は、なぜそのような不正が許されたのかという点だ。本来、貨幣製造を担う造幣局では、厳格なセキュリティ対策が講じられているはずである。しかし、今回の事件では、ずさんな管理体制が浮き彫りとなった。
造幣局の発表によると、作業場の出入り口には金属探知機が設置されていたにもかかわらず、規定通りに運用されていなかったという。その理由は、職員が着用するヘルメットに金属片が付いていたため、アラームが鳴っても詳しく調べずに通過させていたというのだ。
本来、安全を守るための設備が形骸化し、事実上機能していなかった。こうした杜撰な管理体制が、男性職員の不正を可能にした大きな要因だと考えられる。
組織全体に蔓延していた「緩み」
今回の事件は、一職員による個人的な不正行為というだけでなく、造幣局という組織全体に潜む構造的な問題を示唆している。造幣局が公表した調査結果では、以下の点が指摘されている。
- 内部規定の形骸化:金属探知機のずさんな運用だけでなく、現場での管理監督者の立ち会いがおろそかになっていた。
- 人事管理の硬直化:上司による職員の身上把握が不十分で、異変に気づくことができなかった。
- 閉鎖的な組織風土:内部規定違反があっても、すぐに声を上げて是正する雰囲気がなく、牽制機能が働かなかった可能性がある。
これらの問題は、造幣局という独立行政法人が、国民の信頼のもとで通貨を管理するという、極めて重要な役割を担っていることと、あまりにもかけ離れた実態ではないだろうか。
信頼回復に向けた「ガバナンス改革」
造幣局は今回の事態を重く受け止め、2025年10月3日付で関係職員の懲戒処分を公表した。溶解課の課長や主事ら計6名が減給や戒告の処分を受け、さらに前理事長と担当理事も報酬を自主返納するなど、組織としての監督責任を明確にした。
また、二度とこのような事態を起こさないために、再発防止策を公表し、組織のガバナンス改革を本格的に進める姿勢を示している。具体的な対策は以下の通りだ。
- 管理体制の徹底・強化: 回収貨幣の移し替え作業における職員の配置や、防犯機器の適正な運用を徹底する。
- コンプライアンスの徹底: 役員が現場を訪問し、職員との意見交換を行うほか、外部専門家による研修を実施する。
- 職員の身上把握の徹底: 管理者が定期的に職員のストレスや不満を吸い上げ、異変に気づける体制を構築する。
- 内部監査の適切な実施: 本局からの牽制機能を発揮し、内部監査を強化する。
- リスク管理の強化: 組織全体のリスク評価を見直し、再発防止策の進捗をフォローアップする。
- 再発防止委員会(仮称)の設置: 理事長が主導し、外部有識者も加えた委員会を設置し、ガバナンス強化策を継続的に検討する。
これらの対策を確実に実施することで、失われた国民の信頼を回復できるのか。今後の造幣局の取り組みが注視される。
繰り返される「魔が差した」の連鎖
今回の事件で男性職員は「魔が差した」と語ったという。しかし、この言葉は過去の不祥事でもしばしば使われてきた。
例えば、過去に起きた公的機関での横領事件や不正行為でも、当事者は「魔が差した」と語ることがある。しかし、その背景には、個人のモラル低下だけでなく、チェック機能が働かない組織の構造的な問題や、周囲が異変に気づくことができないコミュニケーション不全などが潜んでいることが多い。
造幣局の今回の事件も、まさにこの典型的な例と言えるだろう。内部通報がなければ、不正は明るみに出ることなく、そのまま闇に葬られていた可能性も否定できない。
信頼回復への道のり
造幣局は「通貨制度を支える独立行政法人として、あってはならないこと」と深く謝罪している。そして、今後は再発防止策を確実に実施し、国民の信頼回復に努めると誓っている。
しかし、一度失った信頼を取り戻すことは容易ではない。今後の造幣局には、公表した再発防止策を着実に実行するだけでなく、外部からの厳しい目にも耐えうる、透明性の高い組織運営が求められる。
日本の通貨を支える最後の砦である造幣局が、今回の事件を教訓として、真に国民に信頼される機関へと生まれ変われるか。その真価が問われている。
参照:令和7年10月3日付報道発表について(造幣局)