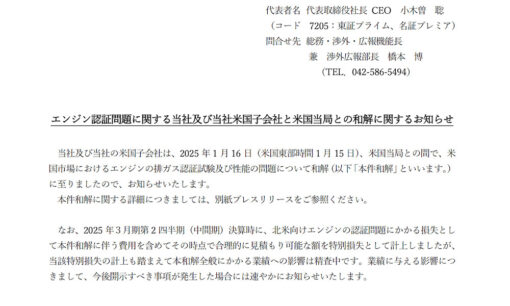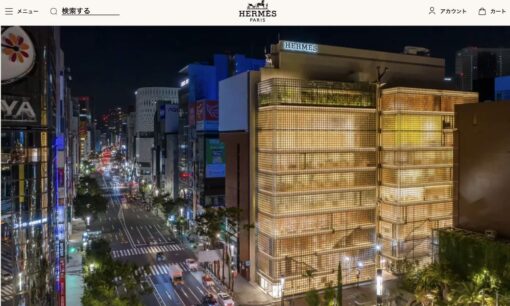日本郵便で発覚した不適切な点呼問題は、ついに配達の主力である軽バンにも処分の矛先が向けられた。国土交通省は東京や大阪の郵便局を皮切りに、全国で最大約2000局を対象に軽貨物車の使用停止処分を科す方針を固めている。郵便や宅配便の配達網に大きな混乱が生じるのは必至であり、物流を担う公共サービスの信頼性が問われる事態となっている。
不適切点呼問題、軽バンも処分対象に
日本郵便における運転手への点呼の不備が、さらに深刻な局面を迎えている。国土交通省は9月3日、日本郵便に対し、郵便物や宅配便の配送で主力となっている軽バンなど軽貨物車について、車両使用停止の行政処分案を通知する方針を固めた。これまでに同社の大型トラックやワンボックス車約2500台は、同様の問題で既に事業許可を取り消されている。今回の処分は、軽貨物車という日常の郵便配達を支える根幹部分にまで及ぶことから、物流への影響は避けられないとみられている。
国交省は行政手続法に基づき、日本郵便に弁明の機会を与えた上で、10月中にも正式に処分を下す見通しだ。関係者によると、まずは東京都や大阪府など都市部を中心とした約100局に通知を行い、その後も週100局程度のペースで処分対象を拡大。最終的には全国で約2000局に達する可能性が高いという(読売新聞などの報道による)。
全国調査で判明した「不適切点呼」
問題の発端は、運転手が業務に入る前に行うべき法定点呼の不備である。点呼では、飲酒の有無や体調確認を行い、輸送の安全を確保することが義務づけられている。しかし日本郵便が4月に公表した全国調査によると、全国3188の郵便局のうち75%にあたる2391局で不適切な点呼が行われていたことが判明した。この結果を受け、国交省は6月、大型トラックなどの一般貨物車両について事業許可を取り消した。さらに軽貨物車に関しても特別監査を実施し、全都道府県で違反が確認される見込みとなった。
行政処分の仕組みと「日車」制度
貨物自動車運送事業法では、点呼を怠った事業所には「車両使用停止」の行政処分が科される。停止期間は違反の重さによって異なり、対象台数も事業所の規模に応じて決まる。処分は「日車(にっしゃ)」と呼ばれる単位で示され、例えば「160日車」の場合、10台の車両を16日間、あるいは5台を32日間使用停止とする形で割り振られる。
今回の処分では、郵便局によっては100日を超える停止を受けるケースもあり、業務への打撃は甚大となる。法令上、営業所に所属する車両の半数以上を停止させることはできないが、それでも稼働台数が大幅に減ることは避けられない。
軽貨物車は郵便配達の「主力」
日本郵便は全国で約3万2000台の軽貨物車を保有しており、郵便物や小型荷物の集配を担う「主力戦力」となっている。同社のトラック便はすでに約58%を子会社や同業他社に委託しており、残りを軽貨物車で補ってきた。今回の処分によって軽貨物車の一部が使えなくなれば、委託比率をさらに増やさざるを得なくなる。
また、配達の現場ではすでに人員不足が課題となっており、使用停止による稼働台数の減少は、遅配やサービス低下を招く恐れがある。委託拡大は即効性のある対応策とされるが、コスト増が避けられず、同社の経営にも影響が及ぶとみられている。
原付きバイクでも不備が発覚
問題は軽貨物車だけにとどまらない。日本郵便の社内調査によると、全国で配達に使われている原動機付き自転車(約8万3000台)でも、3188局のうち6割弱にあたる1834局で点呼の不備があった。法令の適用外ではあるが、同社の管理体制全般に対する不信感を強める結果となっている。
国交省は6月25日には輸送の安全確保命令を出し、点呼体制の早急な改善を求めた。命令違反には最高100万円の罰金が科されるが、今回の処分対象は命令前の違反行為である。
日本郵便の対応と再発防止策
日本郵便は再発防止策として、点呼記録のデジタル化を全郵便局で進めている。また、本社には安全管理を統括する新部署を設置し、体制強化を急いでいると説明している。ただ、全国的に慢性的な人員不足が続く中で、制度の徹底がどこまで実効性を持つかは不透明だ。
一方、現場で不適切な点呼を行っていた職員や管理者の処分については、現時点で明確にされていない。国交省の監査や社会的な批判の高まりを受け、責任の所在をどう明らかにするのかが今後の焦点となる。
消費者生活への影響は避けられない
郵便は日常生活に欠かせない公共インフラであり、その混乱は消費者に直結する。宅配便や書類の到着が遅れるだけでなく、年末にかけて需要が増す時期にはさらなる影響が予想される。特に、地域によっては代替輸送網の確保が難しく、遅配やサービス低下が長期化する懸念もある。
また、委託拡大によるコスト増は、将来的に郵便料金やサービス体系の見直しにつながる可能性もある。公共サービスとしての役割を果たしつつ、企業経営を維持する難題に日本郵便は直面している。
信頼回復への道のり
今回の処分は、郵便事業に対する信頼を大きく揺るがすものだ。国交省による一連の監査は、日本郵便の安全管理体制が根本から問われていることを示している。物流業界全体でも人手不足や労務管理の課題が深刻化しており、郵便局の不適切点呼問題は業界全体の縮図ともいえる。
信頼回復には、徹底した再発防止策の実施とともに、利用者に対する誠実な情報公開が不可欠である。郵便事業は国民生活に直結するだけに、日本郵便がどこまで透明性を確保し、責任を果たせるかが注目される。