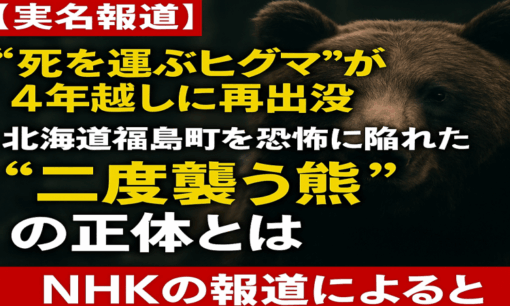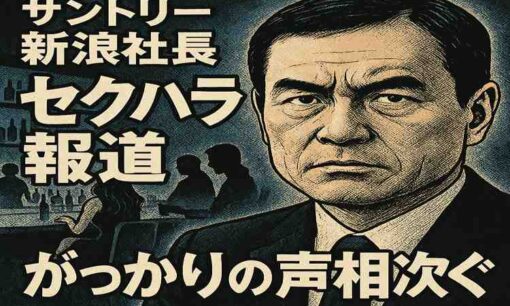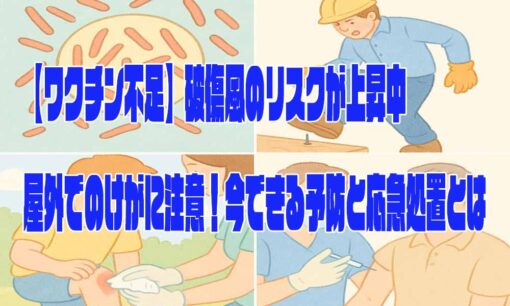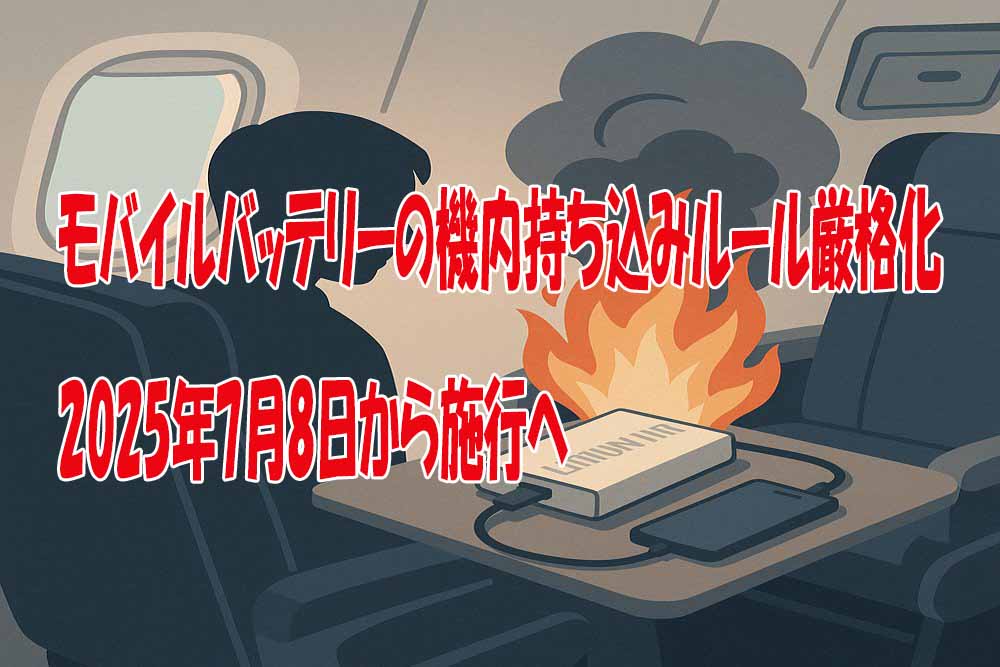
航空機内でのモバイルバッテリーの取り扱いを巡り、国土交通省と定期航空協会は2025年7月8日から新たなルールの運用を開始する。視界の届かない場所での保管を禁止し、使用時も常に状態を確認できることを求める内容で、相次ぐ発煙・発火事故を受けた安全対策の一環とされる。航空各社や利用者の対応が問われるなか、リチウムイオン電池のリスクと国際基準に即した管理の徹底が急務となっている。
発火事故を受けて国交省が新指針を策定
国土交通省と定期航空協会は、航空機内におけるモバイルバッテリーの取り扱いについて、新たなルールを2025年7月8日から適用すると発表した。ANA(全日本空輸)やJAL(日本航空)をはじめとする国内航空会社すべてが対象となる。
今回の措置は、近年増加傾向にあるバッテリー由来の発煙・発火事故を受け、安全対策を一層強化することが目的である。
【新ルールの概要】常に「見える場所」での保管と使用が原則に
新たな指針では、乗客が機内に持ち込むモバイルバッテリーについて、座席上の収納棚や他の手荷物の中など、視認できない場所に保管することを原則禁止とした。また、スマートフォンなどの電子機器への充電や、機内電源からモバイルバッテリー自体を充電する行為についても、使用者が常時確認できる位置で行うことが求められる。
航空各社は、保安要員による車内巡回や搭乗前のアナウンスなどを通じて、新ルールの周知を徹底する方針である。
【過去の事例】韓国・エアプサン機では座席が半焼
国土交通省によると、2025年1月に韓国のLCC「エアプサン」の機内でモバイルバッテリーが発火し、座席の一部が半焼する事故が発生した。幸い乗客に大きな被害はなかったが、バッテリーの異常加熱により煙が充満し、一時的な避難対応がとられたという。
このほかにも、国内外の航空会社で同様の事故が複数報告されており、特にリチウムイオン電池を内蔵した安価な製品で発火リスクが高い傾向がある。
【国際基準との整合性】ICAOのガイドラインに準拠
航空機内の安全性向上の観点から、国土交通省はこれまでも**国際民間航空機関(ICAO)**が定めるガイドラインに基づき、モバイルバッテリーの取り扱いを規制してきた。
現行の基準では、モバイルバッテリーの機内持ち込みは以下の通り制限されている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機内持ち込み | 可(容量に応じて制限あり) |
| 預け入れ荷物 | 禁止(安全基準による) |
| 容量制限 | 100Wh以下:制限なし/100Wh超~160Wh:事前申告が必要/160Wh超:持ち込み禁止 |
| 個数制限 | 一般的に2個まで(航空会社によって異なる) |
【中国の事例】「3C認証」取得製品でなければ持ち込み禁止
中国当局では、国内線において「3C認証(中国強制認証)」を取得していないモバイルバッテリーの機内持ち込みを禁止している。この認証制度は安全性・品質の基準を満たすことを求めるもので、基準に満たない製品は機内への持ち込み自体が認められない。
日本国内では同様の認証制度は導入されていないが、航空各社は「信頼性あるメーカー製品の使用」を乗客に呼びかけている。
【リチウムイオン電池のリスク】見えない「サーマルランアウェイ」
リチウムイオンバッテリーは、高出力・軽量という利点がある一方で、過充電・外部衝撃・製造不良といった要因で「サーマルランアウェイ(熱暴走)」を起こすことがある。これは、電池内の温度上昇が連鎖的に進行し、最終的には発煙・発火・爆発に至る現象である。
使用中にバッテリーの膨張・異臭・異常発熱などが確認された場合は、即座に使用を中止し、可能であれば機内乗務員へ申告することが望ましい。
【利用者に求められる姿勢】「安全は一人ひとりの意識から」
航空機内という閉鎖環境において、火災事故は重大なリスクとなる。国土交通省および航空各社は、制度面からの予防策を整備するとともに、乗客一人ひとりが正しい知識と使用方法を身につけることの重要性を強調している。
特に、廉価で規格外のモバイルバッテリーはリスクが高く、安全認証を得た製品を選ぶといった基本的な対応が、事故の未然防止につながる。