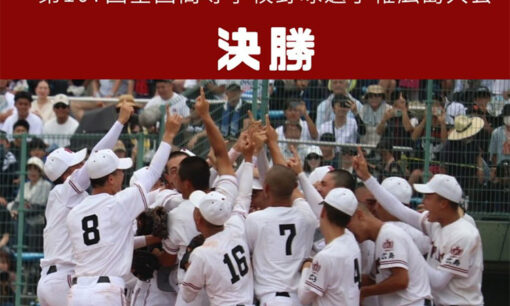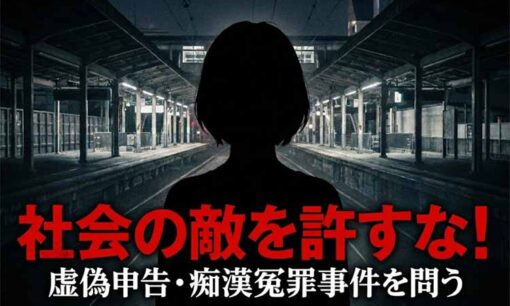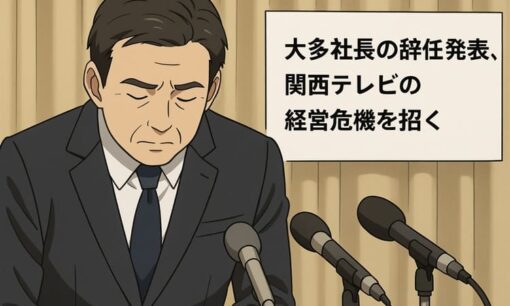デジタル機器が日常に溶け込む現代、子どもたちはスマートフォンやタブレット、テレビゲームと共に成長している。便利さの裏で見過ごされがちなのが、視力への影響や生活リズムの乱れといった健康面のリスクだ。近視の進行が低年齢化するなか、親として子どもにどのような環境と習慣を用意できるのか――。制限ではなく「使い方」に光を当てた、親子で実践できる新しい“デジタルとの向き合い方”を探る。
スマホ・タブレットが日常にある時代 問われるのは「使い方の工夫」
現代の子どもたちは、生まれたときからスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器が身の回りにある「デジタル・ネイティブ」として育っている。その利便性は教育・娯楽・コミュニケーションのあらゆる場面に及ぶが、一方で過剰な画面依存や視力低下、さらには姿勢や生活リズムの乱れが深刻化している。
新潟市の「はにゅうクリニック」副院長・羽入貴子医師は、NST新潟総合テレビの取材に対し、「近視の発症年齢が下がっており、放置すれば将来的に網膜剥離などの重大な目の病気につながる可能性がある」と警鐘を鳴らした。
しかし、現実として、スマホやテレビ、ゲームと完全に離れることは困難である以上、「上手に付き合う」知恵と生活設計が求められている。
「視覚」だけに偏らせない 五感を育てる活動の導入を
画面を長時間見る生活では、視覚に負担がかかるだけでなく、他の感覚の発達にも偏りが生じやすい。そこで今、家庭や学校において「視覚以外の感覚を使う活動」を日常に取り入れることが有効とされる。
例えば、粘土や折り紙などの手仕事、料理や野外遊び、木工、音楽といった活動は、触覚や聴覚、身体全体の運動感覚を刺激する。こうした時間は、近視予防の観点からも、視線を近くに固定しないで済むという利点がある。
ブルーライト対策と「夜間モード」の活用も
機器側の設定を工夫することでも、目の疲労や睡眠への影響を軽減できる。代表的なのはブルーライトのカット機能や、画面を暖色系に変える「ナイトモード」の活用である。特に夜間は、ブルーライトの刺激が体内時計を狂わせるとされ、就寝前の画面使用は極力避けるか、短時間にとどめる工夫が望ましい。
画面の明るさもまた、周囲の照明に応じて調整する必要がある。暗い部屋で過度に明るい画面を見ることは、網膜への刺激が強すぎるため避けたい。
視線の高さと姿勢 家庭の中に「整った環境」を
意外と見落とされがちなのが、デバイスを見るときの姿勢や視線の位置である。画面は目線よりやや下に置くのが理想とされ、うつむきすぎないよう机や椅子の高さを調整する必要がある。背中が丸まりすぎると姿勢の悪化を招き、成長期の身体全体に影響が及ぶ。
また、使用時間を「30分を目安に一度立ち上がる」など身体を動かす習慣をつけることで、視力にも集中力にも良い効果がある。
「一緒に使う」「使い方を話す」 親子での対話とルールづくりを
スマートフォンやゲームとの付き合いは、「禁止」よりも「共有」へと発想を切り替えることが、長い目で見た時の健全なメディアリテラシー育成につながる。親が子どもと一緒にゲームをする、YouTubeの動画を一緒に観て感想を話すといった行動を通して、単なる“使用”から“対話のきっかけ”へと転換することができる。
そうした時間を通じて、親が無理なく利用内容や時間を把握し、子ども自身にも「使い方を選ぶ力」が育っていく。
「自分で管理する」力を育てる ホワイトボードや時間記録のすすめ
高学年の子どもであれば、「自分で時間を決めて使う」体験を意識的に作ることも有効である。たとえば、「今日は何分使うか」「終わったあと、どんな気持ちだったか」を紙やホワイトボードに記録するだけでも、日々の使用に“振り返り”という視点が加わる。
これは単なる視力対策ではなく、デジタル時代を生きる子どもたちが「自分と道具との距離感を持つ」ための教育でもある。
親子の協力が子どもの目を守る “制限”ではなく“調整”へ
近視の進行を防ぐには、距離・時間・光の3要素に加え、「生活全体の調和」が何よりも重要である。スマートフォンやゲームそのものを悪者にするのではなく、どう使えば健康な生活の一部として組み込めるのかを、家庭内で話し合いながら模索していくことが、これからの時代に求められる姿勢だ。
便利な道具とどう付き合うか。それは、子どもたちが大人になる過程で向き合うべきテーマであると同時に、大人自身が見つめ直すべき問いでもある。