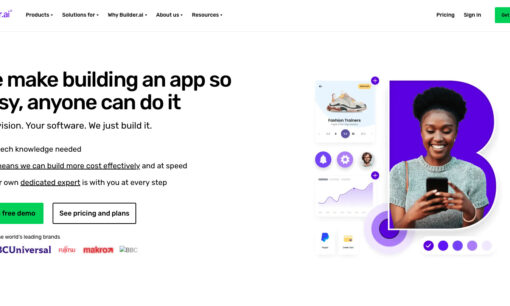日本の国民的アニメが、中国の過激な世論に飲み込まれた。2026年2月7日、共同通信などが報じたところによると、中国各地のアニメや漫画のイベントで名探偵コナンのコスプレや関連グッズの販売が相次いで禁止されている。
原因は、過去に中国で大炎上した僕のヒーローアカデミアとの記念コラボ企画だ。作品内容とは無関係にもかかわらず、ヒロアカの過去の炎上が蒸し返され、コナンまでが「中国を侮辱する作品」と同列に扱われる事態に発展した。娯楽作品が歴史認識とナショナリズムの渦に巻き込まれ、事実上の締め出しを受ける。中国市場における日本コンテンツの危うさが、改めて浮き彫りになっている。
記念コラボが引き金となった炎上の再燃
今回の騒動の発端は、名探偵コナンのテレビアニメ放送30周年と、ヒロアカのテレビアニメ放送10周年を記念した公式コラボ企画だった。互いの主人公を描いた記念イラストなどが公開され、ファン向けの祝賀的な内容として展開されていた。
しかし中国のSNS、特にWeiboでは、ヒロアカの過去が再び問題視された。
ヒロアカは2020年、登場人物名「志賀丸太」が旧日本軍731部隊で使われた被験者呼称「マルタ」を連想させるとして、「中国を侮辱する作品」と強く批判され、動画配信プラットフォームから削除された経緯がある。
この過去の炎上が今回のコラボと結び付けられ、「ヒロアカと関わったコナンも同罪」という論調が拡散した。コナン自体の内容や表現は検証されないまま、過去のレッテルだけが独り歩きし、炎上は一気に拡大した。
中国各地で相次ぐイベント主催者の自主規制
炎上は現実の規制として表面化した。甘粛省蘭州で開催予定だったイベントでは2月5日、主催者が声明を発表し、コナンとヒロアカ関連のコスプレ入場を禁止し、グッズの販売や展示も認めないと明言した。
声明には「中国人民の感情を害する歴史問題が関わっている」と記され、和服やげた、軍国主義を連想させる衣装も禁止対象に含まれた。
北京で7日から8日にかけて開催された北京国際動漫遊戲狂歓節などでも、開催直前に注意事項が追加され、両作品に関するコスプレやグッズの持ち込み禁止が告知された。こうした動きは他の都市にも広がりつつある。
中国政府による公式な全国禁止令ではないものの、主催者がネット世論の反発を恐れて規制を強化する構図が定着しつつあり、実態としては事実上の締め出しに近い。
ヒロアカ過去炎上が示す中国市場の不安定さ
ヒロアカの過去炎上は、中国市場における日本コンテンツの立場の不安定さを象徴している。731部隊という歴史的トラウマは極めて敏感なテーマであり、創作上の意図や偶然はほとんど考慮されない。
一度「侮辱」と認定されれば、その影響は長期間にわたって残り続ける。
今回のケースでは、コナン自体に問題視される表現は存在しない。それでも「問題作とコラボした」という一点だけで、同列に扱われた。中国メディアの瀟湘晨報などは、このコラボを「歴史の傷を無視したもの」と批判し、政府系メディアも慎重ながら否定的な論調を示している。
作品の中身よりも政治的文脈と感情が優先される現実が、今回の騒動で改めて露わになった。
中国SNSで噴き上がる過激なナショナリズム
中国のSNSでは、イベント主催者が掲げた「歴史を尊重し、レッドラインを堅守する」という表現が合言葉のように消費され、ナショナリズム的なコメントが殺到している。
「支持する」「良くやった」「レッドラインに挑戦する行為は許されない」といった賛同の声に加え、「コナンは好きだったが原則の問題だ」「中国で金を稼いでいるのに侮辱するのか」と、ファンを名乗りながら断罪する投稿も目立つ。
さらに「ボイコットだ」「全面撤去せよ」「今後は二次元を厳しく管理すべき」と、文化全体を管理対象とする主張も拡散した。
ここではもはや作品批評ではなく、政治的忠誠心を競う言説が娯楽を押し潰している。
日本側の冷笑と突きつけられた現実
一方、日本側のXでは、中国側の過熱ぶりとは対照的に、冷笑と諦観が支配的だ。
「またか」「いつものこと」「相手にするだけ無駄」といった反応が多く、炎上自体を深刻に受け止めない空気が広がっている。
「過剰反応」「こじつけ」「表現の自由がない国」といった言葉が並び、中国側の論理を理解しようとする姿勢はほとんど見られない。同時に、「中国市場依存の危険性がまた証明された」「政治リスクが高すぎる」といった現実的な指摘も増えている。
一夜にして作品が問題作に転落し、イベントから排除される市場に、どこまで依存するべきなのか。創作やビジネスの観点からも、中国市場との距離感を見直すべきだという声が静かに、しかし確実に広がっている。
コナン側の中国代理店である上海キャラクターライセンス行政公司は、「コラボに政治的意図はない」と声明を出したが、炎上は沈静化していない。今回の騒動は、文化交流がナショナリズムの前ではいかに脆いかを、改めて突きつけた。