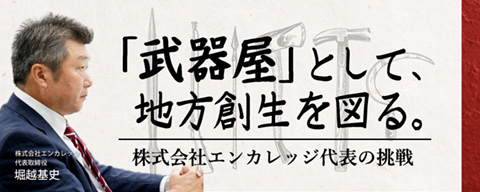全国学力テストで一部教科の平均正答率が低下し、文部科学省は「探究・グループワーク」偏重など運用課題の是正を促した。だが基礎固めの外部化を学習塾に頼るには、年間で公立約16万円・私立約36.6万円(支出世帯平均)という家計の壁もある。
基礎の遅れをどう埋めるか――本稿は塾費の実態を踏まえ、主要学習アプリの料金と機能、家庭での運用手順を整理し、「基礎→応用」へと学びを再設計する現実的な道筋を示す。
文部科学省が“学力低下”を公表。「応用・協働型」授業偏重への懸念も
文部科学省と国立教育政策研究所は、令和7年度(2025年度)の全国学力・学習状況調査の結果を段階的に公表した。小中の国語・算数(数学)で平均正答率が前年度より下がった教科があり、結果の分析と改善サイクルの確立が課題と整理された。
また、文部科学省のワーキング資料では、「総合的な学習(探究)の時間」における運用上の課題――グループ探究の形式先行、児童生徒の興味・関心の反映不足、各教科との連携の弱さ――が指摘され、基礎の系統学習とのバランスを問い直す必要が示された。
こうした状況を背景に、東洋経済オンラインによると「小学校での探究やグループワークの増加が、基礎学力の伸び悩みと関係するのではないか」という論点が浮上している。ただし因果を直ちに断定できないとの見方も併記され、授業設計と評価の見直しが要るとされた。
具体策である「学習塾」は…家計インパクト“大”
小学生の学習塾費(“支出した世帯”の年間平均):公立 約16.0万円/私立 約36.6万円
家計負担を一次統計で確認する。文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」によれば、小学生の学習塾費(“支出した世帯”の年間平均)は公立で約16.0万円、私立で約36.6万円である。単純月割では公立で約1.3万円、私立で約3.0万円に相当する(学年・地域・科目数等で変動)。
民間の概況調査(Ameba塾探し ほか)では小学生の塾の月額平均を約1.9万円とする推計もあるが、一次統計ではない点には留意が必要だ。
物価高の下、外部サービスに基礎固めを“外部化”しにくい世帯も少なくない。ソニー生命の家計調査でも、学校外教育費の月次支出は小学生で平均水準が示され、家計余力に応じて学習機会の差が生じやすい現実がうかがえる。結果として、学校・家庭・地域それぞれでの“基礎の下支え”の設計が問われている。
“基礎の自走化”を家庭に――主要学習アプリの「現在と費用」
学校での探究・協働を活かすには、家庭で基礎反復の自走化を図ることが要になる。近年の主要アプリは、無学年学習、到達度診断、自動採点、復習キュー、保護者ダッシュボードなどを備え、短時間×高頻度の積み上げを設計しやすい。
- スタディサプリ(小学):月額目安 2,178円。要点講義+演習、教科書準拠、進捗管理を提供。
- 進研ゼミ(チャレンジ/チャレンジタッチ):学年・支払い方法により月3,000円台〜7,000円台。紙・タブレット両対応。
- スマイルゼミ(小学生):標準クラス月3,278円〜(支払い条件・学年で変動)+専用タブレット代10,978円。
- すらら:対話型レクチャー+無学年学習。月1万円台前半が中心。
- RISU算数:年額基本料35,376円+進度連動の従量課金。先取りに強いが料金体系の理解が必要。
注:アプリの機能・価格・料金体系は変更される場合があります。最新の公式情報をご確認ください。
運用のコツ(家庭での実装案)
- 毎日10〜20分の固定スロット(就寝前/帰宅直後など)を家族で合意する。
- 音読・計算・語彙を“日課化”し、説明させる課題(口頭要約や短文記述)を週に数回挿入する。
- 週1回、アプリのダッシュボードで到達度と取りこぼしを親子で確認し、翌週の配分を微調整する。
※毎日新聞によると記述式で理由まで書く課題の正答率が低い設問が見られた。家庭で「説明する練習」を取り入れる意義は大きい。
“基礎→応用”の順序を社会で再設計する時期
基礎の定着は、学校だけでも家庭だけでも完結しない。全国学力調査が映すのは、授業内の設計変化と、家庭の外部化(塾・アプリ)による格差の複合問題である。現実的な解は、学校=系統学習の主導/家庭=基礎反復の自走化/地域=学び直しのセーフティネットという役割分担を、行政・学校・企業・家庭の協働で具体化することだ。
応用・協働の学びは重要だが、それは確かな基礎の上にこそ大きく伸びる。基礎を“面”で支える設計に舵を戻せるか――それが次回以降の学力の底上げを左右し、ひいては日本の学びの底力を測る物差しになる。