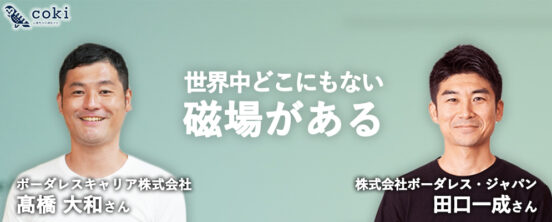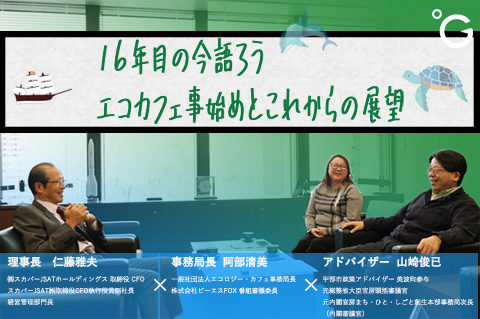戦時中の水没事故で183人が犠牲となった山口県宇部市の長生炭鉱。封印された歴史は市民団体の活動で再び掘り起こされ、2025年8月には人骨も発見された。しかし県は「独自支援せず」と答弁し、国の対応も「検討」にとどまっている。
長生炭鉱とは
長生炭鉱は1914年に山口県宇部市で開鉱された海底炭鉱である。宇部炭田の中でも規模が大きく、最盛期には年間15万トンの石炭を産出した。
戦時中、日本は石油の輸入が途絶え、石炭が主要エネルギー源となった。その結果、「石炭の一塊は血の一滴」と呼ばれるほど増産が強いられた。労働者の多くは朝鮮半島から連れてこられた人々で、長生炭鉱ではその割合が7割を超えたとされる。
しかし海底炭鉱は常に危険と隣り合わせだった。天井からの浸水や落盤は日常茶飯事で、最も危険な場所に送られたのは、朝鮮半島出身の労働者たちだった。
1942年2月の水没事故
1942年2月3日午前9時ごろ、ついに惨事は起きた。坑道の天井が崩れ落ち、海水が一気に流れ込んだ。労働者183人、日本人47人、朝鮮半島出身者136人が水に呑み込まれた。生き残ったのはわずか十数人にすぎない。
事故直後、坑口は「市街地が水没する」との理由で急きょ閉鎖され、遺骨は炭鉱内に取り残されたままとなった。以後、長生炭鉱は「戦時下最大級の炭鉱事故」として歴史に刻まれ、植民地支配や強制労働の象徴とされることになった。現在も海岸には排気塔「ピーヤ」が突き出し、犠牲者の墓標のように海を見つめている。
封印された歴史と市民団体の活動
事故後、長生炭鉱の悲劇は長らく封印されてきた。しかし「忘れてはならない」という思いから1991年、地元市民が「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会(刻む会)」を発足。遺骨返還を目指し、遺族や関係者を招いた追悼集会を毎年開いてきた。2013年には犠牲者183人全員の名前を刻んだ追悼碑を建立。
市民団体は長年、坑口の所在を探し続け、2024年9月、ついに坑口を掘り起こすことに成功した。調査の結果、坑道内部は崩落しており、直接の探索は困難だと判明。しかし、沖合に残る排気塔「ピーヤ」からの調査に希望をつないだ。
2025年8月、人骨の発見
2025年8月、ついに歴史が動いた。日本人ダイバーと韓国人ダイバーが協力して行った潜水調査で、海底から黒く染まった大腿骨や上腕骨、頭蓋骨などが回収されたのである。
長年「鳥の骨ではないか」と疑われてきた発見の数々に比べ、今回の骨は明らかに人のものだった。現場ではその場で法要も営まれ、報道陣や支援者の間からは歓声が上がった。
この調査は日本と韓国のダイバーや研究者が連携して進める共同プロジェクトであり、人骨発見はその協働の成果でもあった。収集された骨は現在、山口県警が保管しているが、DNA鑑定に進むには遺族の対照試料が必要である。特に犠牲者の7割近くが朝鮮半島出身者であるため、韓国側の協力が不可欠とされている。
県は「独自支援なし」と答弁
こうした中、9月26日の山口県議会で県の姿勢が問われた。県観光スポーツ文化部の木安亜紀江部長は「遺骨の収容や返還は国の責任であり、独自に支援することは考えていない」と答弁。さらに、知事の現地視察や国への要請の予定も「ない」と明言した。
傍聴していた井上洋子共同代表は「後退している」と失望を隠さなかった。「遺骨が見つかっているのに、県が国に要望に行かないというのは納得できない」と語った。
国の対応も「検討」にとどまる
一方、国の動きも鈍い。9月18日、刻む会と専門家が厚労省と交渉し、安全確認のためのボーリング調査や鉄管撤去、新しい縦穴の掘削を要請した。しかし担当者の答えは「持ち帰って検討する」にとどまった。
さらに8月28日、林芳正官房長官は「安全性を確保した上での潜水調査に資する新たな知見は得られていない」と述べ、民間団体への財政支援に慎重姿勢を崩さなかった。遺骨の身元確認も「県警が関係省庁と協力して対応する」とするにとどまった。
必要な段取り 安全評価から国際協調へ
遺骨返還を実現するには、次の段階が必要である。
- 安全性評価:ボーリング調査で地盤を確認する。
- アクセス確保:ピーヤ内部の鉄管撤去や坑道補強。
- 追加収容:ROV(無人探査機)や潜水で遺骨を収容する。
- DNA鑑定:日本と韓国双方の遺族から試料を集め、国際協調で進める。
市民団体はクラウドファンディングで資金を集めてきたが、戦時下の国策による人災である以上、国が責任を持つべきだという声は強い。
それでも灯は消えない
国や県の対応が足踏みを続ける一方で、現場の祈りは途絶えない。9月25日には坑口前に183本のキャンドルが灯され、犠牲者の名とともに鎮魂の光が並んだ。揺れる炎は、遺骨を必ず故郷へ返すという誓いの象徴でもある。行政の決断が追いつかなくとも、その願いは消えることはない。