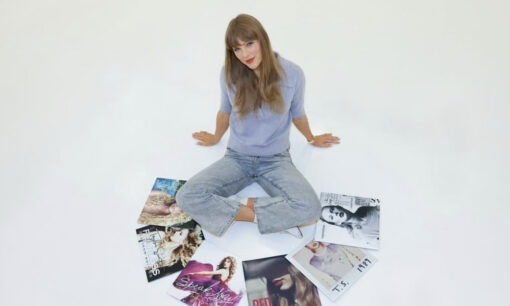大阪市の住宅街。介護ベッドの上で、58歳の女性はわずかに身じろぎをするだけで顔をゆがめる。背骨のゆがみと全身の痛みが日々を縛り、ほとんど寝たきりの生活。身体障害者手帳は最重度の1級認定を受けている。それにもかかわらず、国からの障害基礎年金は“不支給”。理由は「疼痛(痛み)は原則、対象外」という制度の壁だった。女性は「体が動かせないのに、不合理で納得できない」と訴える。制度と現実の溝が浮き彫りになっている。
寝たきり女性に届かなかった年金
女性が体調を崩したのは2022年、新型コロナ感染がきっかけだった。後遺症で体力は急激に落ち、転倒を繰り返した。翌年には呼吸苦と全身の痛みで救急搬送。医師から「脊椎後彎」と診断され、食事も取れず体重は20キロ以上減少した。
入院の末、身体障害者手帳1級に認定され車いす生活となり、今年3月に障害基礎年金を申請。しかし、日本年金機構から届いた通知は「不支給」。理由の一つが「痛みは原則、対象外」という規定だった。
障害者手帳と障害年金はなぜ違う?
「手帳1級なのに年金がもらえないのはおかしい」
多くの人が抱く疑問だろう。だが、障害者手帳と障害年金は制度の目的も基準も異なる。
- 障害者手帳:日常生活の不自由さを基準にし、福祉サービスや交通割引などにつながる。
- 障害年金:働く能力や日常生活能力を基準にし、保険料納付状況も厳格に審査される。
つまり、手帳の等級と年金の等級は連動しない。最重度の手帳を持っていても、年金は不支給になることがある。
「痛みは対象外」という現実
障害年金の認定基準には「疼痛は原則として対象外」と明記されている。痛みは本人しか感じ取れず、客観的な指標で評価するのが難しいからだ。
ただし例外もある。神経損傷による慢性の激痛や、悪性腫瘍に伴う疼痛などは、他覚所見や就労制限と組み合わせて評価されるケースもある。つまり、医師の診断書で「痛みにより常時介助が必要」「就労不能」と具体的に記載されなければ、支給判断に結びつきにくいのだ。
生活保護との関係 併給はできるのか?
では、「障害年金と生活保護の関係」はどうなのだろうか。結論から言えば、併給は可能だ。ただし障害年金は収入として認定されるため、その分生活保護費は減額される。生活保護は“最後のセーフティネット”であるため、他の制度による給付が優先される仕組みになっている。
制度見直しは進むのか?
近年、不支給事案の増加に批判が集まり、厚生労働省と日本年金機構は審査の透明性を高める見直しを進めている。2025年9月には「不支給等事案の点検作業の進捗状況」が公表され、精神障害で不支給とされた一部が支給に変更された。
改正のポイントは、①審査書類に客観的事実を丁寧に記載する、②不支給理由を詳細に説明する、③複数の認定医で審査する、といった透明性の向上だ。こうした改革が「痛み」を抱える人の救済につながるかは、今後の焦点となる。
不服申立てという選択肢
もし不支給に納得できなければ、不服申立てが可能だ。社会保険審査官や社会保険審査会に申し立てを行い、診断書の追記や生活実態の証明を積み重ねることで、結果が覆ることもある。今回の女性のケースも、再申請や不服申立てによって救済される可能性は残されている。
「痛み」をどう支えるか
女性は「動けないのに“対象外”とは理不尽」と声を絞り出す。制度は客観性を重んじるが、現実の生活には数字や診断名では測れない苦しみがある。
障害年金と生活保護、障害者手帳、複雑な制度のはざまで取り残される人をどう支えるのか。今回の事例は、制度の在り方を私たちに問いかけている。