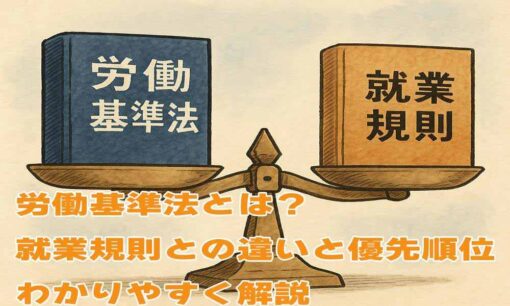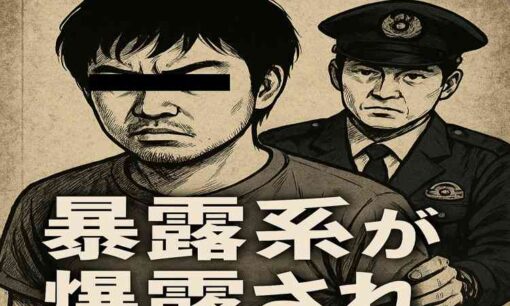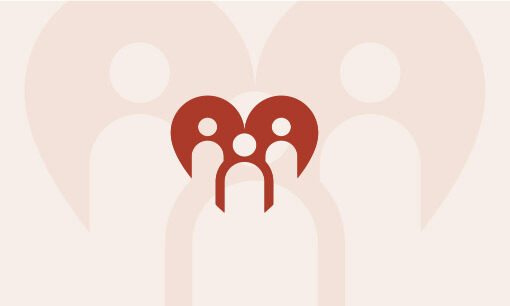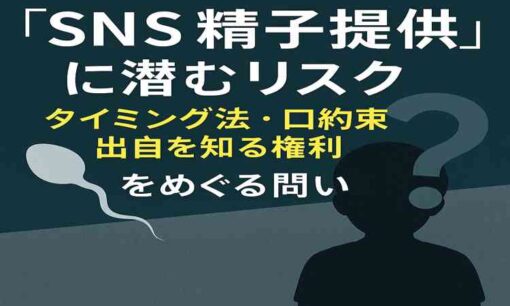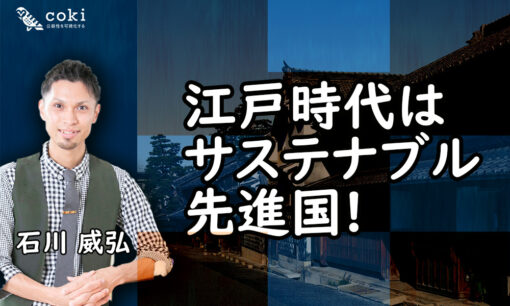社員200人中30〜40人に退職勧奨。レイオフの背景にある“合理性”は?“日本型雇用”の限界か

飲食業界向けに業務効率化サービスを展開する株式会社ダイニー(本社:東京都港区、代表取締役CEO 山田真央)は、2025年6月末時点で在籍していた全社員約200人のうち、2割にあたる約30〜40人を対象に退職勧奨を実施していたことがわかった。
対象となったのは営業職を除くエンジニアおよびコーポレート部門で、生成AIの進展を背景に、企業としての生産性構造を抜本的に見直すことが狙いとされる。
売上は2倍、店舗数も急増中 経営不振ではない
人員削減の発表に対し、一部では「資金難ではないか」との憶測も流れたが、山田氏はこれを明確に否定する。「事業は極めて順調。売上は前年比で2倍に、導入店舗数はこの1年で1万1000店に到達した」と述べ、むしろ成長の只中でこそ、構造的変革が必要だったと強調した。
それでもリストラに踏み切った理由 生成AIと“組織の再定義”
ダイニーでは2024年末ごろからAIを全社的に導入し、議事録作成やカスタマーサポート、営業資料の作成など、各業務におけるAI活用を急速に進めてきた。その結果、社内においても「AIで代替できる業務」が浮き彫りになりつつあり、成長フェーズにおける“リソース構成の歪み”が顕在化していたという。
山田氏は「いまの時代、人を増やして成長するという経営はすでに合理性を失いつつある。生産性を基軸とした経営こそが、次の時代のスタンダード」と語る。
日本企業は“レイオフできない”構造にある
今回の件で注目すべきは、「日本ではレイオフが極めて困難である」という制度的課題だ。
日本の労働法では、いわゆる「整理解雇の四要件」(人員削減の必要性、解雇回避努力、被解雇者の選定合理性、手続きの妥当性)が必要とされ、企業側が一方的に人員削減を進めることはきわめて難しい。そのため、ダイニーも欧米型の「レイオフ」ではなく、「退職勧奨」という合意形成型の対応を選ばざるを得なかった。
流動性のなさが日本企業を弱くする
だが、今この“解雇できない”構造こそが、日本企業の競争力を阻む最大の要因となっている。
生成AIの進化によって、業務が日々再定義される中で、旧態依然とした人材配置では迅速な適応ができない。欧米では数十人規模のスタートアップが数百億円の収益を上げている事例もある中、日本では非効率な販管費を抱えたまま、構造改革すらできずに競争に臨む企業が少なくない。
山田氏の決断は、こうした日本的雇用慣行の「限界」を浮き彫りにし、柔軟な人材戦略=アメリカ型モデルへの移行を日本企業全体に突きつけた格好だ。
感情労働としての「レイオフ通告」
山田氏は、自ら全ての対象社員に直接面談を行い、退職勧奨の意向を伝えた。「論理として正しいと確信していたが、人に伝える行為は想像以上に重かった」と語り、何度もSlackの履歴を見返しながら涙を流したと告白する。
「あなたの職務は、ここでは継続できない」――この一文を伝える際に、社員から返ってきたのは怒りではなく「社長の方がつらいのでは?」という気遣いだったという。
この経験を通じて山田氏は「経営者とは、合理の仮面を被った感情労働者だ」と語る。「だからこそ、痛みに慣れてはいけない。その痛みとともに、前へ進む」と強い言葉で締めくくった。
AI中心の組織へ 営業部門はむしろ拡大
今後の組織設計として、ダイニーはAIを中核に据え、人間がそれを補助する構造への転換を進めていく。営業職はその例外で、飲食業界特有の“人間同士の関係構築”が求められる場面では、AIの限界が明確であると判断。すでに営業の業務もAIによって効率化を進めており、一定の成果が見えてきた段階で、一気に採用アクセルを踏む予定だという。
エンジニアに関しては、AIと協働できる優秀な人材のみを厳選採用する方針を明言。AIネイティブ企業としての進化を加速させる。
東南アジア市場での優位性も視野に
海外展開についても、山田氏は「東南アジアでは今後、システム費用と人件費の逆転が起きる。その時こそチャンス」と語る。すでに日本市場で実績のあるプロダクトを、最小限のローカライズで現地展開する構想を描いており、ローカルプレーヤーとの競争にも自信を見せた。
AI時代の“日本型雇用の終わり”を告げる象徴
今回のダイニーのレイオフは、単なるスタートアップの合理化ではなく、日本型雇用制度の転換を象徴する出来事でもある。
山田氏の「痛みをともなう決断」は、日本の雇用慣行に対する静かな反旗であり、同時に新しい資本効率経営への一石となるだろう。
この変化に向き合えなければ、日本企業はグローバル市場で生き残ることすら難しくなる──そうした現実を、今回の決断は静かに、しかし確かに突きつけている。