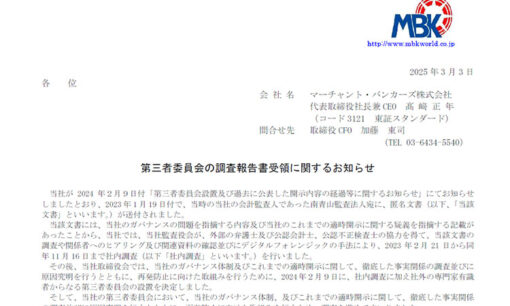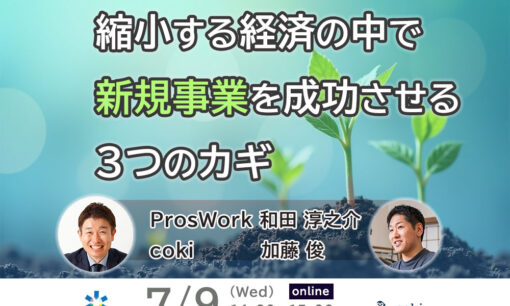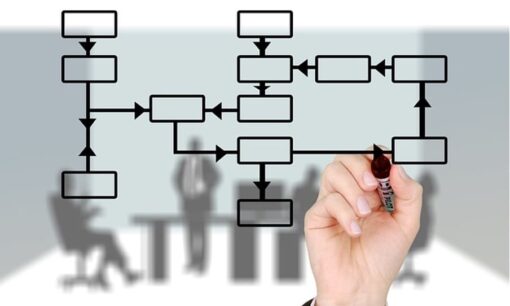日本列島を覆う異常気象が、コメづくりに深刻な影響を及ぼしている。出穂期を迎えた全国の産地では、猛暑と渇水が稲作を直撃。ダムの取水制限、田んぼの干上がり、水を運ぶ農家たち。
かつて「水さえあれば」と信じられてきた稲作の常識が、気候変動によって音を立てて崩れ始めている。
記録的猛暑と渇水が揺るがす日本のコメづくり
「ここまでの暑さと雨のなさは初めてかもしれない」。
そんな声が、日本の米どころ各地から聞こえてくる。2025年の夏、日本列島を覆う記録的な猛暑と少雨が、再び稲作農家を追い詰めている。
かつて「水さえあれば米はできる」と信じられていたが、その前提がいま、大きく揺らいでいる。
全国に広がる「水をめぐる稲作危機」
日本各地の主要産地で、深刻な水不足が発生している。出穂期を前に川や用水路が干上がり、農家たちはトラックやミキサー車を使って水を田んぼに運ぶなど、異常事態への対応に追われている。ある地域では「まだ枯れていないから助けたい」「雨が降らなければどうにもならない」といった切実な声が上がる。
また、各地のダムでは貯水率が例年の半分以下にまで落ち込み、取水制限や断水措置が取られている。ある地域では、7月下旬から10日間の農業用水の断水を実施。他の地域では、農業用水の使用量を半分に制限し、出穂から登熟にかけての時期をなんとか乗り切ろうとする努力が続いている。
田んぼだけでなく、畑や果樹などにも水を供給している地域では、畑作物への影響も懸念されており、「収穫できても価格が読めない」「今後が見通せない」という不安の声もある。
稲は暑さに強くない。気候変動で変わる常識
一般に、稲は高温に強いと思われがちだが、それは誤解である。とくに日本の主力品種であるジャポニカ米は、25~30℃の適温を超えると光合成の効率が落ち、35℃を超えると登熟不良や乳白米の原因になる。
また、出穂期から登熟期にかけては、昼夜の寒暖差と十分な水が必要不可欠だが、近年は夜間も気温が下がらず、熱帯夜が続くことで稲にストレスが蓄積している。そこに水不足が加われば、品質・収量ともに大きな打撃を受ける。
「水さえあれば」は過去の話に
農水省は備蓄米の放出も視野に入れ、現場の把握に努めるとする。一方で、農家や市場関係者からは「2025年の新米価格は予測がつかない」「一部ブランド米は高止まりする可能性がある」といった声も出ている。
今後、全国的な減収や品質低下が広がれば、コメの市場価格が上昇に転じる可能性は高い。とくに、猛暑の影響を受けやすい一部の産地や銘柄では、需給のひっ迫から高騰するケースも想定される。
すでに流通現場では「入荷量が読めない」「仕入れ価格が上がり始めている」といった動きも出ており、消費者の食卓に届く新米が高嶺の花になるリスクも現実味を帯びてきた。
コメは日本の主食であると同時に、文化でもある。だが、いまや猛暑と渇水がその基盤を揺るがしている。雨頼みの稲作は限界を迎えている。水資源の再設計と、気候変動を前提とした農業政策が、急がれている。