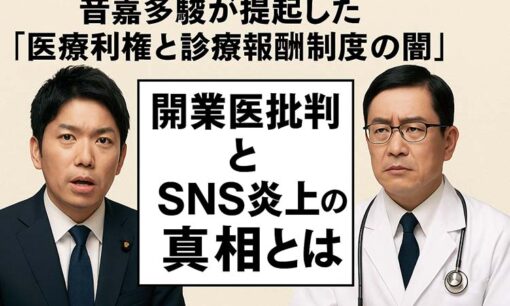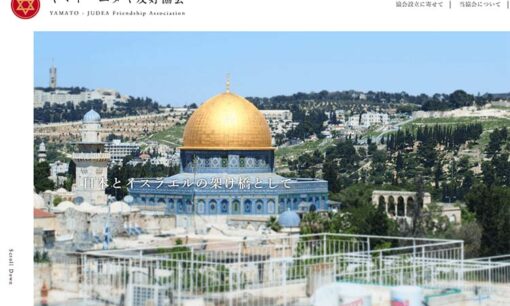2025年7月21日午前2時半現在、「日本人ファースト」をスローガンに掲げた参政党が第27回参議院選挙において12議席を獲得し、参議院において単独で法案提出が可能となる11議席を突破した。
公示前の1議席から飛躍的に勢力を拡大し、参政党は政界の勢力図を塗り替える存在となりつつある。
神谷宗幣代表は20日夜のテレビ出演で「グローバリズムへのアンチテーゼとしての減税、積極財政、日本人の生活防衛に本気で取り組む」と語り、有権者の期待に応える姿勢を強調した。また、「外国人差別」との批判を受けた「日本人ファースト」の表現については、「叩くためのレッテル貼りだ」と反論した。
参政党は外国人労働者や観光客の増加が引き起こす社会不安、物価高への不満を背景に、保守層を中心に幅広い支持を集めた。特に東京や茨城など複数区での議席確保が目立ち、国政における存在感を急速に強めている。
今後注目されるのは、神谷氏が公約に掲げた「スパイ防止法」の行方である。
スパイ防止法:40年ぶりの再浮上
スパイ防止法は1985年、自民党が提出したが、当時は「国家秘密」の定義が曖昧で、言論・報道の自由を侵害する恐れがあるとして廃案に追い込まれた経緯がある。死刑を含む重罰、秘密指定の恣意性、予備・陰謀罪の導入などが強く批判された。
だが今、自民党内でも再びこの法案が注目されている。経済安全保障を担当した高市早苗氏は、「スパイ交換」や「経済インフラの防衛」を理由に法整備の必要性を主張。調査会ではテロ対策やローンオフェンダー(単独犯)の取り締まりも視野に入れる構想が検討されている。
さらに、日本維新の会や国民民主党からも賛同の声が上がり、立法化に向けた機運は高まりつつある。
賛成論:スパイ天国・日本からの脱却
スパイ防止法を求める声の背景には、「日本はスパイ天国」と揶揄される現状がある。先進国の中で、日本にはスパイ行為を直接取り締まる包括的な法制度が存在せず、外国情報機関による工作活動が野放しになっているとの指摘は根強い。
安全保障関係者の間では、中国、ロシア、北朝鮮などの工作員が学術界や経済界、地方行政、通信インフラなどの領域で長期にわたり活動していると見られており、近年では宇宙・半導体・量子技術など先端分野に関する情報流出が懸念されている。
2023年にはアステラス製薬の日本人社員が中国でスパイ行為の疑いで実刑判決を受けた一方、日本側では相互の「スパイ交換」すら不可能な法制度に留まっている。
「自民党がアメリカの民主党化」の裏に極左の浸透工作?
また、日本では外国人による土地購入や企業買収、大学・研究機関への資金提供などを通じた「静かな浸透(サイレント・インベージョン)」が進行しており、国家の重要情報が知らぬ間に流出している危機感が広がっている。賛成派はこうした現状を「無防備すぎる」と批判し、「スパイ防止法は主権国家として最低限の自衛策だ」と強調する。
参政党の神谷宗幣代表も街頭演説で、次のように訴えている。
「自民党がもうアメリカの民主党みたいになっているんですよ。だから全然自民党がトランプ政権とうまくいかないでしょ。関税交渉もいかないでしょ。それは官僚ですよ。官僚、公務員。そういった極左の考え方を持った人たちが浸透工作で社会の中枢にがっぷり入っていると思うんですよ、ね。これをね、洗い出して、ね、極端な思想の人たちは辞めてもらわないといけないと思います、私は。これをね、洗い出すのがスパイ防止法です」
この発言は単なる対外的なスパイ対策にとどまらず、国内行政や制度の内部における「思想工作」への警戒心をも含んでおり、政官の関係、国家主権、官僚制の透明性といった広範な課題と結びつけた構図を描いている。
高市氏も「他国のようにスパイ行為を抑止できなければ、日本人が海外で不当に拘束された際に対等な交渉材料が持てない」と指摘。スパイ防止法は単なる防諜手段ではなく、外交・安全保障の基盤強化と見る立場である。
法案には特定秘密保護法や重要経済安保情報保護法といった既存制度の限界を補完する役割が期待されており、実務面でも警察・公安・内閣情報調査室といった機関の連携強化が課題とされている。
反対論:人権と報道の危機
一方で、スパイ防止法には根強い懸念も存在する。日本弁護士連合会は「国家秘密」の定義が広範・無限定であることを問題視し、「報道機関の取材、一般市民の日常行為すら処罰対象となりうる」と警告する。
同会の声明では、「知る権利」が侵され、民主主義の基盤が揺らぐと指摘。行為の曖昧さと重罰主義の組み合わせにより、政治批判や市民運動への委縮効果が生じる可能性も指摘された。
また、1980年代に旧統一教会系団体がスパイ防止法制定を主張していた経緯もあり、政教分離や信教の自由との整合性も問われている。
今後の焦点:参政党の真価が問われる
参政党は自民党との連携について「現段階では考えていない」としつつも、政策連携の可能性を示唆。神谷氏は「減税・積極財政・外国人政策に共感する勢力と組みたい」と語り、与党との距離を慎重に測る姿勢を見せた。
今後、スパイ防止法をはじめとした国家安全保障関連法案の行方は、参政党の立法能力と世論との対話力に大きく左右される。景気・外交・人権といった複雑な争点が交錯するなか、同党がどのような形で議会内外で信頼を築けるかが、その「一過性の旋風」か「新たな政治勢力」かの分水嶺となるだろう。