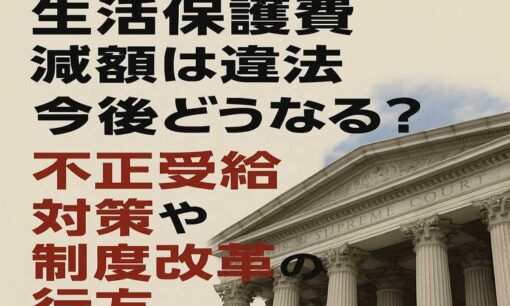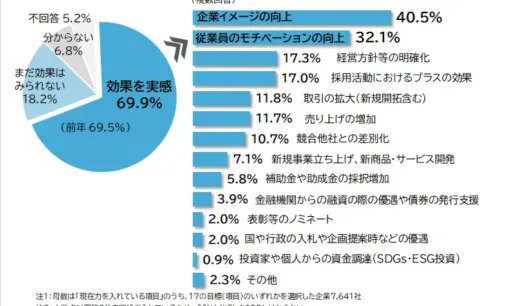木工の「隠す」常識を打ち破り、金継ぎの「見せる」色香をまとう。100年超の歴史を誇る材木屋が放つ新作は、動く素材である木と漆を融合させた。技術的タブーを越え、日本の精神性を世界へ問う新たなサステナビリティの形とは。
「隠す」のが美徳の木工界で、あえて「傷」を黄金に輝かせる逆転の発想
大正6年創業。愛知県岡崎市で100年以上の時を刻んできた老舗、岡崎製材がいま、業界の度肝を抜く挑戦に打って出た。2026年3月の「JAPAN SHOP 2026」でベールを脱ぐ新作「LOG-ing® Kintsugi edition」だ。
この家具、ただの高級品ではない。日本の木工職人が血にじむ努力で守ってきた「隠す美学」——つまり、木の割れや節をいかに目立たせずに仕上げるかという常識を、真っ向から否定しているのだ。
そこに施されたのは、陶磁器の修復技法として知られる「金継ぎ」。本来なら隠すべきはずの木の亀裂を、漆と金粉で堂々と装飾し、唯一無二の「物語」へと昇華させている。静寂の中に熱量を秘めたその佇まいは、まるで傷跡さえも誇りとする老兵のような、凄みのある美しさを放っている。
「木と漆は相性が悪い」……業界のタブーを覆した職人の意地
だが、この美しい融合には、解決不能と言われた高い壁があった。 「木は動く、漆は動かない」 これが、木製家具への金継ぎがこれまで敬遠されてきた最大の理由だ。
木材は生きている。湿気や温度で膨張し、収縮を繰り返す「動く素材」だ。一方で、カチカチに固まった漆はびくともしない。性質の違う両者を無理に合わせれば、やがて漆が剥がれ落ちるか、木がさらに割れる。職人たちの間では、まさに「水と油」のような組み合わせだったのである。
この難題を、岡崎製材は100年培った木材選別眼と、裏側から割れを食い止める「チギリ加工」という伝統技術の合わせ技でねじ伏せた。さらに、漆工芸家・浅井啓介氏という「尾張の怪物」をパートナーに迎え、緻密な構造設計を完遂。不可能を可能にしたのは、愛知が誇る職人たちの「意地」に他ならない。
尾張の技と三河の素材――宿命のライバルが組んだ「チーム愛知」の底力
本作の背景には、もう一つのドラマがある。かつては独自の文化を競い合ってきた「尾張」と「三河」。この愛知の二大拠点が、伝統工芸の衰退という危機を前に、初めて対等な立場で手を取り合ったのだ。
「守破離の『破』、つまり型を破ることにこそ、次の100年がある」 漆工芸家・浅井氏は、今回の共創をそう振り返る。職人不足、伝統の形骸化。そんな暗いニュースを吹き飛ばすように、彼らはあえて「異物」同士をぶつけ合い、火花を散らすことで新しい価値を絞り出した。
素材が歩んできた傷だらけの歴史を、否定するのではなく、敬意を持って「継ぐ」。この「チーム愛知」による挑戦は、単なる工芸品の枠を超え、日本の伝統が生き残るための「生存戦略」そのものに見える。
不良品を「至高の逸品」へ変える、日本人本来の強かな知恵
「LOG-ing® Kintsugi edition」が私たちに突きつけるのは、現代の「使い捨て文化」への静かなる抗議だ。
傷があれば不良品、古くなれば廃棄。そんな画一的な価値観の中で、彼らは「傷こそが美しい」と笑ってみせる。サステナビリティという言葉が、どこか借り物の薄っぺらな表現に聞こえてしまうほど、この家具に宿る「再生の思想」は力強い。
欠点を隠すのではなく、愛でる。壊れたものを、壊れる前より価値あるものへ。この強かで美しい日本人の知恵は、いまや海を越え、グローバルなラグジュアリー市場からも熱い視線を浴びている。
欅の年輪に刻まれた時間と、職人の手による黄金の筋。それらが交差する一点に、私たちは日本のものづくりの、明るい未来を確信せずにはいられない。