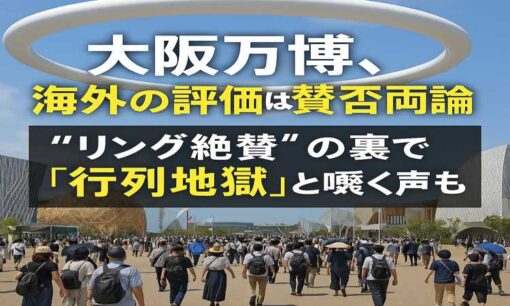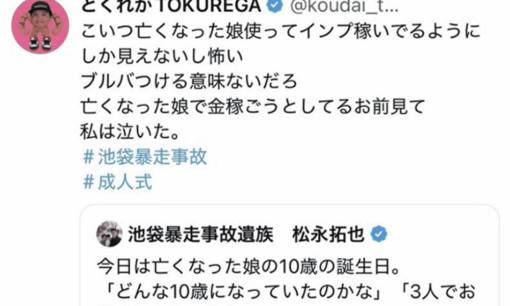着物を単なる古布と見なさず、そこに宿る記憶や祈りを受け継ぐ「スピリチュアル・クチュール」の思想。山形県南陽市から、職人技術と現代的感性を融合させ、伝統を世界基準の価値へ転換する挑戦が始まる。
2026年2月14日、ニューヨークが「南陽」に染まる日
2026年2月。凍てつくニューヨークのランウェイに、一羽の「神話の鳥」が舞い降りる。山形県南陽市に拠点を置く「OUNCHAN(おうんちゃん)」が、世界4大コレクションの一つ、ニューヨーク・ファッションウィーク(NYFW)への参戦を表明した。
地方都市の小さなアトリエから、世界最高峰の舞台へ。この「ジャパニーズ・ドリーム」とも言える快挙の主役は、代表兼デザイナーの渋谷純子氏だ。
彼女が手がけるのは、単なる「着物リメイク」ではない。タンスの奥底で眠り、役目を終えようとしていた着物の“記憶”を、現代のドレスへと転換する「再構築(Reweaving)」の物語である。
「ハサミを入れない」という美学。既存リメイクとの決定的な差
今や「アップサイクル」という言葉は巷に溢れている。しかし、OUNCHANのクリエイションは、それらとは決定的に一線を画す。
多くの業者が着物を一度解体し、平らな「反物」の状態に戻してから製品化するのに対し、彼女は元の着物が持つ「意匠の流れ」や「仕立ての文脈」を頑ななまでに尊重する。鍵となるのは、マネキンに直接布を当てて形を作る「立体裁断(ドレーピング)」の技法だ。
「着物一つひとつの想いに耳を傾ける」と彼女は語る。かつての持ち主が纏った時間の層を、あえて残したまま現代のシルエットに昇華させる。鳳凰や鶴の文様が、現代的なドレスの曲線と共鳴し、新たな命を宿す。この「過去を否定しない」圧倒的な独自性こそが、並み居る競合を退け、NYの審査員の心を動かした最大の要因と言えるだろう。
「効率は悪くていい」。スピリチュアル・クチュールが問う真価
この革新的な挑戦を支えているのは、渋谷氏が提唱する「Spiritual Couture(スピリチュアル・クチュール)」という、ある種、祈りにも似た経営哲学だ。
タイパ(タイムパフォーマンス)や効率性が叫ばれる現代ファッション産業において、同ブランドの歩みは驚くほど「遅い」。着物一着ごとに異なる物語を読み解き、一針一針を職人技で仕上げていく。そこにはマニュアル化された大量生産の余地はない。
「この挑戦が、県内繊維産業の新たな可能性を拓く道標となる」と、やまがた産業支援機構も期待を寄せる。効率を捨て、手間を愛でる。その「非効率の極み」から生まれる唯一無二の価値が、今、サステナブルの本質を求める世界市場において、究極のラグジュアリーとして再定義されようとしているのだ。
伝統を「守る」のをやめたとき、文化は初めて再生する
OUNCHANのNY進出から、我々ビジネスパーソンが学ぶべきは「伝統との向き合い方」だ。
これまで、多くの伝統工芸が「保存」という名の硬直によって衰退の道を歩んできた。しかし渋谷氏は、着物を「守るべき遺物」としてではなく、世界を驚かせるための「最先端の武器」として再定義した。形を維持することに固執せず、本質(スピリット)を抽出して現代の文脈へ翻訳する。
「山形・南陽に根づく記憶が、世界で新たな価値となることに意味がある」と、ブランド戦略を担う深沢光氏は指摘する。ローカルな物語を、グローバルな言語へと書き換える勇気。この「文化の更新」こそが、閉塞感の漂う日本産業を救うための、最も強力なヒントになるはずだ。