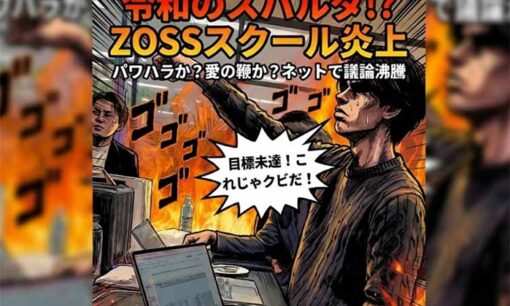物流現場で不可避に発生し、コストをかけて廃棄されてきた「負の遺産」を、地域を温める「資源」へと転換する。鉄の物流を担う丸吉ロジの試みは、エネルギー価格高騰に悩む現代社会への、泥臭くも合理的な回答である。
北広島雪まつりで1,000人が驚愕した「廃油」という未知の熱源
2026年1月31日、北広島ふれあい雪まつりの会場。凍てつく風が吹き抜ける中、人だかりができているテントがある。鉄の物流を担う丸吉ロジ株式会社が設営した「SDGsストーブ休憩所」だ。
ここで暖を取るための燃料は、驚くべきことに市内の飲食店から回収された「使い古しの天ぷら油」や、トラックの整備現場で出た「廃エンジンオイル」である。
「これが本当にゴミだったのか」と、家族連れが焼きマシュマロを頬張りながら不思議そうに炎を見つめる光景は、もはや冬の風物詩になりつつある。前回の開催では、この廃油の熱を体験した市民は延べ1,000人を超えた。
単なる企業の展示を超え、今や会場に欠かせない安らぎの場として定着している事実は、廃棄物が価値ある資源へと昇華した証左といえるだろう。
燃料費高騰の救世主か。廃油ストーブ「サイクルバーン」が示す圧倒的独自性
なぜ、鉄を運ぶ物流会社がストーブを自ら手がけるのか。その背景には、物流業界を直撃している深刻なエネルギー危機がある。同社が開発し、今回リブランディングして出展する廃油ストーブ「CYCLE BURN(サイクルバーン)」は、現場の切実な要請から生まれた結晶だ。
既存のバイオマス機器の多くは専用燃料を必要とし、導入への障壁が低くない。しかし、本機は現場で発生した油を精製することなく、そのまま燃料に転換できる汎用性を備えている。
廃棄費用を払って処理していた負の遺産を燃料に変えることで、理論上の燃料代を「0円」へと近づける。燃料費高騰に喘ぐ整備工場や物流倉庫が、この無骨なストーブに熱烈な視線を送る理由は、その圧倒的な経済合理性にある。
「捨てればゴミ、燃やせば資源」エネルギー地産地消に込めた経営哲学
代表の吉谷隆昭氏の言葉には、抑制がききながらも強い自負が滲む。
物流会社として日々膨大なエネルギーを消費しているからこそ、その責任の取り方を考えなければならないと氏は説く。地域で出た油を地域を暖めるために使う。この小さな循環こそが、真のサステナビリティであるという確信がそこにはある。
これは単なるコスト削減の物語ではない。灯油などの化石燃料に依存し、不安定な国際情勢に振り回されるリスクを、自らの手でコントロール可能な「地域循環型エネルギー」で克服しようとする壮大な実証実験なのだ。
カーボンニュートラルという言葉が叫ばれて久しいが、植物由来の油を燃やすことは、大気中の二酸化炭素を増幅させない理にかなった選択でもある。
物流企業から学ぶ、サステナブル経営を「利益」に変える真髄
丸吉ロジの試みは、エネルギー価格の高騰に直面するすべての日本企業への福音となるだろう。彼らが証明したのは、持続可能な経営とは決して我慢することではなく、知恵を絞って実利を生み出すことであるという事実だ。
自社がコストを払って捨てているものの中に、新たな価値が眠っていないかという問い。そして、環境対策を単なる「義務」ではなく「経営の武器」へと昇華させる構想力。
北広島の雪景色の中で赤々と燃える火は、単なる暖房器具ではない。既存のビジネスモデルを燃やし、新たな価値を創造しようとする一企業の挑戦の証であり、エネルギー自給の未来を照らす希望の灯火である。