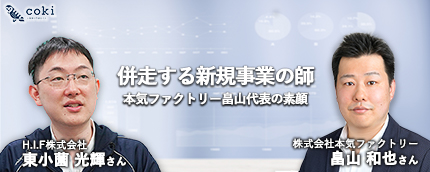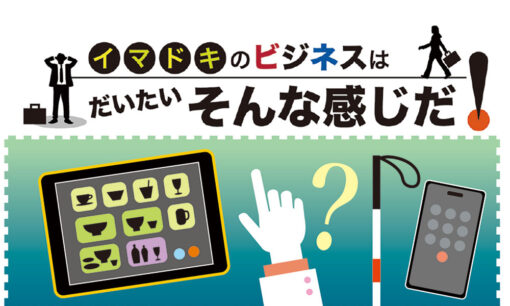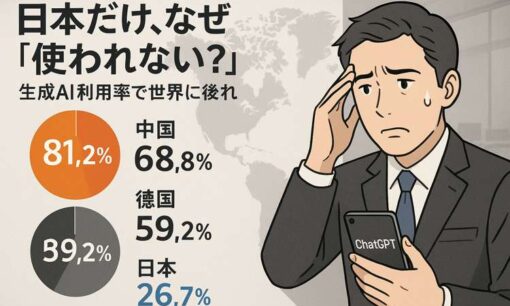SNSで強い政治メッセージが発信されるたび、対立が先鋭化する──そんな構図に、わずかな揺らぎが生まれている。中国外交部の威圧的な投稿を、日本のネットユーザーが大喜利へと“変換”した今回の騒動は、笑いが敵対感情の生じる場を一点緩和した出来事でもあった。過去の「日本鬼子」創作や、海外のユーモア外交の事例を振り返ると、武力に依らず相手の言葉に応じる手段としての「笑い」の可能性と限界が見えてくる。SNSが生み出す新しいカウンターの形を、見直したい。
11/13日、中国外交部アカウントの投稿で起こった大喜利合戦
いまX(旧Twitter)では、日本のネットユーザーが「中国外交部」をオモチャにして遊ぶ光景が広がっている。発端は、中国外交部や国防部の公式アカウントが、日本語も交えた強い警告文を相次いで投稿したことだ。高市早苗首相が衆院予算委で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁し、それを撤回しないことへの反発として、「頭を割られ血だらけにする」といった物騒な表現も投稿されたと報じられている。
本来であれば、こうした威圧的なメッセージは不安や怒りを増幅させる方向に働きやすい。しかし今回、この騒動に「斜め上」から参戦したのが日本のネット民である。あるユーザーが「中国外交部ジェネレーター」と呼ばれるツールを作成し、誰でも外交部の投稿風の画像をつくれるようにしたことで、一気に大喜利合戦が始まった。現在は「大判焼~」といった別名に改称されているが、仕組みは同じだ。
国際大学GLOCOM客員研究員の小木曽健氏は、この状況を見て「実は過去にも似た“斜め上”事案があった」と振り返る。尖閣漁船衝突事件で日中関係が荒れたころ、中国国内では日本人への蔑称である「日本鬼子」が飛び交い、激しい反日デモが続いていた。これに対し日本のネットユーザーは、あえてその「日本鬼子」をかわいらしい萌えキャラクターにしてしまう創作を始めた。
検索すれば当時のイラストを今も見ることができるが、それを目にした中国側のネットユーザーからは「我々は何と戦っているのか」「……ちょっとかわいい」といった声が漏れ、いくぶん戦意をそがれていた、と小木曽氏は記している。
こうした経験を踏まえ、小木曽氏は次のようにまとめる。笑いには、相手を笑ってしまうと相手を心底嫌いになれなくなるという効果がある。軍事力で威嚇する相手に向けられた笑いは、民主主義や言論の自由の素晴らしさを伝えるカウンターにもなりうる。だからこそ、今回の大喜利騒動が、中国側のネットユーザーの目にも届くことを願ってやまない――と。
威嚇と恐怖のために投げられたメッセージが、受け手によって「笑い」に変換されていく。この“変換装置”としてのSNS文化に、小木曽氏は可能性を見いだしていると言える。
海外事例3選にみる“ユーモア外交”の可能性
こうした「強いメッセージがミーム化し、笑いの対象になる」という構図は、海外でもたびたび観測されてきた。ここでは、対立が生じている場面でユーモアが介在した3つの事例を見ておきたい。
Canada at NATO(カナダのNATO代表部)による「Russia/Not Russia」投稿(2014年)
2014年、ウクライナ東部・クリミア情勢をめぐり、ロシア軍の兵士が「誤ってウクライナ領内に入った」と説明したことに対して、カナダのNATO代表部は公式X(当時はTwitter)で一枚の地図画像を投稿した。
そこでは、ロシア領が「Russia」、ウクライナなど周辺国が「Not Russia」と色分けされ、「地理は難しいかもしれない。しょっちゅう道に迷ってウクライナに“誤って”入ってしまうロシア兵のためのガイドだ」と皮肉たっぷりのコメントが添えられていた。この投稿は3万回以上リツイートされ、NATO加盟国のアカウントやウクライナ外務省も反応し、国際的な話題となった。
軍事侵攻という重い状況を背景にしながらも、カナダ側はここで「怒りをぶつける」ではなく「地理の授業」として批判する道を選んだ。相手の主張の不自然さを、ユーモアを交えて可視化することで、第三者から見た緊張のトーンも一段階下がる。構図としては依然として敵対であるが、笑いをまじえた風刺によって、「ただ怖いだけの存在」ではなく「笑いの対象にもなりうる存在」としてロシアを描き直している。
Embassy of Israel to the USA(米国在イスラエル大使館)によるミーム投稿 ― 映画『Mean Girls』引用(2018年)
2018年6月、イランの最高指導者ハメネイ師が、イスラエルを「根絶すべき腫瘍」と呼ぶなどの厳しい非難をXに投稿した。これに対して、米国在イスラエル大使館の公式アカウントが返したのは、人気映画『Mean Girls』の一場面から切り取った「Why are you so obsessed with me?(なんでそんなに私に執着するの?)」というGIF画像だった。
敵対的な声明に対し、政治用語や歴史的文脈ではなく、ポップカルチャーの軽いミームで応じる。ObserverやBusiness Insiderなどはこれを「ミーム外交(meme diplomacy)」の象徴的な一例として取り上げた。ユーモアをはらんだ返答は、支持者や第三者から見ると、「過激なのはむしろ相手側で、こちらは余裕を持っている」という印象を与えやすい。
もちろん、中東情勢そのものを変えたわけではない。しかし、少なくともSNS空間においては、通常なら張り詰めた応酬になる場面が「少し肩の力が抜けた皮肉」として提示され、敵対感情がそのまま増幅されるのを食い止める働きを持ち得たと言える。
インドのフードデリバリー企業 Swiggy と Zomato のSNS掛け合い
3つ目の例は、国家間ではなく企業間の「ライバル関係」が舞台である。インドのフードデリバリー大手であるSwiggyとZomatoは、激しい市場競争のライバルでありながら、SNS上では互いをネタにしたジョークや軽妙な掛け合いを続けてきた。
広告・メディア専門サイトなどの報道によれば、両社は割引キャンペーンや新サービスをめぐって軽く“煽り合い”つつ、ときに映画『Sholay』の名コンビ「Jai & Veeru」になぞらえて、自分たちの関係を「ケンカするほど仲が良い」キャラクターとして演出する。その結果、ユーザーからは「どちらも面白い」「この掛け合いを見るのが楽しみだ」といった反応が寄せられ、競争が単なる罵り合いではなく、エンターテインメントとして受け取られている。
ここでユーモアが和らげているのは、国家の緊張ではなくビジネス上の対立だが、「本来なら敵対関係になりやすい相手を、あえて笑いのパートナーにもしてしまう」という構図は共通している。
私たちが大切にすべき「武力を用いない反撃」の意味
中国外交部の日本語警告文をめぐる大喜利や、「日本鬼子」萌えキャラ化のエピソード、そして海外のユーモア外交・ブランド間の掛け合いを並べると、一つの共通点が浮かび上がる。それは、武力や物理的な力ではなく、言葉と表現のレベルで反撃するという態度である。
相手が軍事力や暴力を背景にした威圧的メッセージを投げてきたとき、こちらが同じ種類の力で応じれば、対立はそのままエスカレートする。これに対して、「笑い」で受け止め直すことは、メッセージの重さや怖さを一度分解し、別の文脈に置き換える行為だ。小木曽氏が述べるように、笑いには「相手を笑ってしまうと、嫌いになれなくなる」という作用がある。相手を完全な悪として固定せず、どこか滑稽な存在として捉え直すことで、こちら側の心の持ちようも変わる。
カナダの「Russia/Not Russia」地図や、イスラエル大使館の『Mean Girls』ミーム、SwiggyとZomatoの掛け合いは、それぞれの場でこの「言葉による反撃」のバリエーションを示している。相手をやり込めることだけを目的とするのではなく、第三者の視線を巻き込みながら、対立の構図そのものを揺らがせていく。
もっとも、ここから先は本稿の筆者としての補足になるが、笑いには当然リスクもある。現に被害を受けている人にとっては「笑い事ではない」状況もあり、当事者の痛みが“ネタ化”されれば、それ自体が新たな傷になる。誰に向けた笑いなのか、誰がその場にいないのか――その線引きは常に意識されるべきだろう。
それでもなお、相手の発言や態度に「何も言い返せない」か「力でやり返す」か、という二択しか持たない社会は窮屈だ。ネット空間における大喜利やミームは、その間にもう一つの道――武力を用いない反撃――がありうることを具体的なかたちで示している。
怒りや恐怖を飲み込みすぎず、同時に暴力に訴えずに応答する。そのための手段として、どんなユーモアが可能なのか。今回の中国外交部をめぐる騒動は、その問いを私たちに投げかけている。