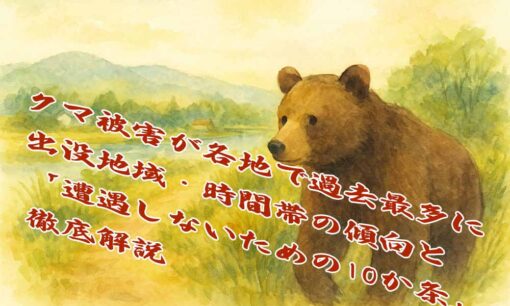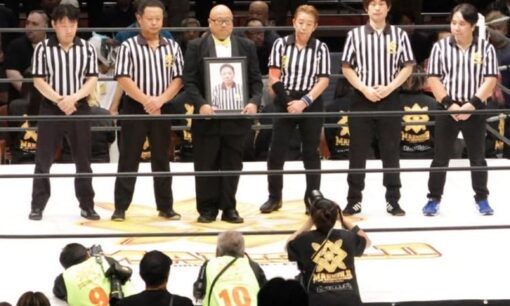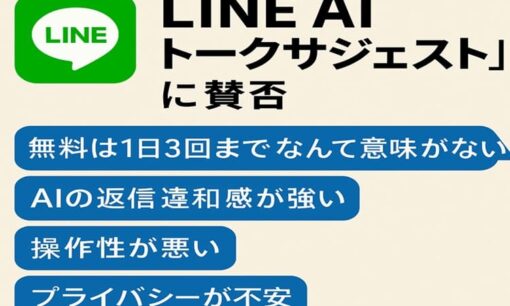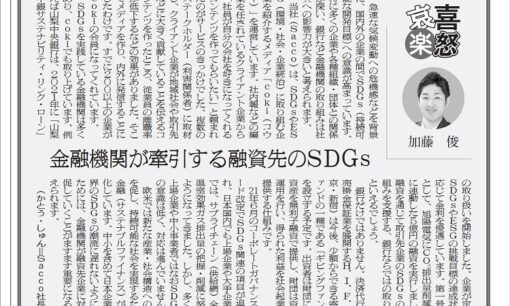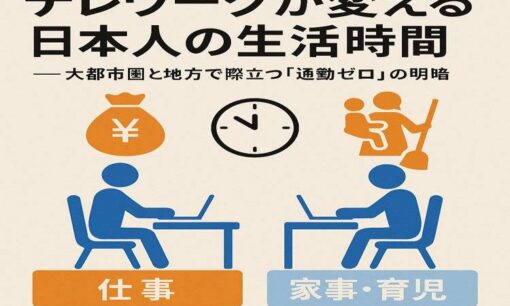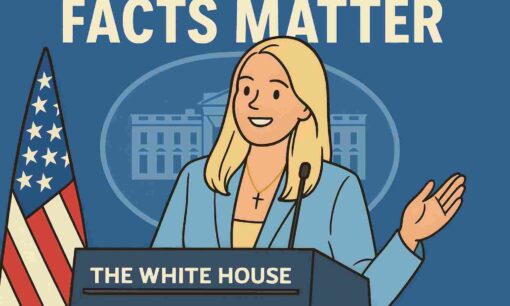今年4月〜10月、環境省が発表したクマによる被害件数は176件、被害者数は196人に上り、過去最悪のペースで推移している。各地で連日のクマの目撃や被害報告が報じられ、日常生活に不安が広がるなか、週刊誌週刊SPA!に連載を持つ俳優・猟師の東出昌大氏が「そんな危ないもんじゃないですよ」という実感を投げかける寄稿を発表した。
しかし、その言葉はYahoo!ニュースのコメント欄で批判を浴び、波紋を広げている。東出氏の現在の活動状況も踏まえながら、寄稿の内容、反響、そして背景にある狩猟・野生動物対策の実情を報じる。
東出昌大氏の現在地と活動状況
1988年2月1日生まれ(37歳)の東出昌大氏は、モデルとして活動を始め、映画『桐島、部活やめるってよ』で俳優として注目を集めた。その後も『GONIN サーガ』『デスノート Light up the NEW world』『コンフィデンスマンJP』シリーズなど話題作に出演し、若手俳優の中でも確固たる地位を築いてきた。しかし、俳優人生は決して平坦ではなかった。
2020年1月、映画で共演した俳優との不倫が報じられ、大きな社会的批判を受けた。当時、妻だった女優の杏との離婚は同年8月に成立し、三児の父である東出氏のイメージと仕事には深刻な影響が及んだ。CM出演はすべて終了し、映画やドラマの公開時にも批判が寄せられるなど、芸能活動は一時停滞した。
その後、東出氏は都心から距離を置く選択をした。2022年頃から山間部に移住し、山小屋での自給自足生活を公開。猟師免許を取得し、山に入って狩猟を行う生活に軸足を移したことで、「芸能界から距離を置いた生き方」「社会的スキャンダルからの再出発」といった文脈で注目されるようになる。
一方で俳優業を完全に手放したわけではない。2023年には映画『Winny』や『雪女と蟹を食う』などに出演し、演技力は一定の評価を維持している。2024年以降はメディア露出こそ抑制しているが、週刊SPA!連載など、自身の暮らし方や自然観に基づいた文章活動が増加。自給自足生活を取材したドキュメンタリー企画、トークイベントなども継続的に行っている。
また、地方のイベント出演や講演では「自然と生きる」「自分で獲って食べる」という生活哲学を語る機会が多く、近年は“俳優兼猟師”として独自のポジションを築きつつある。芸能界の華やかな場よりも、山を歩き、獲物と向き合う日々を通じて得た実感を語ることに価値を感じているようだ。
スキャンダル後の復帰劇というより、「山での生活に根ざす表現者としての再出発」と捉える方が適切かもしれない。寄稿の文面からも、表層的な発言や炎上狙いではなく、山の現場で見てきた現実から“言うべきことだけを言う”という姿勢がうかがえる。
寄稿の主張:クマ報道の「過熱」と実感
寄稿の中で東出氏は、次のように述べている。
まず、テレビを持たない生活であっても、連日のようにクマ報道が飛び込んでくることに言及。「週刊誌などからも今年だけで8件もの取材依頼を受けた」と述べ、クマをめぐる言葉が“数字が取れる”題材としてメディアに扱われていると分析している。
「日常的に山に出入りしている身からすれば、クマには滅多に出合わない」と実感を語り、環境省の死者数を挙げながら「一昨年6人、今年5人(令和7年8月末時点)」「以前からお亡くなりになる方は一定数いた」と冷静な視点を提示している。
東出氏は「メディアは『危ない』『死のリスク!』などの言葉を拾い歩きたい」という前提があると述べ、「そんな危ないもんじゃないですよ」という自身の実感は、編集部にとって快く思われないことも分かるから、取材を断ると明かしている。
さらに、出没の背景として、
- 山の木の実の不作
- 猟師の高齢化
という二つの要因を指摘。特に狩猟免許所持者の約70%が60代以上という環境省の統計に触れ、「60代はまだ若手です、70代80代の猟師が多い」と現場の状況を記述。車で道路脇に止まり鹿を撃つ「流し猟」、道路沿いに罠を掛ける手法が主流になっているとし、獲物を一人で運べず道路に遺棄されるケースも示唆している。
東出氏は最後に、「クマがこれ以上迫害されない為に、捨てられる鹿の生命を減らす為に、ちゃんと獲物を持って帰れる若い猟師が増えてほしい」と願いを記し、「私は殺してばっかの日々だが、この寄稿で一人でも多くの猟師が増えて、その方の人生と山の生き物の生命が良い方向に向いてくれたらなぁ、と。誰が為にか書く」と締めている。
寄稿に寄せられた批判と背景
この寄稿がYahoo!ニュースで配信されると、コメント欄には批判が殺到した。主な声は以下の通りである。
- 「被害件数が増えているのに“そんな危ないもんじゃない”と言われても、住民の恐怖が伝わらない」
- 「クマ被害で亡くなった人もいる以上、軽視とも受け取れる言い回しは不快だ」
- 「猟師視点だけで語るのではなく、地域住民・被害者視点が薄い」
- 「若い猟師を増やせという提案は、駆除・狩猟を肯定する方向に見える」
メディアが恐怖を煽る構図と、現場で山に入る者の感覚とのズレが浮き彫りになった。特に、クマ出没で実際に日常生活に支障をきたしている地域住民からは「報道以上に現実が怖い」という切実な声が多数寄せられていた。
同時に、寄稿の中にある「メディアは数字が取れる題材を喜ぶ」「報道が過熱している」という批判には、「確かにニュース映えしやすい素材ではある」という支持の声もあった。だが、全体としては批判的な反響が目立った。
クマ問題をめぐる視点の交差点
東出氏の寄稿と、その後に寄せられた読者の反応は、私たちが今どの地点に立っているのかを静かに映し出している。被害の増加で緊張が高まる地域社会、恐怖を可視化しやすいメディア構造、そして高齢化が進む狩猟現場の疲弊。この三つの現実が折り重なるなかで、クマ問題は単なる“出没情報”や“駆除の是非”だけでは語りきれない複雑さを帯びている。
寄稿で示された東出氏の言葉は、山で生きるひとりの猟師としての実感に根ざす。しかし、生活圏にクマが現れる地域住民にとっては、その言葉が現実との距離を感じさせる場合もある。互いの立場の差が、そのまま受け止め方の差となって表れているのだろう。
いま求められているのは、恐怖を増幅させるのでも、危険を矮小化するのでもなく、事実に基づいて「どこで何が起きているのか」を丁寧に共有する姿勢である。山林管理、生態系の変化、狩猟体制の再構築、報道の在り方。いずれも一朝一夕では解決しないが、視点を積み重ねることでしか前に進めない問題だ。
東出氏の寄稿は、そうした議論の入口を改めて提示したといえる。今回の反響が、地域の不安や現場の声をくみ取る議論へとつながっていくことが望まれる。