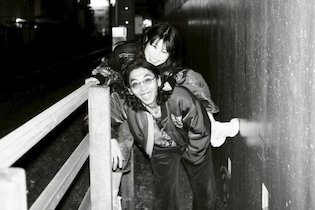「日本が壊される!」——10月26日、日本各地で“移民政策反対デモ”が同時多発的に行われる。山形、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、愛知、大阪、愛媛、福岡と列島を覆う怒号は、政府が推し進める外国人労働者受け入れ拡大への恐怖と不信の表れだ。6月の大阪デモからわずか数か月で火種は全国に飛び火し、すでにJICA事業撤回という具体的な影響も生んだ。治安、文化、地域社会への不安が、いま一斉に噴出している。
“地方も立ち上がった”——都市から全国へ広がる怒り
これまで反移民運動は「都市部の一部の声」と片づけられてきた。しかし今回のデモ予定地には山形や愛媛といった地方都市の名も並ぶ。大阪での数百人規模のデモは、参加者の映像や演説がX(旧Twitter)上で拡散され、瞬く間に「自分たちの地域でも声を上げよう」という共感を生み出した。
地方にとって、人口減少や高齢化はすでに切迫した現実だ。
そこに外国人労働者の大量流入が重なれば、雇用の競合や地域文化の解体を招くのではないかという恐怖が直結する。都市部の課題ではなく“日本社会全体の存続”を揺るがす問題として受け止められていることが、今回の運動を特異なものにしている。一見すると小規模な動きに見えても、その背後にある「生活基盤を守りたい」という感情は切実だ。だからこそ、全国同時デモという形で怒りのエネルギーが結集した。
“治安崩壊”は現実か——外国人犯罪の急増が突きつける数字
参加者の恐怖心を支えているのは、SNS上の憶測ではなく、実際に報道される事件や統計の数々だ。
警察庁によれば、来日外国人による刑法犯の検挙件数は令和5年に1万5000件を超え、前年比で約2割増加した。
特にベトナム人による窃盗事件は突出しており、侵入窃盗に限れば検挙人員の8割を占めるという。長野県では技能実習生を含むベトナム人による刑法違反が2024年に246件、前年の3倍以上となり、地元紙は「かつてない治安不安」と報じた。
さらに埼玉県川口市では、トルコ国籍の男が女子中学生への性的暴行で有罪判決を受けた後、再び別の少女に同様の行為を行ったとして摘発され、法務大臣が「強い危機感」を示した。こうした再犯事例は、制度設計そのものへの疑念を強める象徴となった。
「数字が現実を裏づけている」——参加者たちの声は、ただの思い込みではなく、事実として報じられる事件を根拠にしている点が大きい。治安崩壊の恐怖は確かに“肌で感じる現実”になりつつある。
クルド人コミュニティの摩擦——地域社会に広がる亀裂
川口市や蕨市では、クルド人住民と地元住民との間に摩擦が広がっている。公園や学校でのトラブルが繰り返し報道され、周辺では「子どもを一人で外に出せない」と語る保護者もいる。
移民が増えることで地域の多様性は確かに広がる。しかしその裏で、生活習慣の違いや言語の壁から小さな衝突が積み重なり、やがて社会不安につながっている。差別的言辞が飛び交えば移民側も被害者となり、対立はさらに先鋭化する。
「受け入れるか、拒絶するか」という単純な構図ではなく、地域社会が実際にどう変容しているのかを直視せざるを得ない段階に入っている。デモ参加者が「これ以上は日本がもたない」と訴える背景には、このような摩擦の現実がある。
政府の“ごまかし”とJICA撤退——国民の不信は頂点に
政府は一貫して「移民政策ではない」と強調する。東京都がエジプト人労働者との協定を結んだ際も「単なる労働力補填」と説明したが、市民の疑念を晴らすことはできなかった。
さらにJICAの「ホームタウン事業」では、山形・千葉・愛媛などの自治体がアフリカ諸国との交流都市に指定されたが、「移民受け入れの布石ではないか」と批判が殺到。結果として名称変更や撤回に追い込まれた。この経緯は「国民の声を無視して進めた施策が結局破綻する」という典型例と受け止められている。
政策が発表されるたびに不信と反発が噴き上がり、国と市民の距離は開くばかりだ。「ごまかし続ける政府」と「信じられない国民」の対立構図は、もはや修復が難しい段階に入っている。
全国デモは“未来を決める分水嶺”
10月26日の全国同時デモがどれほどの規模になるのかは、日本社会の未来を占う試金石だ。数万人規模の動員となれば、政府は政策転換を迫られる可能性もある。警察の警備態勢やメディアの報道の仕方はもちろん、与野党の反応までもが注目されている。
市民が本当に求めているのは、単純な「移民を入れるかどうか」の二択ではない。出生率の低下、社会保障の持続性、地域経済の衰退——これらを含めた包括的な国家ビジョンが欠かせない。だが現状、政府からは説得力のある解決策が示されていない。
「未来を誰がどう描くのか」——10月26日のデモは、その問いを突きつける分水嶺になるだろう。
結び
全国同時デモに凝縮された“不安のうねり”は、単なる排外主義ではなく、日本社会そのものの在り方を問う叫びだ。10月26日、その声がどれだけ響き渡るかによって、政府の進路、そして日本の未来の形までもが大きく揺さぶられるに違いない。