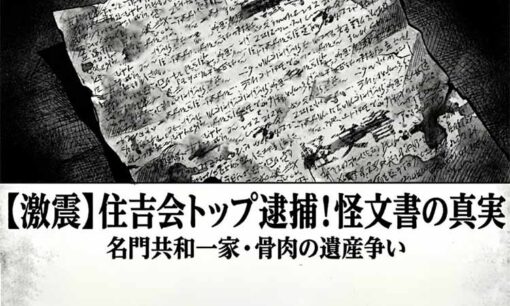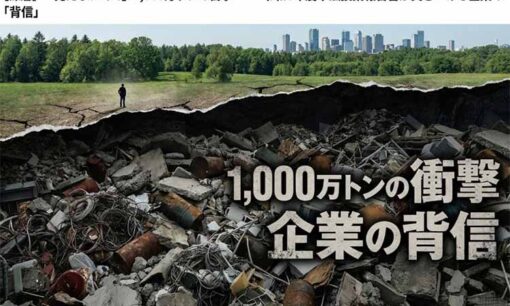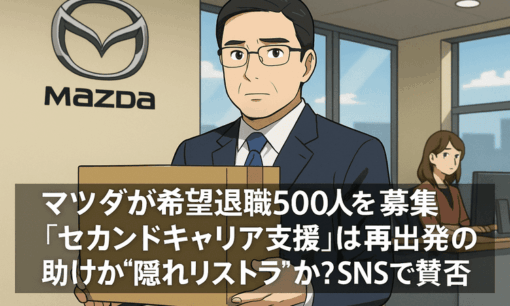長野県小谷村で2023年7月に開業した古民家レストラン「NAGANO」が、わずか1年余りで閉業する見通しとなった。運営会社「sio」(東京都)は村との指定管理契約を更新せず撤退を決定。1億2600万円を投じた村の大型投資であり、人気シェフ・鳥羽周作氏の監修という話題性にも関わらず、集客は伸び悩み、観光振興の起爆剤にはならなかった。さらに開業直前の不倫報道も宣伝活動を停滞させ、集客不振に拍車をかけたとみられる。
華々しい開業と村の期待
小谷村は新潟県境に位置し、冬季には豪雪に見舞われる過疎の村。観光による地域振興を目指し、2017年度に築140年超の古民家を取得。およそ1億2600万円を投じて飲食店向けに改修した。指定管理者選定は難航したが、2022年10月に東京・大阪・福岡で展開する人気レストラン「sio」と契約が成立。翌2023年7月、古民家レストラン「NAGANO」がオープンした。
開業当初は鳥羽周作シェフの知名度を背景に、県外からもファンが訪れ、話題性は十分だった。メニューは3,000円の鮭定食や、1〜3万円のコース料理など、都会的な価格設定でスタート。村役場は観光の起爆剤としての成功を期待した。
価格と立地が生んだ壁
しかし、オープン後しばらくすると客足は次第に鈍化した。観光客は一定数来訪したが、村内外のリピーターは伸びず、2023年度(7月〜翌3月)の来客数は2,916人。翌2024年度は2,005人と減少し、収益改善には至らなかった。
背景には価格設定と立地条件のミスマッチがある。鮭定食に3,000円という価格は観光客にも割高に映り、2万円のコース料理は旅行中の時間制約や費用感に合わなかった。さらに村は豪雪地帯で、冬季はアクセスが困難。宿泊を伴う観光客にとっても、夕食は宿の提供で済ませるケースが多く、集客のハードルは高かった。
運営側も価格を下げ、インバウンド向けにすき焼きメニューを導入するなど対策を試みたが、大きな改善にはつながらなかった。
若きシェフと村民の奮闘
厨房を任されたのは、入社4年目の白木聡シェフ(当時30歳)。長野県上田市出身で、地元に貢献したいという思いから小谷村に移住した。開業準備の段階から農家や住民を訪ね歩き、山菜や伝統的な保存食「小谷漬け」を取り入れるなど、地元色を打ち出す努力を重ねた。
自ら畑を耕して食材を育てるなど、村に根ざした活動も展開。村民の中には当初懐疑的な声もあったが、真摯な姿勢が次第に理解を呼び、協力を得られるようになった。農家の協力で新メニューを開発し、試食会を通じて地域の食文化を広める取り組みも進められた。
しかし、料理の完成度や接客以上に、集客と収益という厳しい経営課題は解決されなかった。
開業直前の不倫報道と宣伝停滞
2023年6月、開業を目前に控えた時期に、運営会社「sio」代表である鳥羽周作氏の不倫疑惑が週刊誌で報じられた。相手が有名女優だったこともあり、全国的に大きな注目を集め、古民家レストラン「NAGANO」にも余波が及んだ。
店舗周辺には記者が連日詰めかけ、問い合わせも料理や予約に関するものではなく報道対応が中心となった。本来なら開店告知やPR活動に注力すべき時期だったが、宣伝を控えざるを得ない状況に追い込まれた。
村役場には苦情や問い合わせが寄せられたほか、地域内でも否定的な声が一時強まった。現場スタッフは「逆境を追い風に」と奮闘したが、予約数の伸び悩みにつながったとみられる。閉業の直接的な理由は客数減と採算悪化だが、不倫報道が間接的に影響した可能性は否定できない。
それでも届かなかった集客
来客数は初年度2,916人、次年度2,005人と減少。特に冬季は積雪によるアクセスの悪さが致命的だった。観光客頼みのビジネスモデルは、近隣のペンションやホテルの食事提供と競合し、思うように需要を取り込めなかった。
定食中心への切り替えや価格見直しも実施されたが、効果は限定的。村民割引や料理教室など地域向けサービスを展開するなど努力を続けたものの、持続可能な経営には至らなかった。
契約終了と村に残された課題
2024年8月、村議会全員協議会で、運営会社から撤退の打診があったことが公表された。指定管理契約の満了は9月末。閉業は避けられない見通しとなった。
村にとっては1億2600万円を投じた大型投資であり、短期間での撤退は大きな痛手だ。村観光地域振興課の太田勝課長は「営業が苦しいことは知っていたが、撤退は痛手」とコメント。今後は村が改修した古民家をどのように活用するか、地元主体での再生が焦点となる。
閉業が投げかけるもの。観光と地域再生のはざまで
「NAGANO」は、有名シェフのブランド力と村の投資が結びついたプロジェクトだったが、価格設定、立地条件、集客戦略の難しさを乗り越えることはできなかった。開業直前の不倫報道も追い打ちとなり、集客の伸び悩みを加速させた。
閉業は失敗として語られる一方で、地域と観光の関わり方を見直す契機ともいえる。今後は地元の人々が主体となり、持続可能で地域に根ざした観光のかたちを築けるかどうかが問われている。