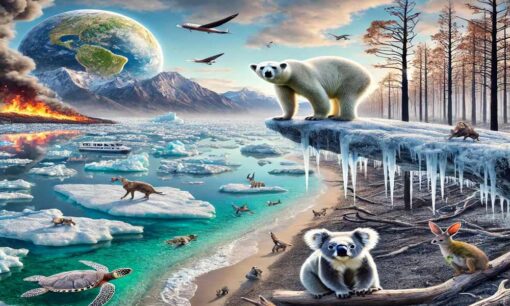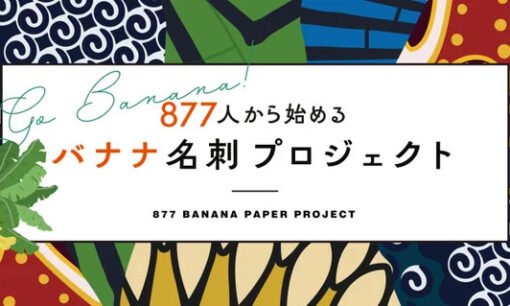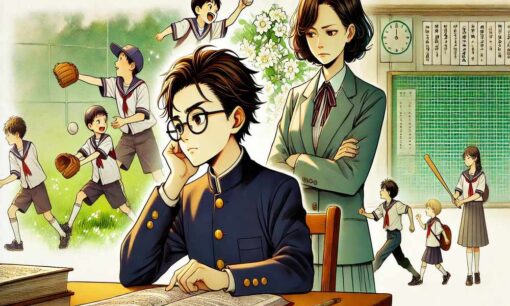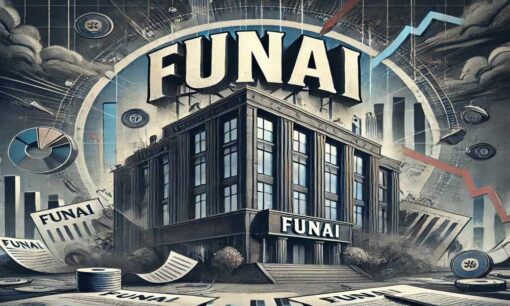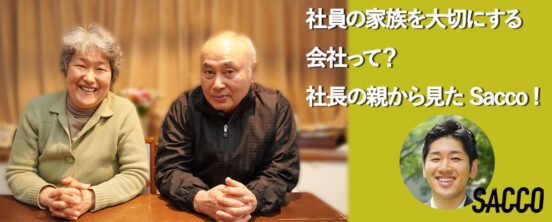そば蜂蜜ジェラート、ミツロウ新製品、ザンビア連携まで

宮城県丸森町・耕野地区の石塚養蜂園は、移動を最小限に抑える定飼養蜂を主軸に、蜂蜜の生産と「受粉用ミツバチ」の供給を二本柱として事業を営む。
「冬はいちばん寒い時期だけ千葉で越冬します。春以降は丸森を中心に仙台近辺、遠くは秋田まで採蜜に行きます」と代表取締役社長の石塚武夫氏。現場の実像とこれからを聞いた(編集部取材による)。
「消費するだけでなく生産する側に回りたいという思いが原点にある。アピールは得意じゃないけれど、蜂と向き合って淡々とやる——それがうちのやり方です」と石塚氏は語る。
仙台南の山里に根を張る定置養蜂
日本では九州から北へ季節を追う転飼(転地)養蜂が知られるが、石塚養蜂園は東北の山々に花期が巡る地の利を生かし、拠点を大きく動かさない定飼養蜂を重ねてきた。

「移動を抑えられる分、群の体調にしっかり向き合えるのがうちのやり方です」。冬は温暖な千葉で群を守り、春の訪れとともに宮城、秋田へと働きに出る。
「受粉用ミツバチ」は地域を回す“資材”
同園は蜂蜜生産に加え、施設園芸向けの受粉用ミツバチの供給で地域の農業を支える。「イチゴやメロン、スイカ、サクランボ、リンゴまで受粉にはミツバチが使われています。受粉を担う“資材”としての蜂ですね」。流通単位は箱で「1箱6,000〜1万匹くらい」。

価格は「作物によりますが1箱2万とか3万とか」が目安だという。貸し出しは長期に及ぶ。「イチゴなら10月から翌年4〜5月まで半年です。途中で群が弱ることもあるので、管理の段取りが肝心です」。
収益構成は蜂蜜4、蜂群供給1ほど。「病気とダニのコントロールを“どのタイミングで、どう打つか”。そこができないと安定供給は成り立ちません」。
採れたままを届ける 香りを閉じ込めた丸森の蜂蜜
同園の蜂蜜は採れたままの風味を尊重する。「蜂がためたものを余計なことをせずにいただく。ほんとうにそれだけです」。地場の直売所を中心に仙南から仙台市内まで丁寧に届けると、「花の香りが強く立つね、と言ってもらえることが多い」という。
そば蜂蜜ジェラートと、蜂の巣模様のワッフル
加工では“通好み”のそば蜂蜜を生かしたジェラートが目を引く。「そばの蜂蜜は色が黒くて独特の味で、一般には少し癖がある。でも乳製品と合わせると驚くほど相性がいい」。

自社菓子の定番「蜂蜜ワッフル」も人気だ。蜂の巣模様のオリジナル型を起こし、手焼きで仕上げる。「見栄えを狙ったというより、蜂蜜の良さが素直に出る形にしたかっただけなんです」。

ミツロウで広がるものづくり キャンドル、ワックス、クレヨン
採蜜の副産物・ミツロウの活用も進む。「キャンドルは形が見えてきました。秋から年内には出せると思います。木工や革に使えるワックスも年内を目標に。クレヨンは配合を試している最中で、来春に間に合わせたい」。直売所にただ並べるだけでは伝わらない現実も知る。「デザインや形、物語を添えて、ちゃんと届く形にしたいんです」。
ザンビアと結ぶ、森を守る蜂蜜づくり
耕野から始まった「ザンビア・プロジェクト」は今年、石塚養蜂園が主体の“養蜂特化”の段階に入った。「ザンビアは日本より蜂蜜が採れる土地です。ただ、自然巣を壊して採るなど非効率なやり方も残っている。衛生管理や巣箱の普及で品質と収量を底上げしたい」。狙いは自然保全にも及ぶ。

「養蜂が広がるほど森は生き延びます。大きな木がある森のほうが蜂蜜はよく採れるからです」。将来は技術協力の裏付けがあるザンビア産蜂蜜を日本で紹介する構想も描く。「ただの輸入ではなく、筋の通った蜂蜜として売りたい」。
被災と再起 「お見舞いですから」と言えた日の痛み
2011年の東日本大震災では、宮城沿岸のイチゴハウスが壊滅的被害を受け、貸し出していた群も約300箱が流出した。「体育館の避難所に行って『蜂代…』なんて言えるわけがない。だから『お見舞いですから』と請求は控えました」。経営的な痛手は小さくなかった。
2019年の台風でも養蜂場が被災し、巣箱が流された。「順調に来て足元をすくわれる、というのが2回ありました。だからこそ、いまは調子がいいときほど身を引き締めています」。それでも群を立て直し、地域の園芸と食卓を支え続けている。
課題は“伝わり方” 柏での小さな店構想
生産拡大の余地はあるが、宮城南部だけでは市場が限られる。「どこかに卸して終わりだと埋もれてしまう。作り手の気持ちまで含めて伝わる場がほしい」。故郷・千葉県柏市での小さな店を構想する。蜂蜜の試食や使い方の提案まで含め、体験を設計する考えだ。
身近な素材と蜂蜜の“出会い”をつくる
商品開発の軸は身近な素材だ。「わざわざ遠くから仕入れてまでやるなら、うちはやりません」。旬のフレッシュな山椒の実を蜂蜜に漬けると香りが移る。
「山椒はこの辺の山にあります。ドライとは香りの出方がまるで違う」。在来のナッツ「かやの実」を使った“国産×国産”の蜂蜜漬けにも取り組む。「かやの実は手間もかかるけれど、香ばしくておいしい。蜂蜜と合わせると、ちゃんとした一品になります」。
1997年独立、転地と定置の両面を知る
石塚氏は千葉・柏の出身。有機農家の手伝いを重ね、養蜂との出会いを機に鹿児島の養蜂家に住み込みで2年間修業した。「九州から東北、北海道へ北上する転飼養蜂を体で覚えました」。1997年、25歳で宮城に独立。「東北は蜜源の山が近く、同業者も少なかった。群の面倒を見切れる場所として、丸森がよかった」と振り返る。
変わらない核 “いい群”をつくり、淡々と届ける
蜂蜜の味は最終的に花が決める。「糖度は見られても、味は自然が決める」。一方、受粉に出す群の健全性は人の技術で変わる。「病気の兆候を見逃さず、時機を逃さず手を打つ。いい蜂を出すのは技術です」。そしてささやかな手応えが日々の糧になる。「『おいしい』『助かった』と言ってもらえる。
宣伝は得意じゃないけれど、群と向き合って、身近な素材と出会わせて、きちんと語れる場で手渡す。それがうちのやり方です」。