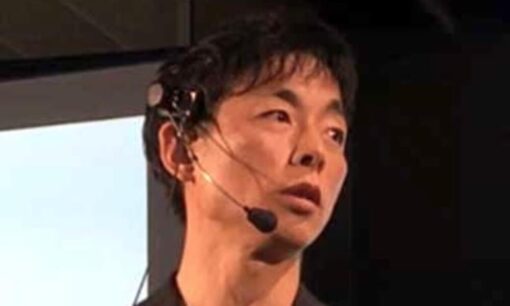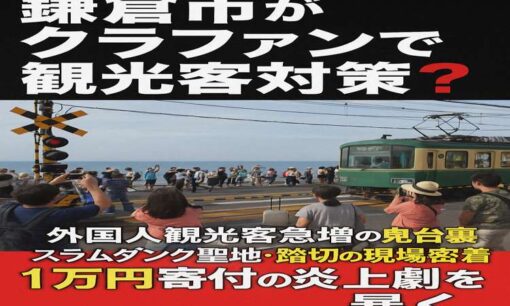7月5日。
空はよく晴れていた。洗濯物はすぐに乾き、エアコンは快適な室温を保ってくれていた。水道からはいつも通りの勢いで水が出たし、スーパーの棚にはペットボトルの水が山積みにされていた。
何も起こらなかった…その日は。
でも、それは“たまたま”だったのかもしれない。
今年2025年、梅雨明けは観測史上最速とも言われる早さで訪れた。6月中に西日本の梅雨が明け、7月初旬には全国的に真夏日が続いている。暑さのニュースは連日報じられているが、その裏で静かに進行しているのが「水不足」という見えない危機だ。
水が足りなくなる予兆…。雨が降らなかった梅雨
気象庁の発表によると、徳島県では梅雨期間中の降水量が平年の37%、潮岬ではわずか19%にとどまった。豊岡も41%、大阪や和歌山でも80〜90%と、各地で深刻な降水量の減少が見られている(MBSニュースより)。これは単なる“空梅雨”ではない。気象の長期的な傾向として、雨の降るべき季節に降らないことが常態化しつつあるのだ。
さらに懸念されているのが、水源の貯水率である。たとえば、東京都が依存する多摩川水系のダムは、すでに平年比16%減という報告も出ている。現在はまだ給水制限とまでは至っていないが、気温上昇とともに使用量が増え続ければ、一気に危機的状況に陥る可能性もある。
水不足で何が起こるのか?生活と経済への波紋
水不足は生活全般に影響を及ぼす。まず考えられるのが、家庭への節水要請や給水制限だ。これが進むと、洗濯やシャワーの回数に制限がかかったり、公共施設での水使用が制限されたりする。また、過去の事例では香川県で夜間断水が続いた年もあった。
さらに影響が大きいのが農業だ。灌漑用水が不足すれば、米や野菜の生育に支障をきたす。2023年には、関東の葉物野菜が高騰し、スーパーでの品薄が話題になった。今後も同様の事態が全国的に発生する可能性は否定できない。
飲料水や生活水の需要が増える一方で供給が不安定になれば、価格の上昇や買い占めといった社会的混乱も予想される。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、暑さと水不足のダブルパンチが健康リスクにも直結する。
備えは必要か?水を「買う」前に知っておくべきこと
「水を買っておいた方がいいのか?」という声がSNSでも増えている。答えはYes。ただし、必要最低限の備蓄にとどめるべきだ。
内閣府の防災ガイドラインによれば、1人1日あたり3リットル、最低でも3日分の備蓄が推奨されている。つまり、4人家族で36リットル、2リットルのペットボトルで18本分が目安だ。1か月分の買い占めや箱買いは不要であり、かえって他の人が買えなくなる社会的弊害を生む。
また、水道水を清潔な容器に貯めるという方法もある。ポリタンクや非常用給水バッグを活用し、定期的に入れ替えれば、災害時にも使える生活用水になる。重要なのは、「備える」ことを“静かに”、“必要なだけ”行うことだ。
やらなくてもいいこと。不安に駆られないために
水不足への不安が高まると、過剰な反応が起きがちだ。しかし、以下のような行動は、実は「やらなくてもいいこと」として見直すべきだ。
- 過剰な水の買い占めや保管
- 風呂に水を張りっぱなしにするなど、非衛生的な備蓄
- 冷房を我慢してしまう(熱中症のリスク増)
- 地域外の情報に過度に反応する
- SNSでの不確かな情報の拡散
備えとは、必要な行動だけを選び取ることでもある。恐れすぎず、しかし油断もせず、正確な情報に基づいて日常を見直すことが、最も賢明な「危機対応」なのだ。
「何も起こらなかった日」から始める備え
7月5日は、確かに何も起こらなかった。
けれども、水不足は“目に見えない形”で、すでに進行している。
田んぼに届かない水、枯れはじめた河川、下がりつづけるダムの水位…、そうした変化が、私たちの暮らしの背景で着実に起きている。
「何も起こらなかった日」こそ、備えを始める絶好のタイミングだ。
目に見えない変化に気づき、静かな行動を積み重ねていく。そうすれば、いつか「何も起こらなかったね」と言える夏を迎えられるはずだ。