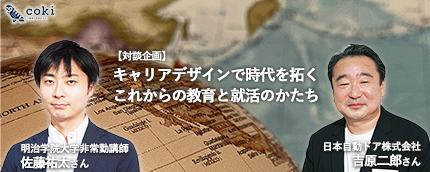東京都交通局が運行する都営バスの車内で、9歳の女児が置き去りにされる事案が発生した。子どもの安全確保を揺るがす今回の出来事は、単なるヒューマンエラーの一言では片づけられない。なぜ子どもは車内に取り残されるのか。背景にある課題と、子ども自身が取れる具体的な行動について考察する。
「終点での点検」は義務 それでも見逃された理由
事案が起きたのは2025年4月8日。都営バスは東京・荒川区の終点に到着後、運転手が営業所の車庫へ車両を移動したものの、本来義務づけられている「車内の終点点検」を行わず、そのままバスを離れたという。
都営バスの運転手は60代の男性で、「トイレに行きたかった」と事情を説明している。点検を怠った理由は一見、個人的な生理的事情にすぎないように見えるが、根底には「確認作業の形骸化」とも言える慣れが存在する。乗客の降車を前提とした“無人化”の思い込みが、こうしたリスクを引き起こす。
気づいたのは“家庭の備え” GPSで我が子の現在地を確認
この事案の発覚を早めたのは、父親が娘に持たせていたGPS端末の存在だった。帰宅しないことを不審に思った父親が位置情報を確認したところ、バスの営業所内にいることが判明。すぐさま連絡を入れ、事態の発覚につながった。
幸いにも女児は後部座席で寝ていただけで、体調に異常はなかった。だが、営業所に戻ってきた別の運転手が車内を確認するまで、25分間にわたり子どもは車内に取り残されていた。
繰り返される「置き去り」 未然に防ぐには
子どもが車両に置き去りにされる事故は、バスに限らず、通園バスや自家用車でも繰り返されてきた。2022年には静岡県牧之原市の認定こども園で3歳の園児が送迎バスに取り残され死亡する事故も発生している。
こうした事案に共通するのは、「確認手順の不履行」と「誰かが見ているだろう」という思い込みである。形式上のチェックが“慣れ”によって形骸化すると、安全確認は抜け落ちやすくなる。
一方で、今回のケースのように家庭でGPSなどの見守りツールを活用することで、早期の異常察知が可能になる場合もある。個人の備えが事故の深刻化を防いだことは評価できる。
子ども自身ができる「命を守る行動」も必要
今回のように、置き去りが判明するまでに一定の時間がかかるケースでは、子ども自身が自分の身を守る手段を知っているかどうかが生死を分けることもある。家庭や教育機関では、次のような行動を具体的に教えておくべきである。
● クラクションを鳴らす
車の運転席に移動し、ハンドル中央のホーンを何度も強く押して大きな音を出す。周囲の注意を引く効果が高い。
● 窓やドアを叩く・蹴る
閉じ込められていることを知らせるため、手や靴で大きな音を出す。必要に応じてガラスを割る行動も許容するよう教えておく。
● 大声を出す・叫ぶ
「たすけて」「ここにいるよ」と叫び続ける。恥ずかしがらずに声を出す訓練も事前にしておくとよい。
● GPS・携帯で連絡する
GPS端末やスマートフォンを持っていれば、緊急連絡先に電話する・警報を鳴らすなどの使い方を教えておく。
● 涼しい場所に移動・水分補給
夏場の高温時には直射日光の当たらない場所へ移動し、水筒があれば少しずつ水分を摂る。
組織と家庭、それぞれの再発防止策
東京都交通局は今回の事案を受け、車内点検の確実な実施を全乗務員に改めて指示したという。しかし、今後求められるのは「通知」ではなく「仕組み」だ。チェックリストの義務化、点検完了の記録制度、人物検知センサーの導入など、確認を人任せにしない構造的対策が必要である。
同時に、家庭や学校・園などでも、子どもに「命を守る行動」を教えることが欠かせない。待つのではなく、動く。その意識と備えが、いざという時に子ども自身を救う力となる。