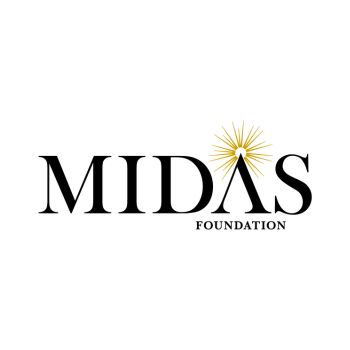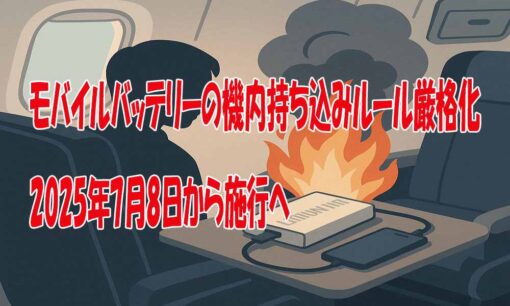公益財団法人ミダス財団(所在地:東京都港区、代表:吉村英毅、以下「ミダス財団」)は、子どもたちが多様な体験を享受できる社会の実現を目指す「子どもの体験コンソーシアム」を設立しました。11月17日に都内で設立シンポジウムを開き、子ども支援に取り組むNPO法人の代表や大学教員、国会議員等が、子どもの体験における現状と課題、今後の取り組みについて話し合いました。
体験の豊かさが、環境要因によって左右される現状
日常的な遊びや旅行先での新たな出会いや挑戦などを含む、あらゆる体験は、子ども時代の日常を彩り、成長する土台となるものです。豊かな人間性や自ら学び、自ら考える力といった生きる力の基盤としての役割が期待されます。体験には旅行やキャンプ、美術館やコンサートといった文化芸術体験など「非日常の体験」と、家庭内でのお手伝いや友達との遊び、習いごとなど「日常の体験」などさまざまな体験が含まれます。
しかし、人口減少などで地域コミュニティーが衰退する中、手軽な体験機会は減りつつあります。さらに体験の豊かさが、家庭や地域といった子ども自身が選べない環境要因によって左右される現状があります。こうした現状は「子どもの体験格差」とも呼ばれ、社会課題になっています。
本コンソーシアムでは、ミダス財団が事務局となり、子どもの学習支援・居場所づくり、自立支援など子ども支援に取り組むNPO法人や、子ども支援や教育学等を専門とする大学教員らと、課題を共有し協働します。
ミダス財団のチーフ・インパクト・オフィサー、山添真喜子さんは設立の意義をこう説明します。
「NPOの方とのヒアリングや、子どもの体験に関する既存の研究論文の整理、アカデミアの先生たちとディスカッションを通じて、さまざまなプレイヤーの方が取り組む分野である一方、それらの活動が分断されているように見受けられました。だからこそ、中間的な立場にあるミダス財団がステークホルダーの方たちをつなぐ場を提供することが重要と考え、コンソーシアムを立ち上げました」
「体験を買う社会ではなく、体験がある社会に」
11月17日に開いたシンポジウムでは冒頭、ミダス財団の吉村英毅代表が「さまざまな体験は子どもの成長の土台であり、近年は非認知能力を測るものとして重要性が高まっています。子どもの将来にとって何が重要かを本質に据え、多様な体験が保障される社会を目指します」と挨拶しました。

その後、本コンソーシアムに参加するNPO法人7団体の代表や大学教員ら専門家や子どもの体験に関する課題に関心のある国会議員が意見を交わしました。
困窮家庭の子どもへの支援に取り組む、認定NPO法人キッズドア理事長の渡辺由美子氏は、「約4500世帯を支援していますが、コロナ禍後、夏休みの予定が全くないという家庭が半数です。予定がある残り半数の家庭も地域のバザーやお祭りが唯一ある、というのが現状です」と説明。こうした状況を踏まえ、キッズドアでは、交通費の支給や食事の提供などの工夫を行ったうえで、子どもたちが参加しやすい体験イベントを企画しています。
子どもの体験機会に関する具体事例も紹介されました。子どもの居場所を提供する、NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい代表理事の金城隆一氏は、「一緒に食事をするといった仲間と集う日常的な体験に加え、飛行機に乗って遠い場所で職場体験するなど、新たな人と出会う非日常の体験の提供も行っています」と語ります。
子どもの貧困対策を進める認定NPO法人 Learning for All代表理事の李炯植氏は、「体験を買う社会ではなく、体験がある社会にしていかなければならないと考えます。公共性をもって体験を子どもたちに届けられる社会の実現にコミットしたい」と話し、子どもの体験に関する社会課題解決のため官民協働で取り組む必要があると提言しました。
シンポジウムの後半では、子どもが体験を通して得られる効果について話し合いました。子どもたちはさまざまな体験を通し、生きる力やソーシャルスキルが育つほか、逆境や困難に直面しても乗り越える「レジリエンス」が身につくことも期待されます。
本コンソーシアムでは今後、定期的な勉強会開催や調査研究に加え、子どもたちへの体験プログラムの提供を行います。体験機会の提供と並行し、参加した子どもたちにアンケートをとり、体験前と後の変化などを調査し、政策提言に生かします。