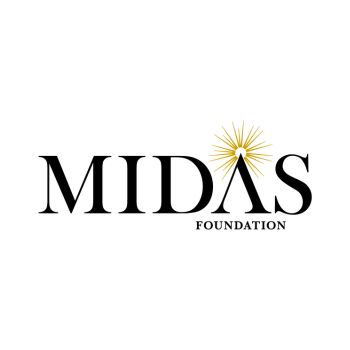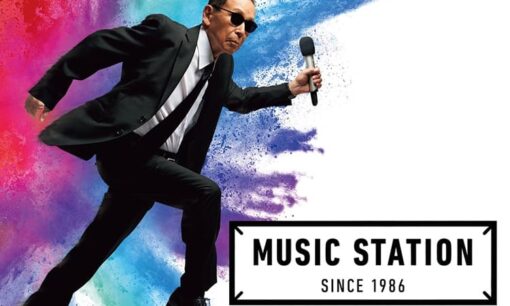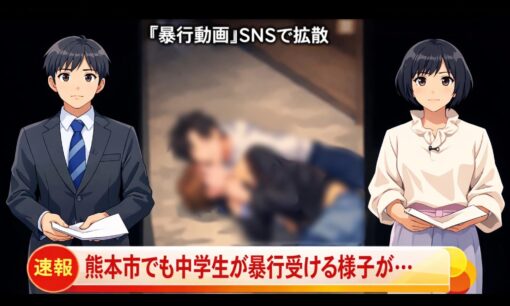地方に住む女子生徒には、地域とジェンダーの2つの格差があるとされています。
女子の場合、経済的要因や家庭や地域の価値観によって、地元に残るというプレッシャーを受けることも少なくありません。都市部では得られる進学情報やキャリアの選択肢が、地方では得にくい課題もあります。
「人生の選択を自ら決定できる社会」を目指す、公益財団ミダス財団(以下、ミダス財団)はこの夏、教育分野のジェンダーギャップ解消を目指す団体「# Your Choice Project」の活動をサポートしました。
8月に都内で行われた進学支援イベントを取材しました。
メンターが学習支援、生徒同士の交流会も
# Your Choice Projectは、地方に住む女子高校生に対し、進学やキャリア形成のための情報提供、ロールモデルとの交流、メンターによる学習支援などを行う団体です。
東京大学の女子学生たちが中心となり、2021年に設立されました。
地方に住む女子高校生に対し、難関大学に通う女子学生がメンターになり、個別に進路相談にのったり、学習計画を立てたりします。
このほか、さまざまな仕事に就く女性たちのキャリア講座、オンライン交流会なども開いています。
夏休みを利用した今回のイベントは、実際に東京大学のキャンパス訪問や民間企業の見学を通して、進学や就職の選択肢を広げてもらう狙いがあります。
広島や沖縄、群馬など全国の高校2年生たちが参加しました。

この日は、多様なキャリアを積んできた女性たちと意見交換する、ワークショップも行いました。
ミダス財団のチーフインパクトオフィサー・山添真喜子さん、ミダスキャピタルの投資先企業である株式会社ZEST(ゼスト)の田中さくらさんらがそれぞれのキャリアを語りました。
田中さんは都内の中高一貫の女子校を卒業後、東京大学理科2類に進学。
卒業後はトヨタ自動車、コンサルティング会社を経て、在宅医療・介護事業者向け収益改善プラットフォームを提供する株式会社ZESTで執行役員として活躍しています。
「受験を考えると、部活をいつまで続けるか悩んでいます」との参加者の相談に、田中さんは、こうアドバイスしました。
「受験生のときに赤点をとるぐらい物理が苦手でしたが、部活も推し活も続けました。息抜きを入れてコツコツ積み重ねたほうがうまくいく気がします。二度と戻れない高校生活、いま一番やりたいことを思い切り楽しんでください」(田中さん)
「やりたいことを、とことん追求してほしい」
ミダス財団のチーフ・インパクト・オフィサー、山添真喜子さんは自身のキャリアや仕事観について語りました。
山添さんは、大学卒業後、ITコンサルティングファーム、環境コンサルファームなど外資系企業を経て、米コロンビア大学で行政学(環境政策)修士課程を修了。
帰国後、日系の総合シンクタンクで、サステナビリティ経営を専門にするコンサルタントとして活躍。2025年1月にミダス財団に入りました。

「サステナビリティ経営の仕事に就く原体験になったのが、香港大学への留学でした。当時は、イギリスから中国に返還される直前で、大気汚染がひどく、ハードコンタクトが痛くてつけられないほどでした。企業活動と環境保護の両立が必要になる時代がくると実感しました」(山添さん)
この日、山添さんが高校生たちに伝えたかったことの1つが「自分のやりたいことを、とことん追求する」ということ。
環境コンサルティングファームから、シンクタンク、そしてミダス財団に転職後も一貫してサステナビリティ経営やインパクト評価に関する仕事を続けてきました。
インパクト評価とは、事業が対象社会にもたらした社会的な変化(インパクト)を測定する評価手法のこと。
「ニッチな分野でも自分のやりたいことを追い続けると、年齢を重ねたときに履歴書がストーリーのあるものになります。ぜひいろいろな挑戦をして、信念を持って取り組めることを見つけてください」(山添さん)
参加した生徒からは「進路や仕事を選ぶ視点が見えてきた気がします」、「失敗は怖いことではないんだと思いました。自分の夢を早く見つけたいです」という声が上がりました。
経済的ハードルや情報格差が課題に
WEF(世界経済フォーラム)が発表する2025年の「ジェンダー・ギャップ指数」、日本は調査対象の148カ国中118位。
経済、政治、教育、健康の4項目を総合して評価しますが、日本は主要7カ国(G7)では最下位です。特に女性の政治参加が後退しました。
世界的にも男女格差が大きい日本。その日本の中でも、東京が通学圏ではない地方に住む女子学生の進学の選択肢が狭められている現状があります。
東京大学の入学者に占める地方女子の割合は、2021年度でわずか9%です。# Your Choice Project代表・古賀晶子さんは「地方の女子学生が直面する課題は複合的です」と指摘します。

「まず、経済的なハードルがあります。学費だけでなく、下宿代や生活費の負担は家庭にとって大きいです。特に地方の女子は、地方の男子と比べ、実家に近い大学に行くことへの保護者の期待値が有意に高いという調査結果も出ています。地域によっては『女の子は地元で就職すべき』『遠くの大学に行くのは心配』といった価値観が進学の選択を制限してしまいます」(古賀さん)
情報格差の問題もあります。都市部なら塾や学校から比較的簡単に得られる進学やキャリア情報も、地方の学生には届きにくい課題があります。
福岡出身で現在、東京大学工学系研究科で学ぶ古賀さん自身も、高校生のときに意識の違いや選択肢の偏りを感じてきました。
だからこそ「進学やキャリアの情報格差を埋め、生徒が自分で将来を考えられる環境づくりをサポートしたい」と語ります。
参加者の進路や将来への意識変化をアンケート
今回のイベントで、ミダス財団は参加した生徒たちにアンケートを実施しました。参加前と後では、進路や将来への意識の変化を調べて、今後の施策に生かす考えです。
イベントに参加した女子生徒の中から、研究者や起業家など社会をリードしていく人材が生まれるかもしれません。
自分の限界を決めず、自分が本当にやりたいことを見つけること。その一歩を支えることが、多様性や日本社会の活力向上につながります。
【参考文献】
「なぜ地方女子は東大を目指さないのか」江森百花、川崎莉音著、光文社新書