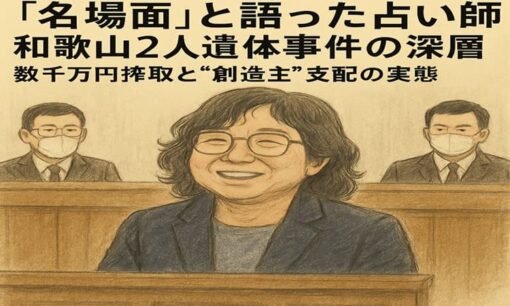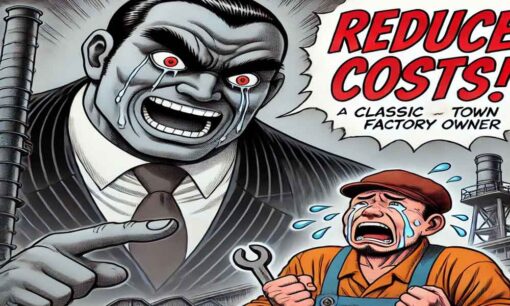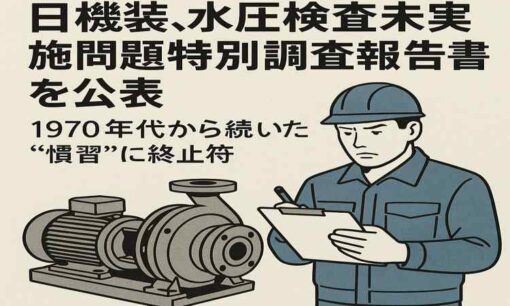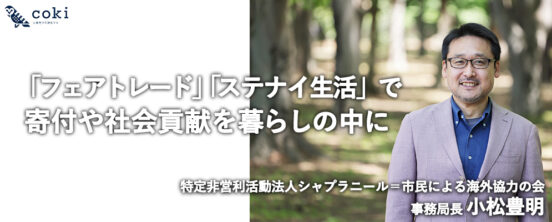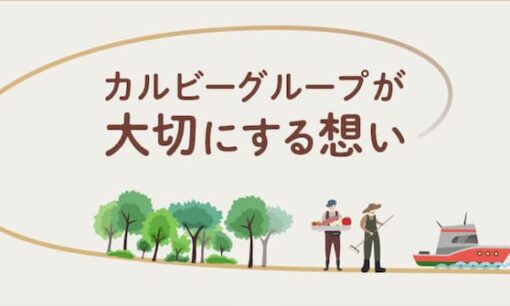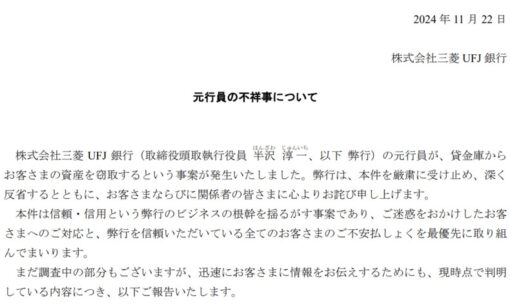時価総額5000億円未満の企業は義務化見送りを検討、制度の根幹に揺らぎも

金融庁は、2027年3月期から段階的に導入を予定していたサステナビリティ情報の開示義務について、当初想定していた「すべての東証プライム上場企業」を対象とする方針を見直し、企業の規模に応じた段階的導入に舵を切った。2025年7月7日付の『日本経済新聞』(電子版・有料会員限定)が報じた。
これまで、2027年3月期に時価総額3兆円以上の企業(約70社)から開始し、翌年以降、1兆~3兆円(約100社)、5000億~1兆円(約100社)、そして最終的には5000億円未満のすべてのプライム企業(約1350社)に義務化を拡大していく計画だった。
しかし金融庁は、最終段階の5000億円未満企業への一律適用について、義務化の見送りも含めた再検討に入った。背景には、EUでも中小企業への開示義務を緩和する動きが出ているほか、日本国内でも規模が小さい企業に対する「過度な負担」との懸念が根強くあったことがある。
外国人投資家比率と開示ニーズ、政策判断の軸に
義務化の見送り対象とされる中小規模の企業群では、外国人株主比率も相対的に低い。金融庁によると、外国人持株比率が3割以上となる企業は、時価総額5000億~1兆円未満の層で約45%、3000億~5000億円では30%弱にとどまる。サステナ情報の主要な利用者とされる海外投資家の「開示ニーズ」が限定的であるとして、政策判断に反映されたかたちだ。
一方で、時価総額が大きく、外国人投資家が多数を占める企業にとっては、国際的な水準に足並みを揃える意味でも、開示の義務化は避けられないとみられる。
会計士や実務家の現場からも賛否両論
企業会計や開示支援の現場では、今回の方向転換について「現実的な対応」と受け止める声がある一方、「大企業と中堅企業の情報格差が広がる」との懸念もある。ある会計士は、「仕事としては開示が進むほうが良いが、正直言って必要性を感じていない企業も多い」と率直な見方を示した。
また、プライム市場の要件に組み込まれることを前提に、社内体制を整えてきた企業にとっては、今回の見直しが「拍子抜け」に映る側面もある。
「誰のためのサステナか」投資家偏重の論理に潜む構造的限界
今回の制度見直しで繰り返されたのは、「海外投資家の比率が低い企業には開示の必要性が薄い」との論理だった。だが、こうした考え方は、サステナビリティ情報を“資本市場のためだけ”に位置づけている点で、そもそもの理念と乖離がある。
ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)やGRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)など、国際基準でもサステナ情報は単なる財務情報の補完ではなく、「ステークホルダーとの対話手段」として定義されている。すなわち、情報開示は投資家だけでなく、顧客、従業員、地域社会といった企業を取り巻く多様な関係者に対して「説明責任」を果たす行為である。
ある中堅上場企業の経営者は、「採用や新規取引先からの信頼を得るうえで、人的資本や環境への姿勢を示すことが当たり前になってきた。制度の有無ではなく、企業としての姿勢が問われている」と話す。
義務か任意かにかかわらず、企業の信頼やブランド価値はサステナ情報の中身と真摯さによって形成される。「投資家に必要とされないから開示しない」という議論では、企業価値の本質を見誤りかねない。
制度に先んじていた企業たち 開示を“信頼資本”と捉える姿勢も
制度的な義務化が進まない一方で、実はすでにサステナ情報の開示に取り組む企業は増えている。特に、外資系顧客を抱える製造業や、大学・自治体と連携する地域企業の中には、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)や人的資本の指標を自主的に開示する例も見られる。
たとえば、ある地方の中堅企業は、温室効果ガス排出量や労働災害発生件数、女性管理職比率などを自社ホームページ上で公表。営業活動ではこれが信用の担保となり、環境認証や大型発注の前提条件として機能しているという。
こうした企業にとって、今回の「義務化見送り」はむしろ機会の拡大と捉えられている。「制度がない今こそ、他社より先に開示することが差別化になる」(東証プライム上場・非製造業IR責任者)との声もある。
開示を“やらされるもの”ではなく、“企業価値を高める手段”と捉える企業と、制度がない限り動かない企業。その差は、制度が緩やかになる今後こそ、かえって広がっていくのかもしれない。