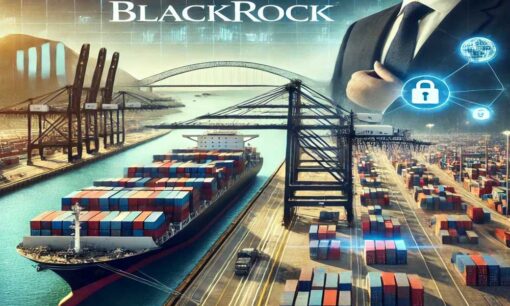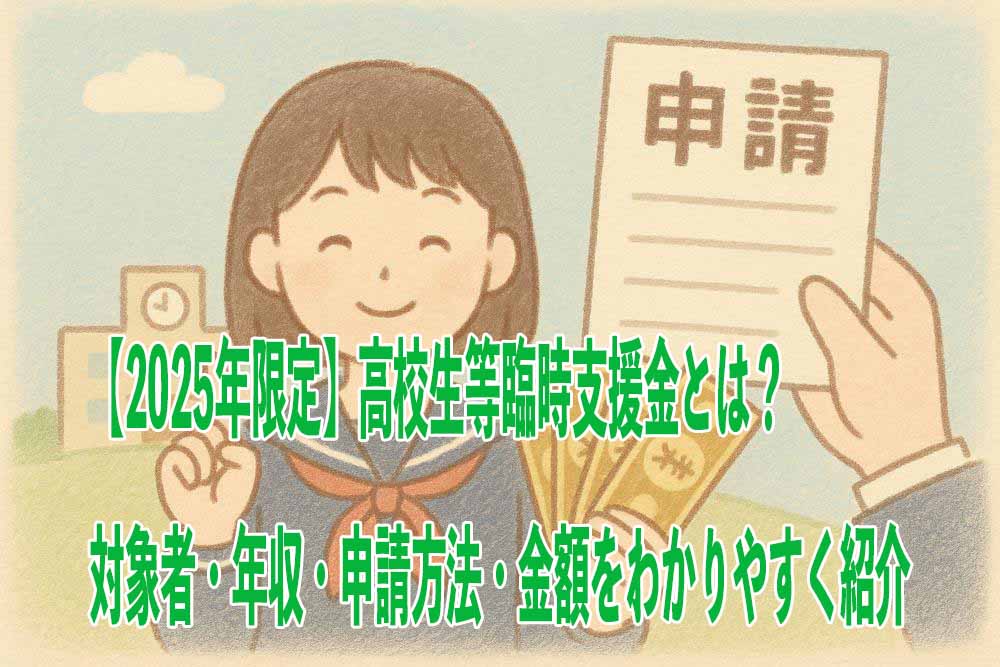
2025年度に限り、文部科学省は「高校生等臨時支援金」を創設した。従来は支援の対象外とされていた世帯に対して、授業料相当の支援を行うもので、年収910万円超の中間・高所得層にも最大11万8800円の補助が適用される。授業料無償化の本格実施(2026年度)に先駆けた経過措置として注目される本制度について、対象者、金額、申請手続きなどの詳細を解説する。
高校授業料支援を“拡大”──制度の概要
文部科学省は2025年度(令和7年度)に限り、臨時的措置として「高校生等臨時支援金」制度を創設した。これは、既存の「高等学校等就学支援金」では対象外とされていた中間所得層以上の世帯に対し、授業料相当の補助を行うものである。
従来の就学支援金制度では、おおむね年収910万円未満の世帯が対象とされてきたが、物価上昇や教育費負担の増加を背景に、年収910万円を超える世帯でも家計の圧迫が無視できなくなっている。こうした現状を踏まえ、授業料無償化の対象を全世帯に広げる2026年度の制度改革に先立ち、経過措置として当該支援金の運用が始まった。
支給額は最大11万8800円、国公私立で一律
支給額は、国公私立を問わず年額上限11万8800円とされる。この金額は、従来の「就学支援金制度」における共通基準額と同等である。授業料そのものが補助対象となるため、実際に支給される金額は、学校種別や授業料の実額によって変動する可能性がある。
なお、就学支援金制度では、年収590万円未満の世帯に対しては年額最大39万6000円(私立・全日制)の支援が行われているが、臨時支援金はあくまで中間〜高所得層の「制度の谷間」を補う役割を担う。
対象となるのはどのような世帯か
「高校生等臨時支援金」は、以下の条件をすべて満たした世帯が対象となる。
- 高等学校等(※)に在籍していること
- 「高等学校等就学支援金」の申請を行っていること
- その結果、就学支援金の「対象外」と判定されていること
※高等学校、専修学校(高等課程)、高等専門学校(1~3年生)などが該当する。
所得の目安としては、住民税の「所得割課税額」に基づいて算定されるが、概ね年収910万円を超える世帯が臨時支援金の対象となる可能性がある(扶養親族の人数によっては前後する)。
支援金を受け取れないケース
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の支給対象外となる。
- 就学支援金の申請を行っていない世帯
- 就学支援金の対象と判定された世帯(年収910万円未満相当)
- 高校を卒業している生徒、または在学年数が基準を超えている場合(全日制:3年、定時制・通信制:4年)
- 専攻科・別科・科目履修生・聴講生
なお、専攻科については別途支援制度が用意されている場合があるため、各学校への確認が必要となる。
申請方法と注意点──まずは「就学支援金」の申請を
臨時支援金を受けるには、前提として「高等学校等就学支援金」の申請を行っていることが必要である。申請していない場合は、たとえ年収が高くても臨時支援金の対象にはならない。
申請の流れは以下の通りである。
- 就学支援金の申請を行う(学校経由)
- 就学支援金の対象外と判定される
- 臨時支援金の支給決定通知が届く
- 必要に応じて継続申請を行う(年度途中転校・再申請等)
申請受付や支給開始の時期は各学校により異なるため、詳細は在籍校からの案内を確認する必要がある。
令和7年度限りの制度──“見逃し”を防ぐには
本制度は、2025年度(令和7年度)に限って実施される臨時的な措置である。2026年度からは、高校授業料無償化の本格実施により、現行の就学支援金制度そのものが見直される予定となっている。
一方で、制度の谷間に位置していた中間・高所得層が公的支援を受けられる初の制度でもある。支給対象となる可能性がある世帯は、「就学支援金の申請の有無」を早期に確認し、手続きを漏らさないよう注意が求められる。