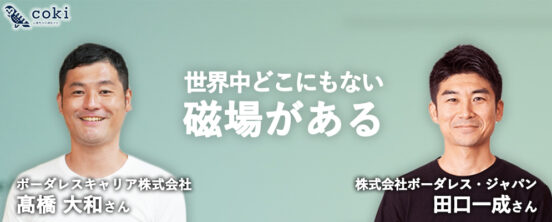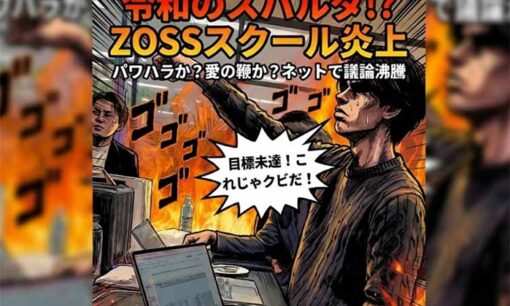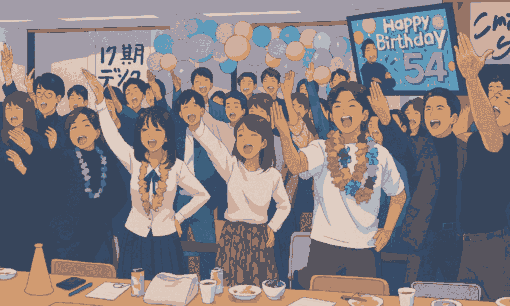「技術立国を捨てる気か」「これで日本は終わる」。12月5日夕方、政府・与党が「研究開発税制の縮小」を検討中との速報が流れると、ネット上は怒りの声で埋め尽くされた。物価高や人手不足であえぐ企業から、虎の子の研究資金を奪うような政策に見えれば、反発も無理はない。
だが、感情的に石を投げる前に、少し冷静になってほしい。実はこの騒動が起きる半月前、11月26日の時点で、河野太郎氏がこの税制の「不都合な真実」を淡々と指摘していたことをご存知だろうか。
彼がXに投稿した内容は、今回政府が大ナタを振るわざるを得なかった“決定的な理由”を物語っていた。
巷の怒り vs クールのなデータ
世間の常識はこうだ。「減税をして企業を応援すれば、研究が進み、イノベーションが起きる」。 しかし、河野氏が11月に提示した事実は、その常識を根底から覆すものだった。
彼が指摘したのは、「見せかけの数字」だ。
「適用企業の試験研究費の増加割合はこの2年間で0~3%というのが最も多く(中略)物価と人件費の上昇が3%であったことを考えると、適用企業の試験研究費の増加にこの政策が寄与したとは言えません」 (河野太郎氏 11月26日の投稿より)
ここにあるのは冷徹な計算だ。企業は「研究費を増やしました!」と申告して減税を受けている。しかし、その増えた分(約3%)は、昨今の物価高や賃上げ(約3%)とほぼ同水準。 つまり、「インフレで高騰した電気代や人件費を払っただけで、研究の実質的な規模は1ミリも拡大していない」のだ。
それにもかかわらず、国は「よく投資した!」と減税のご褒美を出し続けていた。約1兆円もの国費が、イノベーションの誘発ではなく、単なる「企業のインフレコスト補填」に消えていた疑惑。これが「効果が不透明」と断じられた最大の要因だ。
「のほほんと延長」への強烈な皮肉
さらに河野氏の投稿を読み解くと、制度の欠陥はこれに留まらない。下がっても貰えるザル制度になっていたこと。現行の仕組みでは、そもそも試験研究費が減少していても対象になるケースがある。また、偏る恩恵であったこと。減税額の9割は資本金1億円超の大企業だった。さらにその4割は自動車と化学産業が占めるようだ。
スタートアップ支援というよりは、巨大企業への既得権益化している実態。河野氏はこれを「のほほんと延長するのではなく」と独特の表現で切り捨て、「効果がない部分は廃止・縮小」すべきだと明言していたのだ。
これは「撤退」ではなく「選別」だ
12月の「研究開発税制縮小」という見出しだけを見て悲観するのは早計だ。 11月の河野投稿とセットで読み解けば、政府の意図は明確になる。
漫然とした「全方位のバラマキ」はやめる。その代わり、物価高を乗り越えてでもリスクを取り、本気で投資を増やす企業や分野だけにリソースを集中させる。 今回のニュースは、日本の科学技術を切り捨てるものではなく、長年放置されてきた「制度疲労」への荒療治だったと言えるだろう。