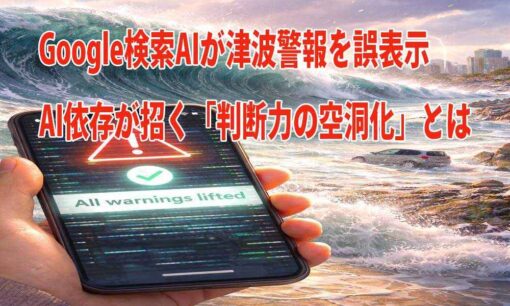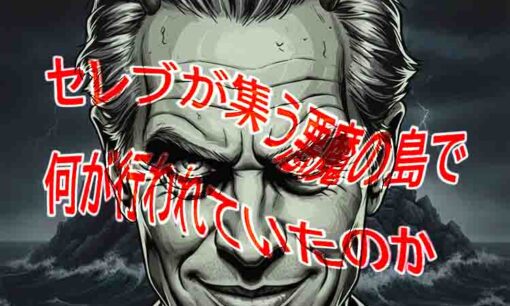テレビ朝日の報道によると、冬の節電方法として「厚着をして暖房器具の使用を控える」と答えた人が最も多く、室内暖房の利用を我慢して光熱費を抑える傾向が強まっているという。その一方で、電気を使わず寒さを軽減する工夫や、断熱素材を活かした商品が注目を集めている。本稿では、暖房機器以外で実践できる防寒策と、それが家計・社会・環境にもたらす効果を整理する。
冬の節電、鍵は「暖房に頼らない時間をどう快適にするか」
東京都心でも気温が5.1℃と強い冷え込みを観測し、暖房費への懸念が高まっている。
「とにかく暖房を我慢する」のではなく、住宅性能や生活動線を見直すことで、電力使用を抑えながら快適さを保つ方法が求められている。
住宅の「弱点」を断熱で補い、暖房効率を高める
窓や出入口は熱の出入りが大きい場所であり、冷気遮断が有効だ。普段使いのカーテンの内側に挟むだけの断熱ライナーが人気という。
住まいの冷え対策として、例えば次のような工夫がある。
・厚手カーテンを天井付近から床まで垂らす
・カーテンと窓の間に空気層を確保する
・玄関や廊下など、風の通り道を遮断する
家庭におけるエネルギー消費の中で暖房が占める割合は約2割。冷気の侵入と暖気の流出を抑えられれば、暖房に頼らず室温を維持しやすくなる。
身体を温める工夫で「暖房の稼働時間」を短縮
暖房機器に頼り切らず、身体そのものを温める工夫も欠かせない。
具体策:
・足元対策(靴下+スリッパ)で体感温度を底上げ
・ブランケットやひざ掛けを常備
・温かい飲料・食事で内側から保温
・入浴後の冷え込みを衣類で速やかにカバー
自治体の試算では、暖房の設定温度を1℃下げる、使用時間を短縮するといった取り組みだけで、年間十数kgのCO₂削減と数千円規模の光熱費抑制につながるとされている。
暮らし方・動線の見直しで “電気を使わない暖かさ” を作る
生活の中心となる部屋を決めて、暖かい空気を逃がさないことが重要だ。
・扉を閉め、暖気を居室に留める
・昼間は日差しを取り込み、夜間はカーテンで熱を守る
・寝具や衣服を多層化し、深部体温を保持
「どの部屋を温めるか」よりも、「どこで過ごすか」を選ぶことが節電への近道となる。
暖房機器に頼らない選択がもたらす環境・経済の効果
地球環境への貢献
日本の電力は火力発電への依存度が依然高く、冬季は特に需要が集中する。
暖房の負荷を減らせば、電力ピークを抑え、燃料消費や温室効果ガス排出の抑制につながる。
家計・経済の安定に寄与
暖房使用を日々数時間減らすだけでも、月数百〜数千円の節約が期待できる。
断熱・保温アイテムなど小規模投資なら短期間で回収できるケースが多い。
省エネ投資は、長期的に光熱費上昇リスクを緩和する“家計の保険”となる。
国の支援制度を活用して断熱改修を進める
初期費用が課題となる断熱改修は、国の補助制度により後押しされている。
主な制度(代表例):
● 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
・高性能な断熱材や窓・ガラス・玄関ドアの導入を補助
・補助率は費用の3分の1、戸建て上限120万円/集合住宅上限15万円
(年度により見直しあり)
● 住宅省エネ2025キャンペーン
・三省(国土交通省・経産省・環境省)連携の省エネ支援
・窓や外壁、床などの断熱改修、エコ住宅設備の導入を対象
・事業ごとに補助額や要件が設定
制度活用のポイント:
・工事着手前に申請が必要
・対象建材・設備には性能条件がある
・国と自治体の補助は併用できる場合もあるが重複補助に注意
断熱性能を高めれば、暖房に頼らず過ごせる時間が自然と増え、節電と快適性の両立が近づく。
まとめ:節電と防寒は暖房だけでは成立しない
本稿では、
・住宅の断熱対策
・身体を温める工夫
・生活動線の最適化
・国の支援制度の活用
という四つの視点から暖房に依存しすぎない冬の暮らし方を整理した。
今冬は、
冷気を入れない
身体を温める
暮らし方を整える
支援制度も活かす
これらを組み合わせることで、我慢ではなく“賢い節電”が実現できる。
家計にも環境にも優しい選択が、これからのスタンダードとなりつつある。