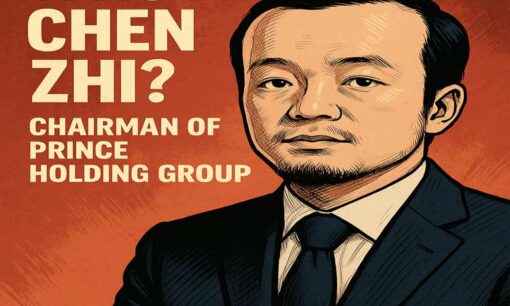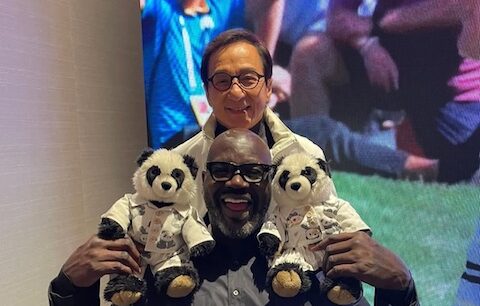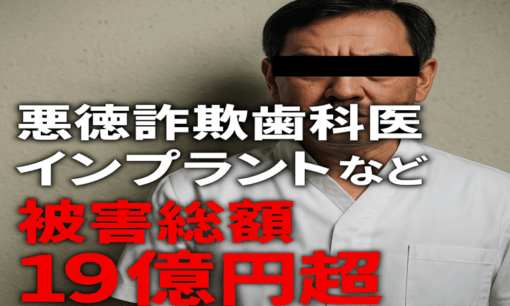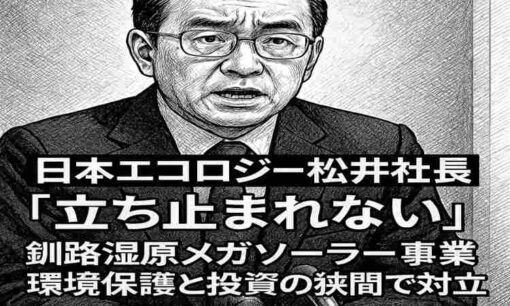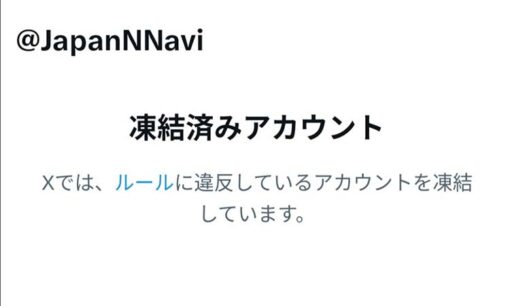高市首相の台湾有事発言に反発した中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた。中国の旅行会社は団体ツアーを次々と停止し、SNS上には「日本行きを取りやめる」という投稿が増えている。
その影響は即座に日本各地へ広がった。
和歌山・白浜の温泉旅館では、中国人69人の団体客がまとめてキャンセル。大阪では、民泊運営者・林伝竜氏のもとで600件を超える予約が消滅し、利用者の半分を占めていた中国人客のうち8割が離脱した。
しかし今回の騒動で最初に浮かび上がったのは、「日本の観光業者が困っている」という単純な構図ではない。
むしろ、最初に苦境へ追い込まれたのは、日本在住の中国人たちだったのではないか。
中国人が中国人を迎え、中国人の店を回る 「一条龍」の仕組み
インバウンドの裏側では、ここ十年で「一条龍(イーティアオロン、一匹の龍)」と呼ばれるモデルが急拡大してきた。
これは訪日中国人の旅程を“最初から最後まで”中国資本だけで完結させる仕組みだ。
クルーズ船、チャーター便、バス会社、免税店、ホテル、飲食、体験ツアー。
これらを中国系企業が一気通貫で押さえ、旅行者をネットワーク内部で囲い込む。言い換えれば、
「中国人が中国人を案内し、中国人の施設を使わせ、中国人の店で買い物させる」という完全循環型モデルである。

SNSでも、次のような冷ややかな声が広がる。
「恩恵を受けていたのは一条龍を運営する中国系民泊や旅行手配会社。日本は通過点でしかなかった」
つまり今回の渡航自粛は、この“内向きの中国人向けビジネス網”こそを直撃した形だ。
「仕事が消えました」在日中国系手配会社の悲痛な声
実際に、一条龍の一角を担う在日中国系手配会社の担当者は、今回の状況を次のように語った。
「昨日まで8割が中国のお客さまでした。でも渡航自粛が出た瞬間に電話が鳴りやみ、翌日にはキャンセルの山でした。私たちは日本で頑張って働いているのに、政治の問題で全部吹き飛ぶ。正直、もうどうしたらいいかわかりません」
別の関係者もこう漏らす。
「日本のホテルの予約も、食事の手配も全部こちらが一括で回してきた。中国の客が動かないと商売そのものが存在しなくなるんです」
観光地のフロントよりも早く悲鳴を上げたのは、観光の“裏側”を支えてきた彼らだった。
日本不在のインバウンド構造
観光はもともと季節や政治情勢に左右される“水物産業”である。しかし一条龍モデルは、そこにさらに特殊な脆弱性を付け加えた。
旅行動線のすべてを中国資本が握っていたため、
日本はただ「場所」を提供していただけであり、旅行消費の大部分は中国系ネットワークの内部に落ちていた可能性が高い。
製造業では“脱中国依存”が進みつつあるが、観光だけは依然として中国依存が続いてきた。その構造が、渡航自粛という政治的な一撃であっけなく露呈した。
では、日本はどう向き合うべきなのか
今回の騒動は、日本経済にとって痛手である一方で、“観光立国”の在り方を考え直す契機にもなり得る。
観光客が多ければ多いほど地域に迷惑が集中するオーバーツーリズム問題は、コロナ前から各地で指摘されてきた。
実際のところ、中国人観光客が日本に押し寄せることで大きな利益を得ていたのは、中国資本のネットワークに属する事業者たちだった、という構図も捉え直されている。
つまり、「中国人観光客が来なくなって最も困るのは誰か」という問いは、今回明確になったように見える。
“歓迎すべき事態”という逆説と、日本が取るべき方向
中国人観光客が押し寄せることで恩恵を受けてきたのが主に中国系事業者だったことを思うと、今回の急減は、実は多くの日本人にとって“歓迎すべき調整局面”なのかもしれない。
もちろん観光産業全体が冷え込むことは避けたい。
だが、これを機に、日本企業にも、日本人にもきちんとお金が落ちる仕組みを作り直すこと。
地域と日本社会に利益が循環するインバウンド構造を育てること。
これこそが長期的には日中関係の安定にもつながるはずだ。
一条龍モデルは中国人によって中国人のために構築された“独自の観光経済圏”だった。
その歪みが露呈した今こそ、日本は観光の主導権を取り戻す時期に来ている。