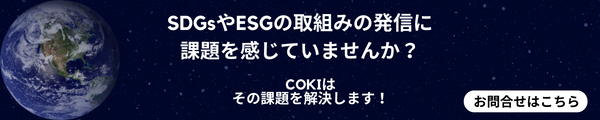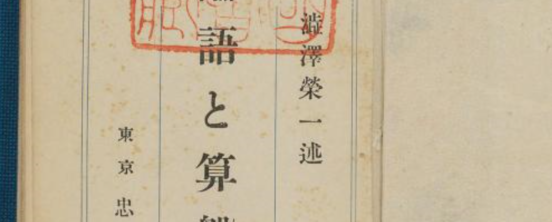©Studio Ghibli
気候変動による異常気象の多発、貧富の格差拡大、感染症の猛威の中、相変わらず人類は目の前の利害を巡る闘争に明け暮れている。このような中、世界共通の目標であるSDGs2030アジェンダの達成に向け、残された時間が少なくなってきた。我々のステークホルダーが地球規模に広がった今日、SDGsの取り組みを加速化するには、やはり資本や企業の力は重要であり、ESG対応企業によるさらなるイノベーション(創造的破壊)が期待されている。では具体的にどうするのかと言ったとき、実践にあたっての分かりやすいアイコン(イコン)があったほうがよい。ナウシカは間違いなくその候補の一人となり得るだろう。人間と自然の調停者ナウシカの行動を理解すれば、SDGsの実践方法が見えてくるのではないか…。ところが、である。
「ナウシカ」の真実
「風の谷のナウシカ」マンガ版の深み
世の中に周知されているアニメ版ナウシカは、彼女の捨て身の贖罪的行為によって神性を帯びてしまい、かえって生身の人間との繋がりが断たれてしまう。一方で、アニメの原作とされているマンガ版は、アニメ版公開後、制作を継続し10年かけてようやく完結に辿り着いていて、そこには別のナウシカ像がある。言い換えれば、ナウシカの真実はむしろマンガ版にあるといってよい。そこで、本稿では、着手から12年以上かけて完結した、マンガ版ナウシカの深みで、SDGsやESGを実践するとしたら?という思考実験を試みてみよう。驚くべきことであるが、純粋に作品として読んでも、これはもはやマンガの範疇を超えている。戦争という人間の極限状況を背景に、浮かび上がらせた地球の生命と死の叙事詩といってよいだろう。本書は、人類にとってのステークホルダーとしての地球、そこに生息する生命全体の絡み合いを高いレベルで包摂しているので、実践方法を考えるには最高の教材なのだ。
アニメ版とマンガ版の差異
まず、アニメ版のシーンで我々の共通の記憶を呼び戻そう。
戦争の道具に利用され、囮として飛行ガメにつるされた王蟲(おうむ)の幼生を救い出し、蟲とともに甕から降り立ったナウシカは、幼生を王蟲の群れに返そうする。小さな影、ナウシカは、蟲の大群を前にひとり心を開き、ただ静かにたたずんでいる。しかし、人間の所業に怒狂う王蟲は止まることを知らず、山のようなうねりとなって迫り、ナウシカは天高くはじき飛ばされる。あわれナウシカは激しく地面にたたきつけられて、あっけなく落命する。
風の谷の子ども:「姫姉さま、死んじゃった・・・」
大ババ様:「身をもって、王蟲の怒りを鎮めてくだされたのじゃ。身をもってあの子は谷を守ってくれたのじゃ・・・」
♪~ナウシカ・レクイエム(Dies iræ+遠い日々)~
クロトワ:「な、なんだこの光は!?」
大ババ様:「なんといういたわりと友愛じゃ。王蟲が心を開いておる。子どもたちよ、わしのめしいた目の代わりによく見ておくれ・・・」
「・・・(急に低い声で)その者青き衣(ころも)をまといて金色(こんじき)の野に降り立つべし。(失われし大地との絆を結びついに人々を清浄の地にみちびかん)・・・古き言い伝えはまことであった・・・(涙々)」
ナウシカの犠牲的行為により、群れを成す王蟲の目は怒りの赤から、穏やかな青に徐々に変わっていき、大地は青一色に覆われた。ここで戦争により大地を汚した人間の贖罪が成立するとともに、ナウシカは神話の人となって生まれ変わる。
さて、メーヴェを操り、空を駆ける神がかりなアニメ版と違い、マンガ版のナウシカは、苦悩しつつ我々と同じ地面を這ってくれる側面を持つ存在だ。モノカラーのマンガであるがゆえに、戦争の残虐な殺りく行為や、人が蟲に喰われるシーンもかえってリアリティがある。実際、ナウシカが王蟲に食べられるという衝撃的な場面もある。
このマンガ版ナウシカ1巻目が発表されたのは、1982年のこと。ソ連の最高権力者ブレジネフの死去もあって、米ソの冷戦体制が変わりはじめたタイミングだった。1986年には、チェルノブイリ原発事故が起こり、ソ連の技術的権威も失墜。ついに1989年にはベルリンの壁が壊され、1991年にソ連が崩壊する。しかし、冷戦が終わっても、覇権構造が変わっただけで、平和は訪れず、戦争は終わらない。1992年には、内戦によってユーゴスラビアが解体した。この間『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で我が世の春を謳歌していた日本では、1990年に一転、バブルが崩壊し、右肩上がりにものごとが良くなっていくという幻想は霧消した。よく見え始めた視界には環境破壊やテクノジーへの不信といった発展の影の部分が浮き上がってくる。そういった時代の瘴気を吸収しつつ、映画製作による中断をはさみながらも、最終巻7巻目が完了したのは1994年だった。
結果的にマンガ版ナウシカを通しての宮﨑駿氏の問いは、アニメ版公開後10年の歳月をかけて深められ、一つの時代を跨いだことにより、かえって普遍性を持つに至ったとも言える。
マンガ版では、ナウシカが様々な登場者たちとの対話を通して、自ら問いを発し、答えを見出ていく道程に光が当てられている。戦争の業火の中で、ナウシカ自身が生命の意味、この世界成立の真実に迫っていくという物語が基調なのだが、一方で登場者たちも、ナウシカと共に行動しながら、気づきを得て個々の囚われから解き放たれていくというサブストーリーが絡み、物語世界の隅々までの包摂度は高い。
物語世界の背景

ユーラシア大陸の西のはずれで起こった産業革命を契機に、人類が高度な産業文明社会を築いて1000年後(西暦2800年頃か)。発達した科学技術は頂点に達し、工学、化学やバイオテクノジーにより、人類は機械の製造だけでなく、新しい生命の創造、改変や長寿化など、自然環境を自由自在に操れるようになった。ところが、技術がいかに高度化しても戦争は止むことはなく、ついには強力な生物兵器、巨神兵を生み出し、そのプロトンビームによって、一瞬にして世界は火の海となり焼き尽くされた(火の7日間戦争)。したがって、人類が創り上げてきた過去の科学文明は壊滅、その後さらに1000年(西暦3800年頃)たっても再生されることはなかった。火の7日間戦争以降、細々とたそがれの日々を生きていくことになった現人類は、過去の文明のスクラップを集め、兵器を作り、また戦争を始める。
一方、文明と戦争の遺物である有害物質を吸収して成り立つ生態系は、腐海という瘴気をまき散らす森を生成し、巨大菌類からなるその森は胞子を飛ばしながら次第に拡大していく。腐海は、300年に1回、大海嘯という突然の大膨張を起こし、人間の住める場所はどんどん狭まっていくのだった。
そんな中でも、狭い土地を巡って人々は争いをやめず、かつての技術の残滓から粘菌を作り替えた生物兵器を開発する。しかし、科学者たちの読み誤りから、凍結していたはずの粘菌が試験管を破り、叢を成して大膨張を始める。ここで、また新たな大海嘯が勃発したのだ。
それでも、人類は戦争をやめず、わずかな人が住める場所を奪おうとして、また戦うのである。本書には、大局を忘れ、常に目の前のひっ迫した課題にとらわれて止まない愚昧な人間の姿が嫌と言うほど描かれている。
マンガ版ナウシカの登場者構成

マンガ版では、残された土地を巡るトルメキア軍と、土鬼(ドルク)諸侯国軍(マンガ版で登場)の戦争(トルメキア戦役)が物語の大きな背景となっているが、ここで本稿を進めるにあたって必要な程度にマンガ版における登場者の設定について述べる。
ナウシカ:軍事大国トルメキアの辺境にある小部族国家、風の谷の族長ジルの娘。(以下マンガ版の設定)風の谷は、トルメキアと軍事同盟を結んでおり、トルメキア軍の出陣時には、部隊に組み込まれ行軍する。ナウシカは、メーヴェに乗り、ガンシップ(戦闘機)を1機引き連れて、トルメキアの敵、土鬼諸侯国軍殲滅のため駆り出される。そして、対敵、対見方内のいたるところで発生する無意味な軋轢や闘争をやめさせるべく奮闘する。ナウシカは、難民の中のひとりの乳児、一匹の蟲といった生命を救いながら、自身の命題である腐海の秘密を探るべく、敵対する戦争当事者たちの間を賢く、巧みに動き回る。
クシャナ:トルメキアの正統な系統の王位継承権を持つのは、王女クシャナである。しかし、クーデターで政権を奪った現王、ヴ王や他の王子から命を狙われている。今回の戦役では、精鋭部隊をはく奪されたうえ、全滅必至の別動隊での行軍を命じられる。さらに、その軍には、応援と称して、軍参謀を装う刺客クロトワを送り込まれる。クシャナとすれば、盛られた毒を母王妃が代わりに飲み、狂人にされたことへの怒りが行動の原動力だったが、軍事同盟によって同行したナウシカに感化され、次第に国家統治の王道へと目覚めていく。
王蟲:森の主とも言える王蟲は、マンガ版ではナウシカと対話することができる存在である。そして王蟲の口から、自分たちのミッションや粘菌が暴発して起こる大海嘯のヒントが明かされる。
粘菌:土鬼軍の生物兵器としてバイオテクノロジーによって作製されたもの。土鬼軍は、トルメキア軍の陣中で粘菌による腐海を急拡大させ、敵を一網打尽にしようという作戦を企てる。人工粘菌は、その膨張力によって、破壊活動を行って死ぬ、死ぬために生まれた生物だ。ナウシカや王蟲には、粘菌の恐怖、悲しみが分かる。ナウシカはこのような粘菌のことを「あの子」と呼んでいる。
巨神兵:旧人類が戦争最終兵器として活用すべく、様々なタイプが生産されていた。火の7日間後に全個体が自然崩壊したが、そのうちの1体だけが、成長を停止されたまま工業都市国家ペジテの地下に埋まっていたのだ。トルメキアと土鬼は、この究極の生物兵器を巡って、奪い合いを演じるが、蛹の状態の巨神兵を土鬼軍が持ち出すことに成功する。
森の人(マンガ版で登場):文明に背を向け、腐海の中で自然と共に生きることを選択した人々。腐海で暮らしているために、森の実態をよく知っている。鳥の人、ナウシカに一体感を持ち、一緒に森に住まないかと呼びかける。
トルメキア軍:ヴ王率いる軍として、広大な土地を持つ土鬼(ドルク)諸侯国の攻略作戦を展開する。対外的には、ヴ王により軍の統制はされているものの、内部では王位継承を巡る王子3人王女1人(前述クシャナ)が争っている。ヴ王の狙いは、領土拡大もあるが、土鬼の首都シュワの墓所に眠る永遠の生命にかかる技術を手に入れることで、王位を永遠のものとすること(子どもですら王位を譲りたくない)だった。
土鬼(ドルク)諸侯国軍:神聖皇帝(自称神聖)が、元のクルバルカ王をクーデターで倒し、政権を奪う。初代神聖皇帝亡き後、息子兄弟のうち皇弟ミラルパが神聖皇弟となって統治している。超常能力により、自らを神のごとく絶対権威化したうえ、僧団を活用し諸侯国を支配している。しかし諸侯国の国民は土着の信仰(アニメ版の、その者青き衣をまといて・・は大ババ様ではなく、諸侯のマニ族僧正の信仰の言葉として語られる。)を裡に隠しており、神聖皇帝に対して心からの忠誠を誓っているわけではない。一方で、皇兄はクーデターのチャンスを狙っている。自分ファーストでアイデアマンの皇兄は、元々の自国領と、トルメキアの領土を一瞬で手に入れる奇策を思いつき実行しようとする。
虚無:(マンガ版で登場)ナウシカの希望を破壊し、意味なきものにしようとする存在。ナウシカが悩みはじめると現れてきて、内面を抉る鋭い言葉で意思をくじこうとする嫌な奴。
墓所の主:(マンガ版で登場)土鬼の首都シュワにある墓所の中にいる、永遠の生命をもつ人工生命体。破滅を迎えようとする旧人類が、人類を復活させる夢を託して、バイオテクノロジーによって作製したもの。墓所の主は人類再生プログラムを運営しており、永遠の生命体であるがゆえに、旧世界や現世界の成り立ちの真相を具に知っている。
庭の主:(マンガ版で登場):善良な牧人の姿をした人工生命体の一種。人類再生プログラムの中で、庭はノアの箱舟のように、各種動物の種や、旧人類の文化遺産を保持する役割を担っている。この庭ができてすでに1000年が経過しているが、庭の手入れ、維持のためには、人手が必要となり、外から巧みに人を誘い込んでくる。
ナウシカは、このような登場者たちとの対話を通して、真実の探求を進めていき、破滅前の旧人類が生み出した、数千年越しの壮大な再生プログラムを次第に見出していく。そして腐海が広がる理由、300年単位で大海嘯が起こる理由。旧人類の図りごとや生命の成り立ちの秘密を突き止めるのだった。
これ以外も含めた、多くの人々や様々な蟲たち、人工生命体が入り乱れて物語は進行していく。大きく分けると、登場者のナウシカから森の人までを、現在の生を肯定するグループ、トルメキア軍から墓所の主を、現在の生を肯定しない(破壊するか、リセットするか)グループとに分けることができる。しかし、物語の進行プロセスで、生死善悪の同居、反転、循環もあって、単純な二元的対立ではないところにマンガ版ナウシカの深みがある。
特に、このマンガ版でナウシカに対峙する存在として、圧倒的に重要な意味をもつのが人類再生のカギを握る永遠の人口生命、墓所の主なのである。
永遠の生命体としての国家

滅亡の危機に瀕した人類が託した夢としての人工生命体
火の7日間戦争が起こるタイミングで、滅亡を免れないと悟った旧人類が最後に欲したのは、滅亡後に人類を再生することだった。そのために、いったん墓所という名のシェルターの中に人工生命体を作製し、人工子宮で新人類の卵を育成するという方法を取った。この卵を産み、保管し育てる役割を担うのが、永遠の生命体、墓所の主なのである。合わせて高度な知能を持つ墓所の主は、旧人類の技術遺産を受け継ぎ、生物の創出、改変を行う技術仕様書を作成することができる。これを実行に移していくのが墓所の教団に属する科学者たちである。
旧人類の叡知が詰め込まれた格納庫であり、人工頭脳でもある墓所の主は、汚濁にまみれた世界をリセットし、青き清浄な世界を創るプログラムを運用している。最終的に復活を遂げるのは、戦争をする闘争心を持たない善良な新人類である。戦争のない楽園、青き清浄の地では、人類は詩と音楽によって文化的な生活を営むことが可能となる。これはキリスト教におけるハルマゲドンを通過した後にに訪れる天国のような世界だ。
墓所は土鬼の首都シュワに位置しているが、その墓所を守るために存在しているのが、先述の神聖皇弟ミラルパであった。神聖皇弟がなぜ、神聖足り得ているかというと、人の心が読める超常能力だけでなく、化学テクノロジーによって200年以上の長寿が維持されているからだ。生体細胞を維持する特殊な薬液によって、ミラルパは生きながらえていた。しかし、その実態は墓所の主との契約によって、国を統治する権力と長寿の生命(永遠ではない)を与えられているにすぎなかった。墓所の主は、土鬼諸侯国の影の支配者でもあったのだ。
永遠の生命体としての国家と政治家
つまり、旧人類が永遠の生命体に意思を持たせたことによって、かえって人間がその支配下に置かれることになってしまった。この生命体はSFファンタジーの産物として片づけられもするが、生命体を国家として置き換えてみると心穏やかでなくなってくる。
法律を生み出す永遠の生命体である国家は、顔や虹彩、指紋などの生体認証や、マイナンバーなどの国民コードの付与により、確実な徴税のために次第に国民個々の財産の把握を実行するようになる。国家のDXが進むにつれて、一国民の思想や日常生活、財産状況の把握は技術的にますます容易になってくる。
一定の成熟を経た国家は、さらなるサステナビリティを希求し、法律を変え、統治を最適化していく。そして、国民の便益を図る大義名分のもと、権力の及ぶ範囲をじわじわと広めていくのだ。国力をつけた後には権益の外部への拡張も辞さない。
ただ永遠の生命体としての国家も政務執行ができるわけではないので、手足となる政治家(王)と、公務員(教団の科学者)を必要とする。政治家であれ、公務員であれ自然人がいったん法体系に組み入れられ、この生命体と法的関係を持ってしまうと、生命体のミッション達成のために働かざるをえなくなる。このため仮に戦争になっても厭とは言えず、戦争に加担して大義を執行せざるをえない。
さて、成熟した国家をドライブするのは言語化された大義である。その大義は当該国家にとっての正義だ。正義には論拠が必要となる。もし、その根拠となる宗教やイデオロギーが絶対的であった場合、賛同するものが絶対的善、賛同しないものが絶対的悪となる。絶対的悪は徹底排斥すべき対象となる。
このとき政治学者ハンチントンの言を俟つこともなく、文明間の衝突が起こる。特に国が絶対神に依拠する場合、衝突は苛烈なものとならざるを得ない。ユダヤ教の神と、キリスト教の神と、アラーの神という絶対神が接するエリアで紛争が絶えないのは必然なのだ。神を顕現するのは神の声を媒介する預言者なのであるが、同じ絶対神であったとしても、預言者の主張自体が絶対となり、他の預言者の言説を排除すことになるため戦争の種はもともと孕まれていることになる。(日本では、八百万の神、山川草木悉有仏性というぐらいで、超相対主義的な文明であるため、あまり感覚的にピンとこない)
ともあれ、現実の国家は良い人類を創造しようなどいう野心まではもっておらず、自身(自国)のサステナビリティの追求と主権の維持拡張に恋々としている存在である。その存立基盤が危うくなると困るからこそ、ステークホルダーとしての地球を大切にしようともする。この時公務員は国家の指揮系統に直属しているため、国家の利害と自身の利害はほとんど完全に一致しているが、政治家には別の思惑が絡んでくる。
もし、成熟した国家と政治家の利害が一致すれば、国家は強大になっていくが、多くの場合、利害は完全に一致しない。つまり、国家は永遠を希求するが、政治家の目的は自身の権力基盤の創造と維持なので、もともと軸がズレている。これは政治家生命が限られているがゆえに仕方のないことだが、相互に利害関係のギャップが発生するので、調整しながらの政治運営ということになる。
権力基盤が最大命題の政治家にとっては、場合によっては、地球や国家というステークホルダーよりも、自身の基盤を支えてくれる選挙民が最優先すべきステークホルダーとなる。本稿の文脈で言えば、化石資源由来の事業基盤を持つ選挙民の意向を反映させなければならない政治家としては、SDGsに前向きになれない理由が発生する。
SDGsの虚実

SDGsにかかるステークホルダー間の利益相反による足の縺れ
さらに一国の上位構造である国際社会は、先述のような人工生命体が複数集まって構成される世界だと考えてみよう。それぞれ永遠の持続性を求めているには違いないが、各国家の持続のためには相変わらず化石資源に依存し続けるしかない国家群と、再エネコストの低減に成功し化石資源依存から脱却しつつある国家群がある。これらの間では利害が衝突せざるをえない。
その利害が対立する国家群が集まった国連から生まれてきて、各国の大義を反映しつつ、調整された世界共通の正義の束がSDGsというわけだ。もちろん、個別国でみても化石資源依存産業に支えられる政治家と、非依存型産業に支えられる政治家間で利害調整をした上でのことである。これらの何重もの調整の中で、妥協点を探る中から生まれたSDGsは結果として、大人数が繋がる二人三脚のような内容にならざるを得なかった。
戦争を無くするということはさすがに書けないにしても、SDGs169の個々のターゲットへの踏み込み度合いはバラバラだ。部分的に個別指標はあっても、企業でいう管理会計的マネジメントはされていない。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal1.html
の21_SDG_indicator_data_list参照)
さらに、そもそもで言えばSustainable Development Goals(持続可能な開発目標)とあるように、未だに世界を開発するのだといっているし、対象国となるべき国を、上から目線で開発途上国と呼んでよいのだろうか(先進国を課題先進国と言い換えるのであれば、少しは許されようが)。
無論、SDGs設定に大きな意味はあるし、社会と関わる健全な企業であるならばその活動ゴールがそもそもSDGsなのだという便法も戦術的には正しい。そして、指標を出したことで、少なくとも2030年時点での達成度は把握でき、もう少し進化した次のアジェンダの策定には役立つだろう。しかしながら、結局は、問題解決をはかるというより実施データが取りまとめられ、次の目標を設定するという、目標設定すること自体が活動の中心になりはしないか。
国家や政治家の思惑が交錯するSDGsがこのような運用をなされているのは調整の知恵として妥当とも言えるが、肝心の実現性には疑問符が付く。そこで、我々としてはもっと実行力のある戦略を考える必要がある。
巨神兵の意味を再考する

巨神兵を資本に見立てるとどうなるか
次に、一見禍々しい存在である巨神兵について考察してみよう。巨神兵は、そもそもサステナブルではなく短期決戦兵器である必要がある。なぜなら高エネルギーを発する生命体が、長く生きながらえると地球自体を燃やし尽くし、消滅させてしまいかねないからだ。(火の)7日間でいったん地球を焼き尽くせば事足りるので、短命にプログラムされているというわけだ。
人類が行ってきた文明の創造とは、裏を返せば自由主義に任せた開発という名の破壊競争とも言える。地球の歴史46億年からすれば、枯れた植物が膨大な年数をかけ、折り重るように積み上げてきた化石資源を一瞬で燃やしてしまうほどのものだ。
地球を破壊し、化石資源を吸い上げ、化学物質の塊からなる構造物に変えた“豊かな文明”を築くアクションをイノベーション(創造的破壊)というわけだが、それを誘発したのはまさに資本という巨神兵なのだ。
ところが地球から見れば、イノベーションは創造的どころか、大いなる迷惑、単なるディスラプション(破壊)と言えるだろう。資本の力によって地球の破壊スピードは猛烈に早まった。太古の時代から熟成されてきた化石資源を消費することによって成り立つ文明が生み出したものは、一体何だったのかを改めて考える必要がある。都市がコロナ禍の緊急事態宣言により、虚ろなガラスが嵌め込まれたコンクリートの墓標群と化した時、これが我々の築いた文明の一端だったのかと感じた人もいたのではないだろうか。
巨神兵をお伴に戦うナウシカ
さて、またナウシカの話に戻ろう。アニメ版とマンガ版の大きな違いの中に、この巨神兵の扱いがある。アニメ版では、王蟲の大軍を殲滅するためにトルメキア軍の王女クシャナが使用するが、マンガ版ではまったく異なる役割を担う。巨神兵は、ナウシカを支えるパートナーになるのだ。
ある時、巨神兵を味方につけることができる可能性を感じたナウシカは巨神兵にオーマ(無垢)という名を与える。ナウシカ自身も、巨大でおどろおどろしい怪物でありながらも、心から自分に尽くすオーマに次第に愛情を持つようになっていく。そしてこの巨神兵は、ナウシカに褒められたいがためにナウシカの指示によって戦う。アニメ版と、マンガ版での巨神兵の扱いが違うことで、巨神兵は使い様であるというように、既成概念の転換が可能となるのである。
そもそもナウシカの戦いとは何だったのか?

人間存在の善悪を問うナウシカ
ナウシカは地球の浄化のために自ら犠牲になる高貴な王蟲たちの存在に胸を痛め、このような状況を巻き起こした人類の一人であることへの罪悪感が高まっていく。ナウシカが挫けそうになった時に現れるのが、虚無だ。
虚無:「王蟲のことは悲しまなくてもいいんだよ。みんなじきに(死によって)苦しみから解放される。」
ナウシカ:「でもちがう、やっぱりちがう」
虚無:「自分の足元をみてごらん死者ばかりじゃないか」
ナウシカ:「お前はとてもいやなにおいがする」
虚無:「他者をとやかく言える身か、自分の手を見るがいい。(血が付いている)その手は何だ・・・足元を見ろ、自分の足元を見ろ、死者の中にはお前が殺した者もまじっているんだ・・・いつまでも無垢な子どもでいようったって底がわれているんだ。王蟲はもう許してはくれまい・・・お前はおろかでうすぎたない人間のひとりにすぎないのさ。お前は人間のおとなだ。呪われた種族の血まみれの女だ。」
ナウシカ:「私たちが呪われた種族なのはわかっている。大地を傷つけ奪い取り。汚し、焼き尽くすだけのもっとも醜いいきもの・・・いまさら許しをこうて何になろう」
ここで罪悪感にさいなまれたナウシカは、生きていく意味を見失い、森の浄化のために犠牲となる王蟲に寄り添い、一緒に粘菌の餌となって死のうとする。ところがここで王蟲がナウシカを食べてしまい、物語はナウシカの望みとは別の展開となる。
生命の目的を問うナウシカ
ナウシカは、世界の成り立ちの秘密を握る墓所の主に出会う旅の途中で、その配下にいる庭の主に遭遇する。人類再生プログラムに協力する人工生命体、庭の主との対話によって、ナウシカは生命の目的という問題に直面する。
庭の主は、人類再生プログラムの運用に加担しているため、必然的に生命には目的があるという考えに囚われている。つまり生命は青き清浄な世界を創る目的を持っていると確信しているのだ。科学が力をもち、バイオテクノロジーが発達し、未来への拡張線が見えると、生命はより崇高な何かの目的のために資するものではないのか、という発想が生れてくるのかもしれない。
この既視感は過去にもあった。ヘーゲルはヨーロッパの産業革命の最中、テクノロジーの発展に喚起され、『絶対精神』に向かって発展する世界の歴史を構想した。「世界史とは自由の意識が前進していく過程であり、私たちはその過程の必然性を認識しなければなりません。……。(自由という)この究極目的へのささげものとして、地球という広い祭壇の上で、長い年月にわたって、ありとあらゆる犠牲が捧げられる・・・」(『歴史哲学講義』)ヘーゲルは崇高な目的に向かって矛盾や対立などの困難を乗り越え進むからこそ人間存在には価値があるのだと説いた。
人間は科学という自己拡張ツールを手に入れ、成功体験を積んできたことにより、いつの間にか自由な意思がめざすゴールがあるはずという目的思考に陥っていた。さらに、テクノロジーの高度な進化によって、ますます人類は発展するものだという確信は強固なものとなる。挙句の果てに生命を作り替え、作り出すことができるようになった結果、そもそも生命に目的を持たせることも可能だという考えを持つに至ったのだ。
庭の主も、当然に生命に目的がある方が正しいと考えている。
庭の主:「(欲にまみれた)そなたたち人間はあきることなく同じ道を歩み続ける・・何度もくり返された道を・・・この庭はすべてを断ち切る場所・・・彼ら(庭の先客)は生まれてはじめて安らかな喜びを感じている・・・」
主は、闘争と汚辱に満ちた世界を終わらせ、戦争のない清浄な心を持つ人類を創造するという目的の魅力をナウシカに語り、庭の主の下僕としてこの地に留まらせようとする。しかし、ナウシカはそれを否定する。
ナウシカ:「目的のある生態系 その存在そのものが生命の本来にそぐいません。私たちの生命は風や音のようなもの、生まれひびき合い 消えていく」
つまり、ナウシカはそもそも生命に目的などないのだという。
では、生命に何かの目的を達成する意味がないのであれば、そもそも生命の意味は何であるのか?新実存主義の哲学者マルクス・ガブリエルは「生きることの意味は生きること」だという。また、「命はこの世で価値を生み出す唯一のもの」(『つながり過ぎた世界』)だともいう。
ナウシカのこの問いは、科学が、生命自体をも扱えるものになったため、人間の意志が生命の在り方にも及ぶようになり、生命に目的を持たせる、つまり生命を手段として使うために生み出すことができるようになったことへの問題提起でもある。
絶望という名の生、希望という名の死
もう一つのナウシカの重要な問いかけは、人類が生きる希望とは何かというものだ。
人類を作り替えるべく、墓所の主は、仕様書をもとに清浄な新人類の卵をボコボコと無数に生み出し、育成している。人類を再生する壮大なプログラムはゆるやかに進行していくのだった。
そんな中、神聖皇兄ナムリスは、いよいよクーデターを決行し、皇弟ミラルパを暗殺。土鬼諸侯国軍を手中に収める。そして、巨神兵を奪取し、自国に持ち帰るが、自分自身は目覚めた巨神兵のプロトンビームでズタズタにされることとなってしまった。この結果、プログラム実行を守護する自国の王を失った墓所の主には、次の王が必要となったのだ。
この時、ヴ王とナウシカはそれぞれ別の理由からではあるが、たまたま同時に墓所の中に入り、鉢合わせすることになった。次の王を求めていた墓所の主からすれば飛んで火にいる夏の虫だ。墓所の主はヴ王とナウシカに呼びかける。
墓所の主:「子らよ、・・・自らの愚かさ故むなしく滅びた人間を代表し、そなたたちにつたえたい。長い浄化の時にそなたたちはいる。だがやがて腐海のつきる日がくるだろう。青き清浄の地が甦るのだ」
墓所の主は、ヴ王とナウシカに、新たな王として、人類再生プログラムに与しないかと呼びかける。これをナウシカは拒絶する。
ナウシカ:「・・身体が人口で作り替えられていても私たちの生命は私たちのものだ。生命は生命の力で生きている・・・私たちは、血を吐きつつくり返しくり返し、その朝を超えて飛ぶ鳥だ!! 生きることは、変わることだ。王蟲も粘菌も変わっていくだろう、腐海もともに生きるだろう・・・だがお前は変われない 組みこまれた予定があるだけだ・・・死を否定しているから・・・」
墓所の主:「お前にはみだらな闇の匂いがする・・・お前は危険な闇だ! 生命は光だ!」
ナウシカ:「ちがう!命は闇の中の光だ。すべては闇から生まれ闇にかえる。」
ナウシカは、どのような生まれ方をしようが、どんなに汚濁に満ちていようが、生命は一瞬の光だという。あり続けるものでないからこそ、苦しみの中に喜びもあり、生きとし生けるものを愛おしむこともできる。そして、生死を繰り返すことで、プログラムされていて変われない未来ではなく、変われるかもしれない存在であることにこそ希望を見出だすこともできるのだという。
ナウシカが教えてくれる愛憎を超えた慈悲
さて、ここでまた一つ問いが生まれる。そもそも欲にまみれ争いをやめられない人類を愛せるか?戦争の元になるのは愛憎の心なのであるが、愛とは何かに執着する心であり、どうしても執着するものを奪い合うことで、同時に敵を作り、憎しみを生む。憎しみはさらに憎しみを掻き立てる。とすると、その憎い敵さえも愛することができるのか?ということになる。そこで、そもそも人類はこうした欲から離れられず戦争を起こし、愚行を繰り返す存在として受け止めざるをえないという見地に立つしかない。どうしようもなくダメな人類なのではあるが、ダメであるがゆえにこそかえって、他者にも自身にも慈しみの心を持つことはできるのだ。
ナウシカに会ったヴ王は、血塗られた自身でさえ慈悲の対象であることを知る。ヴ王はナウシカに言う。
ヴ王:「気に入ったぞ、お前は破壊と慈悲の混沌だ」
ヴ王は、ナウシカが清浄な新人類にとっての否定者であるとともに、汚辱にまみれた生命に慈悲を差し向ける存在であることを指摘している。結局ヴ王は、墓所内での戦闘による爆風の中、盾となってナウシカを抱きかかえ死ぬ。
最後に、ナウシカは現人類が、新人類に切り替わる青き清浄の時代が来るという人類復興計画の一切合切を知るのだが、その計画にはとんでもなく重大な欠陥があった。現人類にとってはまったく希望をもたらすどころのものではなかったのだ。そこで、ナウシカは森の人と共に、真実を封印する約束をする。こうして、ナウシカは現人類に真実に反して希望を語りつつ、死に抱かれ汚濁に満ちた生の世界を選択し生きることになる。過酷な現実を知らずに済んだ現人類は、ナウシカの力により、一時の平和と目の前の希望を取り戻して、第7巻の話は終わる。宮崎駿氏は次のように語っている「・・・完結してないんですよ。体力的にも能力的にも時間的にも限界で、本当に這うようにして何の喜びもなく終わりましたね」。(『ナウシカ解読』インタビューより)
生を肯定することがかえって不安や絶望を抱えてしまうこともあるというナウシカの重い問いは、物語が完結していない(?)がゆえに、そのまま読者にナウシカが、問いごと憑依することとなる。ここまで読み込むとわかってくるのは、ナウシカはニーチェの『ツァラトストラ』のような生命の思想書なのである。結果として終わりまで読んだ読者は、真理の探究者ナウシカから、そのミッションを引き継ぐことになるわけだ。ナウシカのレトリックを使えば、「絶望とは希望の始まりだ」ということになるのだから。
結びにかえて~我々の戦いとしてのSDGsとESGの実践

資本としての巨神兵をESGに活用
最後に、本稿は実践が目的であり、問いで終わるわけにはいかないので、我々が取り得る有効な実践方法を考えてみよう。地球と地球に存在する生命というステークホルダーに対して、どのように報いていくことができるのか?それにはまず、我々自身が実行力を手にすることである。
それがまさに、マンガ版ナウシカがヒントをくれた資本という巨神兵なのである。一時に高エネルギーを湧出できる資本によって、化石資源依存型システムを破壊し、サステナブルな循環型地球システムの構築に向かう。まったく資本は使い方次第、毒をもって毒を制することもできるのだ。この資本の巨神兵にエネルギーを注入する当面の参加方法はファンド(投信など)を買うことである。(日本の個人金融資産のうち、眠っているに等しい現金預金は約900兆円以上ありポテンシャルは凄まじく高い。)
この時我々は、SDGsやESGをネタに値上がり期待のトレンドを追っているファンドではなく、「グリーンウォッシング」企業を排除している本物のESG投資ファンドに資金を投入し、そこで運用する。儲けたお金でまた投資をする。投資分野は気候変動対策、貧富の格差解消、感染症対策だ。
そして、自身が投資の成功体験を持つことで、他人にも奨めESGファンドの参加者を増やす。これによって、資本の巨神兵をパワーアップし、化石燃料で回っていくように最適化されている産業社会システムの破壊と再構築へと流れを変えていく一助とするのだ。
その時ESGファンドの性格も一様ではなく、ファンドマネージャーによってカラーやポリシーがある。我々が選ぶのは指標で投資する“パッシブ運用ファンド”ではく、明確なポリシーをもって個別銘柄選定に時間をかける、使命感のある“アクティブ運用ファンド”のファンドマネージャーである。
一方で、もし、読者が経営陣の立場であるなら、自社の企業理念を再構築し、地球的社会課題の解決をミッションとし、SDGsに本気で取り組む側に回る。社内経営システムを書き換えて、証券市場に上場し、資本の受け手となることは有効だ。
無論、それ以外にSDGsに参加する方法はある。
SDGs実践の一歩は、ステークホルダーとしての地球、生命に対する意識改革から
地球と生命に対し働きかけるには、まず、自分の頭で深く考えるために、ナウシカを全7巻読了することが一歩となる。マンガ版ナウシカは、解釈の多様性、多義性を秘めており独自の見方がいろいろ成り立つだろう。
その結果出てきたアクションが、100均ショップで観葉植物を買ってきて、育てるという行為でもよいし、道路わきに生えている草花の名前と生態を知るだけでも価値がある。路肩のわずかな植え込みにさえ、一言で表現できない多様な植物が存在している。例えば、「ホトトギス」という花があるが、この花は地味で毒々しく可憐である。
蟲の話をしてみると、都内23区内においてすら、蟲は多様に存在する。叢を成している木々の中には、クワガタも生息しているし、虹色に光る玉虫はもっと多量にいる。玉虫は、高い木の上を飛び回っているので、下からは見えないだけだ。
さらに粘菌は、もっとも注目すべき存在だ。微小な生物ながら一体の中に沢山の核を持ち、非細胞性の原形質のまま存在している。動物のように動き回り、他の微生物を捕食する特性と、菌類のように静止して胞子を飛ばす特性の両方を備え、環境に応じて集合体になり役割分担することもできるのだ。そして粘菌は他の生物の食物ともなり、食べる食べられるの生態系の中で、生死の無数の繋がりによって、系自体が成り立っていることを明示してくれる生き物である。
よく知れば、粘菌でさえ同じ生態系の仲間ととらえたナウシカのような感性を持つことは可能なのである。こういった生き物たちは普段より少し注意深く観察すれば、簡単に見つけ出すことができる。我々の傍にすでに息づいているのだから。
そして、最後に一言余計に言わせていただければ、芭蕉の句集を詠むことを推奨する。“山路来てなにやらゆかしすみれくさ”このような詩句に改めて触れると、より生命と宇宙が繋がっているリンクが目に見えるようになるだろう。紀貫之の言霊(ことだま)からはじまる、自然と我々の身体、意識が一体化している日本文化の連綿と続く精神。これを大衆芸術として表現していくプロセスで発生した俳句。一方で、マンガというサブカルチャーから生まれ出た現代芸術という接点に、ナウシカが存在しているという気さえする。芸術は直観を可能とする。ナウシカは粘菌~人類~宇宙を包摂する生命の世界を感じ、慈悲の心を持って生きる。個にして全体。全体にして個。恣意的な目的や、予定調和をめざすのでなく、生きるものを生きるものとして受け入れることができる存在者なのだ。
地球や生命というステークホルダーとの繋がりは普段我々が認識している以上に深く、複雑に絡み合っている。仏教用語の中に「芥子須弥を容る」という言葉があるが、これは一粒の小さな芥子粒の中に、須弥=ヒマラヤ山脈=大宇宙が内包されているということを示している。さらに言えば、一即多、多即一、一の中に多があり、多の中に一がある、相即相入の世界。この因縁によって絡み合っている関係を一言で言えば事事無碍法界(じじむげほうかい)ということになる。わかりやすくカタカナでいうと、マルチステークホルダー・インクルージョン(あらゆる関係者が包摂されている世界の様相)と言えるのかもしれない。ターゲットにしたもののみを上昇させていく、増やしていくことをゴールとする目的思考、因果律の解き明かしの産物である物質文明は一つの囚われの結果にすぎない。現実の世界の果ては因縁によって成り立っている。縁という関係性においてあらゆるものに慈悲を差し向けることで、地球の一員である我々は、何かに執着して求めなくても、もともと豊かさをもった本来の在り方に目を開くことができるかもしれない。
文:増山弘之